がん患者のQOLを高める「食楽」療法
全国でも先駆的な活動を行うPEACH厚木
「PEACH厚木」の名前は、「PerfectEating And Comfortable Health(最適な食環境と快適な生活をめざして)」の頭文字から名付けられた。江頭さんは、2000年に任意団体のPEACHサポートを設立し、訪問栄養指導を始めた。03年4月、PEACH厚木を発足。現在、江頭さんを含む3人の管理栄養士が、神奈川県厚木市を中心に、平塚市、座間市、伊勢原市、二宮町などで訪問栄養指導を行っている。
江頭さんは、以前、聖隷三方原病院(静岡県浜松市)の栄養科に勤務。同病院のえんげ嚥下チームのスタッフとして豊富な経験を持つ。現在、厚木医療福祉連絡会(00年4月発足。厚木市、愛川町、清川村の介護保険関連事業者が協力・連携して誕生した民間団体)の摂食・嚥下部会の幹事を務める。同連絡会の医師、歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、介護支援専門員(ケアマネジャー)、理学療法士、介護福祉士などと協力・連携して、訪問栄養指導に取り組んでいる。管理栄養士が独立して訪問栄養指導に取り組むのは全国的にも数少なく、先駆的な役割を果たしている。
現在、約40人の在宅で暮らす高齢者などの訪問栄養ケアを続けている。その中に在宅で療養生活を送るがん患者も含まれる。Aさんもその1人である。
ところで、在宅医療と病院に入院中の患者の栄養方法にはいくつかの方法がある。図2は、米国静脈経腸栄養学会(ASPEN)ガイドラインをもとに作成したものだ。患者の消化管機能の働きがよい場合には経腸栄養法、消化管機能の働きが悪い場合には静脈栄養法が選ばれる。
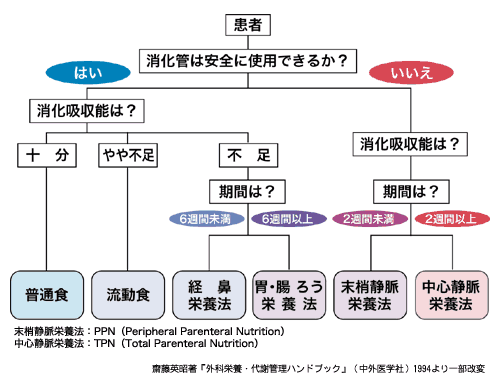
さらに、前者では消化吸収の状態によって栄養法が分かれる。消化吸収の働きが十分なときは普通食、やや不足のときは流動食、不足した場合でその期間が6週間未満なら経鼻栄養法(鼻から入れた管を通して胃・腸に栄養を送る)、その期間が6週間以上なら胃・腸ろうから栄養を送る胃・腸ろう栄養法が選ばれる。一方、後者の静脈栄養法の場合、その期間が2週間未満なら末梢静脈栄養法、その期間が2週間以上なら中心静脈栄養法が選択される。
日本ではこれまで中心静脈栄養法が主流で、栄養法全体の80パーセントを占めることもあったようだ。
しかし、最近、中心静脈栄養法は減少しつつあり、胃・腸ろう栄養法が増加中だという。PEACH厚木でも訪問栄養ケアをしている患者の20パーセントほどが胃・腸ろう栄養法の患者で占められる。胃・腸ろうからしっかりと栄養補給をしながら、口から食べる楽しみも得たいという願う利用者が多いという。
口から食べることで患者のQOLは向上する
中心静脈栄養法はカテーテルに起因する感染症、かゆみが出やすい、偏栄養などの問題点がある。とくに、入院中の患者の偏栄養が課題となり、入院患者の偏栄養問題を解決するために栄養サポートチーム(略称・NST。医師を中心に看護師、栄養士などが連携して、患者に適切な栄養管理を提供する)が全国の病院で普及しつつある。こうした病院の取り組みによっても、中心静脈栄養法が減り、生理的に優れた経腸栄養法が増加しつつあるという。
また、介護療養型病院でも中心静脈栄養法をやめて、経腸栄養法に切り替えるところが増えているようだ。厚生労働省もこうした取り組みに理解を示し、応援に乗り出した。今年10月の介護保険法改正で、「経管栄養から経口摂取に移行できるような取り組みをした場合」には加算(報酬)をつけて、経腸栄養法への移行をバックアップする予定だ。
「病院では中心静脈栄養法から経腸栄養法へ、さらに経口栄養法へ、わかりやすく言えば、チューブをはずして『自分の口から食べる』という栄養法が評価され、そうした動きが出始めています。将来的には在宅医療の現場も、そうした取り組みが行われるようになると思います。口から食べることで患者さんのQOLは確実に向上します。誤嚥などのリスクを伴うため、十分な介入が必要ですが、患者さんにとっては歓迎すべき動きだと思います」と江頭さん。
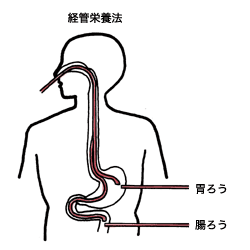
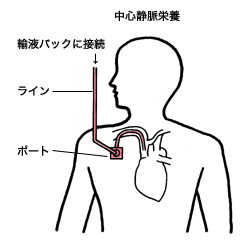
ところで、最近、「根拠の基づく保健医療(エビデンス・ベースト・ヘルスケア=EBH)」が叫ばれている。医療だけでなく、保健医療の現場でも根拠が求められる。そこで、興味深いデータ(ランダム化比較試験。「要介護高齢者に対する口腔衛生の誤嚥性肺炎予防効果の関する研究」米山武義ら。日歯医学会誌2001年。図4参照)を紹介しよう。
全国11カ所の特別養護老人ホーム入所者366名を対象に、無作為に口腔ケア群(日常的口腔ケアと週1回に歯科医師、歯科衛生士による専門的口腔ケアを行う)と対照群(従来のケアのみ)とに分けて、2年間調査を行った。その結果、口腔ケア群は対照群に比べて、発熱発生者数(15パーセント対29パーセント)と肺炎発症者数(11パーセント対19パーセント)でほぼ半分、肺炎による死亡者数(7パーセント対16パーセント)では半分以下に抑えられた。入所者に口腔ケアを行うことの有効性が明らかになった。特養ホームの入所者の要介護度(介護を必要とする度合い)は、在宅医療を受けている患者の要介護度とほぼ同じ。
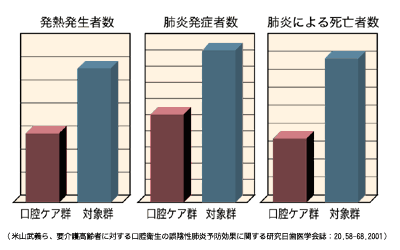
「この比較試験の結果は在宅医療の現場にも当てはまると思います。つまり、在宅医療でも口腔ケアをきちんと行って、口から食べられるようになれば、延命にもつながるのではないかと思います」と江頭さんは言う。
「スプーン一杯分でもいいから、おいしいものを自分の口から食べたい」という在宅がん患者の願いとその栄養ケアは、がん患者のQOLの向上はもちろん、延命効果につながる可能性と希望がある。
同じカテゴリーの最新記事
- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた
- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で
- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる
- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!
- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――
- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる


