明細書は、患者が質問しやすくしてくれるツールである スーパーでレシートをチェックするように、「診療明細書」もチェックしてみよう
イメージできない用語が質問される
明細書の記載内容についての質問に限ると、患者さんは、検査名や薬名など、自分で確かに受けたと思えることについては聞かない。点数の変化もそうだ。今春の診療報酬改定で大幅に点数が上がったがんの放射線治療も、医師から説明があるので、問い合わせはそう増えなかった。
明細書を手に、患者さんがよく質問するのは「費用項目について」。たとえば「判断料」「管理料」という聞きなれない用語に、「これは何ですか」と聞かれることが多い。これらは明細書が出なければ目にしなかった項目だ。
そこで実際の明細書例にそって、質問が集中するだろう用語をひも解いてみた。
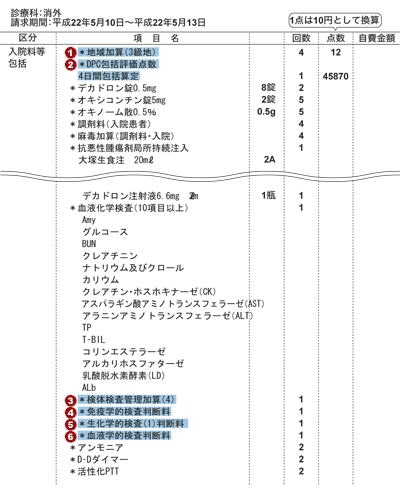
(1)「地域加算(3級地)」
都内23区などの大都市圏から、沖縄、北海道まで、すべての地域で決まっている加算点数で、1から4まであり、これで人件費や薬などの経費差を調整している。経費の低い地域と高い地域の不公平を緩和するもの。
(2)「DPC包括評価点数・4日間包括算定」
「DPC包括」は、03年4月から、特定機能病院など一部の病院で導入が始まった制度のこと。
DPCとは「診断群分類別包括支払い方式」。主な病気の種類別に、あらかじめ、薬(投薬・注射)+検査料+レントゲン料などをパッケージで決め、総額を設定したものだ(手術や放射線治療、リハビリテーション、内視鏡や心臓カテーテル検査や、千点以上の処置などは除外され、別に出来高払いの換算となる)。
ちなみに「包括」とは、医療費を抑えるために導入された制度。
出来高では、医療機関側は、治療も検査も行っただけ請求できたが、今は病院経営が厳しい時代。過剰な診療や、不要な検査をする施設がないとも言い切れない。しかし「この病気はこの額」と決めておけば、出来高制より医療費が抑えられ、患者さんにとってもわかりやすいものと言えるだろう。
では、具体的に見てみることにしよう。明細書(1)に記載されている検査だが、ここには点数の記入がない。これは各検査がすべてDPC包括の中に含まれるからだ。一方、明細書(2)に記載されている退院時処方の、オキノーム、オキシコンチンの2種類の薬は包括から外れるので、点数が入っている。
また同じ検査でも、EF―喉頭は包括ではなく、別途請求となるため、点数が記載されていることになる。
(3)「検体検査管理加算」
(4)「免疫学的検査判断料」
(5)「生化学的検査判断料」
(6)「血液学的検査判断料」
これらは皆、検査の判断料を指している。「判断料」とは、検査結果の判断行為に払われる料金のこと。
例えば、明細書(1)に記載されている「血液化学検査(10項目以上)」を行うと、その判断に「生化学的検査(1)判断料」が払われる。また、明細書(2)の上、「末梢血液像」「末梢血液一般」の判断には、「血液学的検査判断料」がつく。同じく明細書(2)の「C反応性蛋白(CRP)」とは、炎症反応の存在を調べる血液検査の1種で、この判断には「免疫学的検査判断料」が払われる。
このように検査ごとに判断料が対応しているというわけだ。
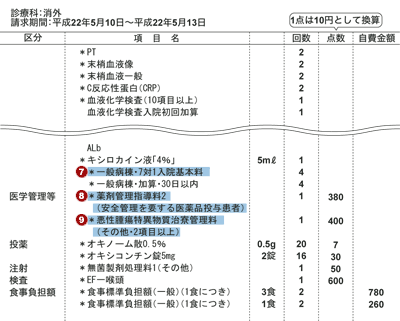
(7)「一般病棟・7対1入院基本料」
病院が、患者さん7人に対して看護師が1人という体制で診ている施設に算定されるもので、包括の中に含まれる。 なお、7対1というのが最も手厚い看護体制にあたり、20対1まで、その基準は6段階ある。
(8)「医学管理等」「薬剤管理指導料(安全管理を要する医薬品投与患者)」
きちんとした管理ができる施設のもとで薬を出している医療機関に払われるもの。 薬剤師が医師の同意を得て、服用の指導などを行った場合に、週1回だけ算定できる。
(9)「医学管理等」「悪性腫瘍特異物質治療管理料」
指導料の一種で、がんと確定診断された患者さんに行った腫瘍マーカー検査の結果に基づき、医師が計画的な治療管理を行った場合、月1回だけ算定できる料金。
質問は窓口業務の一端としてふつうに受け付け、返答

病院では、実際に質問をする患者さんにどう対応しているのか。
国立がん研究センター中央病院では、明細書の質問には、その明細書作成を担当した医療事務員が応対している。費目や点数などについての質問には、計算受付で返答。質問が治療や検査内容におよんだ場合は、2階にある外来の受付につなぎ、多くは看護師さんが対応する。それで済まずに医師と直接やりとりする必要があれば、その場がセッティングされるという手順だ。
どの段階でも質問受付は、担当者をとくには決めず、通常業務の中で行っている。
「最初の質問受付で、入力担当者が答えられるのか? とお思いでしょうが、算定入力担当者は、明細書に関してきちんと理解していないと入力できないのです。ですので、明細書の記述自体への質問なら、大体のことは窓口でわかると思います」と2人は話す。
また、質問に来る患者さんも説明を聞いて納得するケースがほとんどだという。
「どちらかというと明細書は、費用の確認より、医師に診療内容、治療の内容の問い合わせをするきっかけになることが多いようです。明細書を見て、『私は、こういう内容の治療をしているんですか?』と聞かれます。内容の話になると、もう1回外来に行ってもらって看護師が対応し、それで解消しないと医師に確認を取ってもらいます。医師が説明すると『ああ、そういうことだったのだ』となるのです」
多くは明細書に記載されている治療を受けたのに、別のものと勘違いしていたとか、医師の説明時に解釈の食い違いがあったなどだという。 「いずれにしろ、患者さんはもう明細書に慣れてふつうに質問に使っています」と、2人は話している。
わかりにくいからこそ質問受け入れ態勢を生んだ
診療明細書は、治療や検査の正確な記録である。ただ、取材を通してわかったのは、この明細書が、医療機関に「明細書を見た患者さんが質問してくる」と、強く意識させた書類であったことだ。患者の質問が「あるもの」として想定されたのは大きな変化と言えるだろう。
診療明細書は患者が費用面を聞くためだけのツールではない。専門用語だらけの文面で、医療機関と患者の間に介在することで、患者からの質問を当たり前にし、より実際的なコミュニケーションに向かわせてくれる、「患者の質問環境を用意してくれた」書類なのだ。
同じカテゴリーの最新記事
- がん患者、もう1つの闘い。お金が続かなければ……
- 仕事、教育費、相続問題まで、がんにかかわるお金のよろず相談に応じます! 医療費で困ったら、「ソーシャルワーカー」に駆け込もう
- 高額な医療費についての患者実態調査から見たがん家計の真実 つらいよ! がん患者が悲鳴を上げる高額な医療費生活
- 「患者が薬を選ぶ時代」にあって、信頼があり、より安価なジェネリック薬の選び方 積極的にジェネリック薬を利用して医療費を節約しよう
- 明細書は、患者が質問しやすくしてくれるツールである スーパーでレシートをチェックするように、「診療明細書」もチェックしてみよう
- アスベスト(石綿)健康被害者よ、救済の道を知って! 認定されれば、これだけの医療費、療養手当等が支給されます
- 高額療養費制度・高額医療費制度を上手に利用していますか 【大腸がんの化学療法を受けた場合】
- 福島県立医科大学・相良浩哉医師が提案するがん患者への経済的サポート 高額な医療費問題 こうして切り抜けよう


