- ホーム >
- 暮らし >
- お金 >
- 知っておきたいお金の悩み解決法
知っておきたいお金の悩み解決法 (4) 障害年金を受け取るために必要な条件
条件-2 障害認定日に障害等級に該当すること
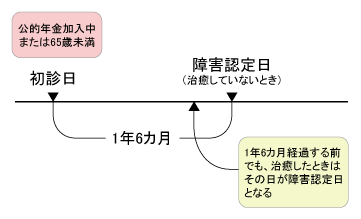
(2)の条件にあげた「初診日から1年6カ月経過した日」というのは、障害の状態について認定する日とされていますが、その前に治癒した場合は、その日が障害認定日となります(図2参照)。治癒というのは、治ったという意味ではなく、「その症状が固定し、今後治療を続けてもその効果が期待できない」状態のことを意味します。また、回復の見込みのない傷病による障害では療養中であっても、症状固定とみなし、初診日から起算した1年6カ月経過を待たずして、特例的に障害認定日とされる場合もあります(表1参照)。
| 主な傷病名 | 人工術等 | 障害認定日 |
|---|---|---|
| 慢性腎不全・糖尿性腎症 | 人工透析 | 施行日から3カ月経過日 |
| 不整脈・心臓弁膜疾患 | 心臓ペースメーカー・人工弁 | 装着日 |
| 骨折・関節の疾患 | 人工関節・人工骨頭 | 挿入置換日 |
| 肺気腫 | 在宅酸素(24時間) | 開始日 |
| 直腸がん・膀胱・前立腺疾患 | 人工肛門・人工膀胱・尿路変向 | 術の施行日 |
| 患部疾患・打撲 | 喉頭部・眼球部摘出 | 摘出日又は用廃日 |
| 事故等 | 事故による切断 | 原則として切断日 |
障害年金をもらうには障害認定日に障害等級に該当していることが必要です。障害基礎年金には1級または2級しかありませんが、障害厚生年金や障害共済年金では3級もあります。
障害等級の1級が一番重い障害で「他人の助けをかりないと日常生活ができない状態」、2級は「他人の助けはいらないが日常生活がかなり制限を受ける状態」、3級は「働くことにかなり制限を受ける状態」となっています。障害の程度を一言で説明するとこのようになりますが、実際にはその障害の部位や程度によってあらわれる影響はさまざまです。そこでこれらの基準を判断するため、障害の程度を等級ごとにあらわした「障害等級表」が政令により定められています。認定の際にはさらに部位ごとに細かく決められた「障害認定基準」により該当する等級が決定されます。
がんという病気の場合、その部位や種類、状態が実にさまざまなので、たとえば複数の部位で複数の症状がある場合などは、その部位ごとの診断書を作成してもらい総合的に判断してもらうことになります。なお、障害のある人が持っている障害者手帳���記載されている等級と年金法の障害等級とは一致していませんので注意が必要です。
障害認定日に障害等級に該当して認定を受けると、そこから障害年金の受給権が発生します。初診日から1年6カ月たった日の障害認定日には障害等級に該当せず、その後、障害状態が悪化して障害等級に該当するようになったときは、そのときに障害年金の請求ができます。これを「事後重症」といいます。請求が認められると、請求した翌月の分から年金が支給されます。ただし、請求できるのは65歳になる前までです。事後重症の場合注意しなければならないのは、請求して障害状態を認めてもらって初めて年金の権利が発生するということです。以前から明らかに障害状態にあったとしても、さかのぼって年金を支給してくれることはないのです。
条件-3 保険料をきちんと納めていること
最後に(3)の「保険料をきちんと払っているか」です。これを「保険料納付要件」といいます。これは、初診日の前日の時点で初診日の前々月までの保険料を納めるべき期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせて3分の2以上あること(保険料滞納が3分の1未満であること)、または初診日の前日の時点で、直近1年間に滞納期間がないことのいずれかをクリアすると障害給付が受けられることになっています。病院にかかった後にさかのぼってまとめて保険料を納めても、認めてはもらえません。保険料が払えないときの免除申請や学生納付特例はとても重要なのです。
【事例】 条件(3)がネックとなり受給できなかったケース
Aさん(35歳)は、直腸がんのため人工肛門(ストーマ)と人工膀胱の造設をしました。半年ほど前に転職した会社での健康診断で病気がわかり、今回の治療となったのです。Aさんの障害状態は障害認定基準からすると障害等級2級(人工膀胱のみは3級)に該当します。会社員であったAさんは障害基礎年金だけでなく障害厚生年金ももらえるはずでした。ところが、Aさんはそのどちらも受けることができなかったのです。ネックとなったのは条件(3)の「保険料納付要件」でした。
Aさんは、今までに何度か転職を繰り返してきました。途中、国民年金の保険料を自分で納める第1号被保険者になったこともありましたが、その保険料を納めたことはありません。老後の年金なんてあてにならない、と思っていたからです。Aさんの年金加入履歴は厚生年金9年間だけでした。これはAさんが本来納めなければならない期間15年間のうちの3分の2未満です。しかし、この原則がクリアできなくても、初診日前の1年間に滞納がなければいいのです。ところが、Aさんが前職を辞めて現在の会社に就職するまでに1カ月間の空白の期間があったのです。もしもこのとき、国民年金保険料を1カ月分納めているか、面倒くさがらずに保険料免除申請をしていれば、Aさんは障害年金を受給することができたのですが。
病気が長期化したら初診日に注意
障害年金をもらうための要件をみると、「初診日がいつなのか」、「初診日から1年6カ月」、「初診日の前日の保険料納付状態」というようにいたるところで「初診日」という言葉がでてきます。実際の障害年金申請では、現在の状態についての医師の診断書以外に、原則として初診日の証明も病院でもらう必要があります。受診している病院が最初から変わらない場合は問題ありませんが、転院している場合などこの初診日証明が取れずに障害年金の申請ができないケースもあります。カルテの保存期間は最終診療日から5年となっています。5年を過ぎたらすぐにカルテを処分するという病院は少ないでしょうが、初診日が10年以上前の場合だと、カルテがなくて初診日が証明できないということも少なくないのです。しかしながら、一方では患者に的確な診療を行うためにカルテ保存期間の5年を経過していても、「患者サマリー※」として既往歴を保存している医療機関も現在は多くなっています。
次回は、実際に受給している人の話を交えながら、障害認定基準等をご紹介します。
※患者サマリー=入院、外来通院患者の診療経過、治療経過を診療開始より現在まで時系列に集約し、現疾患の病状把握のために作成されるカルテのサマリー(要約)です


