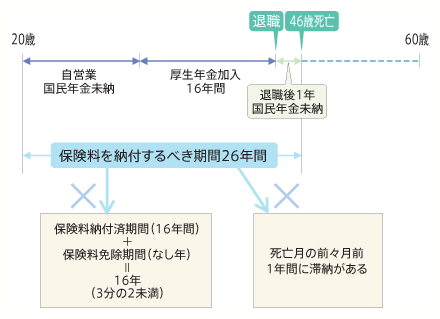遺族年金について知っておきましょう その1 知っていれば経済的に大きな安心
事例-2 退職後に国民年金の手続きをしなかった場合
昭和33年生まれのB男さんが死亡。残された遺族は、妻(43歳)、長男(16歳)、次男(10歳)。
B男さんは、会社の健康診断で肺がんが発見された。会社を休職して治療に専念していたが、再発がわかった時点で「これ以上会社に迷惑をかけては申し訳ない」と自ら退職を決め、会社に申し出た。
退職後の健康保険は、今までの健康保険被保険者資格を継続できる*任意継続被保険者となることを選び、社会保険事務所で手続きを済ませた。治療費は、国民健康保険加入でも任意継続被保険者でも同じ窓口3割負担だが、支払わなければならない保険料が任意継続被保険者のほうが安かったので、こちらを選んだのだ。
しばらくして、社会保険事務所から国民年金の*第1号被保険者保険料納付書が届いた。この頃、B男さんは入院していたため、妻であるC子さんが受け取ったのだが、C子さんはかさむ治療費を捻出するためにパートに出てその合間に病院に通い、肉体的にも精神的にも毎日ぎりぎりの状態だった。納付書のことが気にはなったが、「そのうちに……」と後回しにしているうちに、結局そのままにしてしまった。
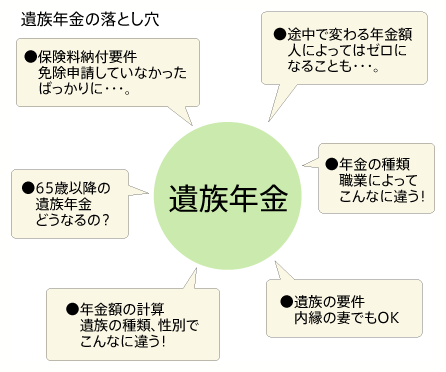
はっきり分かれてしまう明と暗
明 A夫さんの場合
- 遺族基礎年金
……月額約10万4千円
遺族厚生年金
……月額約4万7千円
合計 月額約15万1千円
A夫さんの厚生年金の加入期間は14年でした。最後に勤務した会社に入る前は自営業を営んでおり、そのころは国民年金の保険料を払っていませんが、病気で会社を解雇になってから亡くなるまでの1年半、国民年金の免除申請をしていました。
任意継続被保険者制度=会社退職後、健康保険被保険者資格を継続できる制度。支払うべき保険料に上限があるため、退職時の賃金が高額な人には有利となる場合が多い。ただし、加入要件もあり、退職時に傷病手当金を受けているとその後の給付額が減額となることもあるので注意が必要。
第1号被保険者=自営業者、フリーターなど国民年金の保険料を自ら納めるべき人。給与から保険料を控除される会社員は第2号被保険者。保険料が免除されているサラリーマンの妻は第3号被保険者である。
暗 B夫さんの場合
- 遺族年金……支給ゼロ
B男さんの厚生年金の加入期間は16年、それ以外の時期は国民年金被保険者でしたが、やはりA夫さんと同じく保険料を払っていませんでした。会社退職の1年後に亡くなりましたが、その間の国民年金保険料の免除申請は行っていませんでした。
どこが違ったのか
ふたりの年金加入履歴はほとんど同じでした。ここでのポイントは、国民年金第1号被保険者の免除申請をしたかです。
遺族年金を受けられるかどうかの条件のひとつに「保険料納付要件」というものがあります。これは、一言でいうと「納めるべき保険料をきちんと納めていたかどうか」ということ。「全被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あること」または特例措置として「死亡月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと」が受給の要件となります。
もしもB男さんが若いころの国民年金被保険者期間の保険料を納めていて3分の2以上の納付があったなら、もしも会社をやめてからの保険料免除申請をしていて、死亡前1年間の保険料滞納がなかったなら、A夫さんと同様の遺族年金を受給できたでしょう。
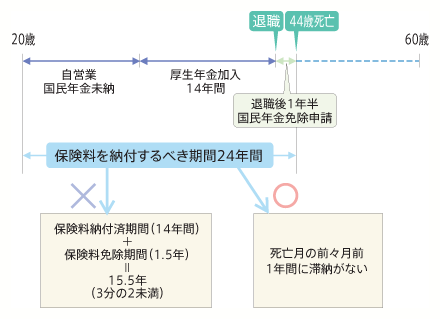
考えるべきこと
一家の大黒柱が病気で倒れて退職した場合、精神的な痛みはもちろんのこと、経済的にも毎月の給与収入がなくなり、治療にも費用がかかり、家計が逼迫することは容易に想像できます。
現在進行形でお世話になっている健康保険についてはどなたも必ず手続きをしますが、国民年金の保険料まで気が回らないことはよくありがちなケースです。でも、保険料を支払うことができないときの保険料の免除申請手続きは必ず行いましょう。
免除申請をしていれば、いざというときに遺族年金が必ずもらえると言うわけではありませんが、少なくとも「免除申請をしていなかったばっかりに……」という事態だけは避けたいものです。