遺族年金について知っておきましょう その3 「遺族」に該当するための条件
遺族年金の額
C夫さんが亡くなって遺族である妻D子さんは、「子のある妻」として遺族基礎年金が受けられます。遺族基礎年金は102万円で月額8万5000円、ここまでは事例1の自営業の夫が亡くなったB子さんと同じです。C夫さんは死亡当時、厚生年金の被保険者だったので、D子さんにはさらに遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の金額は、夫の在職中の平均月収(平成15年4月以降は賞与も含みます)と加入期間で決まります。加入期間が25年未満の場合は、25年とみなして計算してもらえます。仮にC夫さんの在職中の平均月収が30万円、15年4月以降の賞与を含めた年収が500万円、平成16年4月に死亡で厚生年金への加入期間が10年とすると、遺族厚生年金の額は約51万7000円、月額約4万3000円、平成18年4月に死亡で厚生年金への加入期間が10年とすると、遺族厚生年金の額は約52万4000円、月額約4万3000円となります。遺族基礎年金は子が18歳になると支給終了となりますが、遺族厚生年金は再婚しない限り終身で受け取ることが可能です。さらに、遺族基礎年金が支給終了となるとその後厚生年金からD子さんが65歳になるまで「中高齢寡婦加算」という年金がもらえます。これが年額59万4200円です。これらを整理すると、長男が18歳になるまでは月額12万8000円、長男が18歳になって以後、D子さんが65歳になるまでは月額約9万2000円がもらえるというわけです。
事例1の自営業者の夫が亡くなった場合と比較してみるとずいぶん違いますね。A男さんもC夫さんも年金加入暦はそれぞれ国民年金に10年、厚生年金に10年と同じです。死亡時にどの制度に加入していたかによってこれだけの差がでてくる場合があるのです。
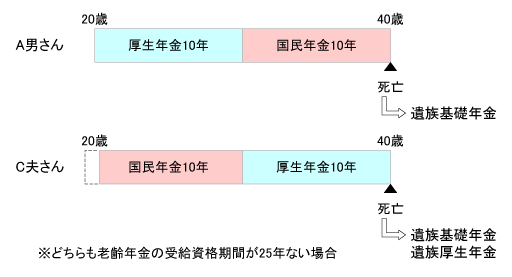
事例-4 共働きの家庭で会社員の妻が死亡した場合
事例3のケースで妻であるD子さんが亡くなり、夫と子が遺された場合を考えてみましょう。まず、夫であるC夫さんは扶養する子がいても「子のある妻」と「子」しか支給対象としない遺族基礎年金はもらえません。遺族厚生年金の遺族の範囲は遺族基礎年金と比べ表3のとおり、ずっと広範囲ですが、55歳未満のC夫さんは遺族厚生年金も該当しません。しかし、かわりに18歳未満の長男が18歳になるまでの4年間遺族厚生年金を受けることができます。遺族厚生年金は遺族基礎年金と違って受給権者の子が父と暮らしていても支給停止とはなりません。D子さんの平均月収が24万円、15年4月以降の年収が400万円、平成16年4月に死亡で厚生年金への加入期間が10年とす��と、もらえる遺族厚生年金の額は約41万4000円、月額約3万4000円、平成18年4月に死亡で厚生年金への加入期間が10年とすると、遺族厚生年金の額は約41万9000円、月額約4万3000円となります。また、C夫さんが亡くなってD子さんがもらえた「中高齢寡婦加算」は「寡婦」ではないC夫さんには当然でませんが、国民年金に3年以上かけていたので、事例2のA男さんと同じく死亡一時金12万円をもらうことができます。
現代社会とのひずみ
これらの事例をまとめたのが表4です。自営業者よりも会社員、夫よりも妻が優遇されていることがはっきりわかります。現在の年金制度が出来上がったのは今から40年以上前です。当時はほぼ100パーセント結婚し、夫は常用雇用者、妻は専業主婦で、離婚率は低く、とくに結婚生活20年以上の夫婦の離婚はまれでした。また、女性は結婚すると退職し、パートタイマーは少数派で、家計補助的な収入をえているだけでした。このような状況のもとでは、年金制度の対象は常用雇用者である夫であり、専業主婦世帯を優遇し、遺族年金も後に残された妻の生活を保障するものであればよかったのです。
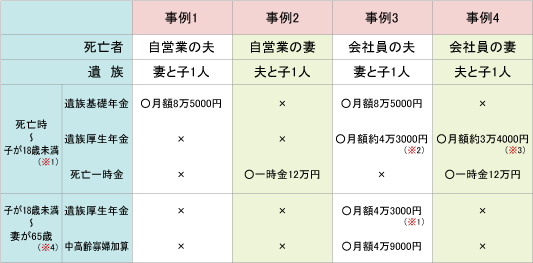
※1 18歳になって最初の3月末まで
※2 死亡者の平均月収が30万円、15年4月以降の賞与を含めた年収500万円厚生年金加入25年未満の場合
※3 死亡者の平均月収が24万円、15年4月以降の賞与を含めた年収400万円厚生年金加入25年未満の場合
※4 65歳以降は自らの老齢年金との調整、選択あり
ところが、少子高齢化問題だけでなく、人々の働き方やライフスタイルの多様化が、あるべき給付と現実社会との間に大きなひずみを生んでいます。これらの問題点も平成16年の年金制度改革で議論はされましたが、とても十分なものではありません。公的保障の不備な部分は自助努力が必要です。生命保険など万が一の備えを考える際は、特に自営業者の方、家計を支える妻がいる世帯では、公的年金額が十分ではないことを考慮して設計されることをお勧めします。
今回は、在職中の死亡で遺族厚生年金を受けるケースを取り上げましたが、遺族厚生年金を受給することができるのは在職中の死亡だけではありません。どこで線がひかれるのか、次回取り上げたいと思います。


