遺族年金について知っておきましょう その4 遺族厚生・遺族共済年金の給付のしくみ
初診日がいつかの違いで分かれた明暗
A男さんC夫さんの年金加入暦を確認しましょう。二人とも、大学を卒業してから厚生年金に加入していました。加入期間は16年間です。その後国民年金の第1号被保険者となり、その期間中に亡くなりました。遺族は、どちらも子どもがおらず、妻のみです。しかし、A男さんの妻B子さんには遺族厚生年金がでて、C夫さんの妻D子さんはもらえない、どこが違ったのでしょうか。
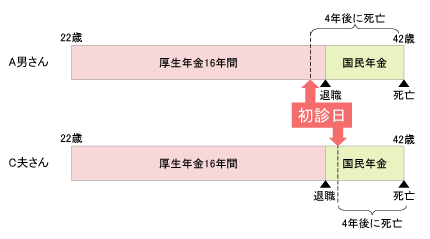
答えは「初診日」がどこにあったかです。A男さんが病院を受診したのは、会社を辞める前つまり厚生年金被保険者(国民年金第2号被保険者)のときでした。一方のC夫さんは在職中から自覚症状があったにもかかわらず、初めて病院を受診したのは、退職後、国民年金第1号被保険者になってからでした。
遺族厚生年金の受給要件では、「厚生年金保険加入中に死亡した場合」遺族厚生年金がもらえます。もう一つ、「厚生年金被保険者中に初診日のあるケガや病気がもとで、初診日から5年以内に死亡した場合」という要件があるのです。実は、この初診日要件は、遺族厚生年金だけでなく、障害厚生年金にも同じようなきまりがあります。「障害のもととなったケガや病気の初診日が、厚生年金保険の被保険者中であること」。初診日が、会社を辞める前か辞めた後かで分かれる明暗です。会社を退職することを考えているとき、気になる箇所があったら、退職する前にきちんと病院を受診するようにしましょう。ただし、どちらも納めるべき保険料をちゃんと納めていること(保険料納付要件)が、受給の要件となっています。
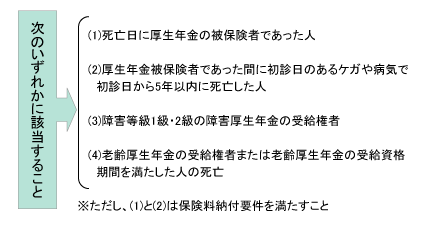
次に、初診日が厚生年金加入中ではないのに、遺族厚生年金がもらえたケースをみてみましょう。
事例-3 会社を辞めていたが30年加入していた場合
E雄さん(50歳)が死亡。遺族は妻F子さん(48歳)のみ。
E雄さんは半年前にリストラにあって職を失いました。現在は、失業保険をもらいながら次の仕事を探していますが、この年代ではなかなかこれといった就職先が見つかりません。やっと老人医療施設での送迎の仕事が決まりかけた矢先に、E雄さんは胃がんであることがわかり、治療のかいなく、亡くなってしまいました。
E雄さんが亡くなったのは、国民年金第1号被保険者のときです。胃がんについては、今まで本人が自覚症状を口に出したことも特になく��痛みを訴えたときが、初めて病院にかかった日でした。つまり、初診日も国民年金第1号被保険者だったわけです。
子どもはいましたが、一番下の子がすでに大学生、遺族基礎年金の受給権者となる18歳未満の子はいません。しかし、E雄さんの妻F子さんは、約11万1000円(注2)の遺族厚生年金を受けることができました。
注2=昭和29年生まれ、平均給与36万円、厚生年金加入期間30年間として算出
厚生年金加入期間で分かれる明暗
E雄さんの事例では、遺族厚生年金受給のもう一つの要件「老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たして死亡したとき」に該当し、遺族厚生年金が支給されたのです。
「老齢厚生年金の受給権者」とはすでに老齢厚生年金を受給している人や、手続きはまだしていないが、手続きさえすれば老齢厚生年金をもらえる権利のある人をいいます。「老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人」とは、年齢がまだ若いため老齢厚生年金をもらってはいないが、年齢以外の加入期間要件をすでに満たしている人のことです。E雄さんの場合、厚生年金に30年加入していましたので、受給資格期間を満たしていたわけです。
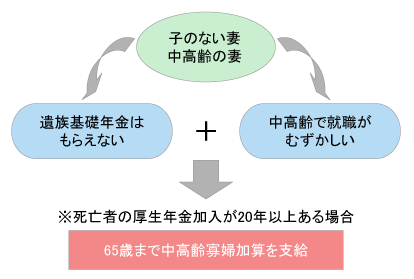
平成19年4月改正予定(表2の(4)の要件に該当する場合)
また、事例1のB子さんと比べると、遺族厚生年金の額がずいぶん多くなっていることに気がついたでしょうか。厚生年金加入期間がE雄さんの方が長かったことも関係しますが、実はそれだけではないのです。遺族厚生年金は、基本的に、亡くなった人の平均給与の額や加入年数(最低保障として300月未満のときは、300月として計算されます)が反映されます。ただし、亡くなった人の厚生年金加入期間が20年以上あり、遺族基礎年金がもらえない(子どもがいない)妻には、もう一つの給付があるのです。「中高齢寡婦加算」です。これが年59万4200円(平成18年度価格)、月額にすると約5万円が65歳になる前まで支給されることになるのです。表2の(4)の要件に該当する場合(例:国民年金への加入期間20年+厚生年金への加入期間5年でも25年加入で(4)に該当)、表2の(1)(2)(3)に該当し、夫が死亡した時に35歳以上で子のない妻には40歳から65歳まで中高齢寡婦加算が支給されます。つまりB子さんには40歳から支給されます。厚生年金加入期間が20年以上か未満か、これも遺族厚生年金受給の明暗を分ける要素の一つといえるでしょう。
次回は、遺族年金の受給者として大半を占める「妻の要件」についてお話します。


