遺族年金について知っておきましょう 最終回 給付される金額の変化について
事例-3 妻が老齢年金をもらう場合
会社員であるC夫さん(60歳)が死亡。遺族は妻C子さん(59歳)。
C子さんは現在遺族厚生年金、月額約10万円をもらっています。C子さん自身も厚生年金にずっと加入して厚生年金保険料を払い続けてきましたから、60歳になると自分自身の老齢厚生年金がもらえるようになります。このとき遺族厚生年金との関係はどうなるのでしょうか。
一人一年金の原則
公的年金は、老齢給付、障害給付、遺族給付をもらえる権利が複数あるときは、老齢年金と遺族年金など、支給事由の異なる年金を同時にもらうことはできないという「一人一年金」の原則があります。C子さんが60歳から老齢厚生年金をもらえるようになったときは、遺族厚生年金か自分自身の老齢厚生年金かどちらか一方しか受け取ることはできません。普通に考えると、年金額の高いほうを選べばいいのですが、実はそう単純ではありません。まず、遺族年金は全額非課税ですが、老齢年金は雑所得として課税の対象になります。また、60歳以降、勤務を続けて厚生年金に加入している場合は、給料の額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。これを在職老齢年金といいます。年金を選ぶ際には、これらのことから総合的に判断する必要があります。
C子さんの場合、老齢厚生年金額は月額で14万円、遺族厚生年金よりも高額でした。しかし、60歳以降も引き続き厚生年金に加入を続けるということで、在職老齢厚生年金(働きながらもらう老齢厚生年金)の額は月額8万円ほどとなります。結局、働いていても全額受け取れる遺族厚生年金を選ぶほうが有利ということになりました。
65歳になった妻の選択肢
遺族厚生年金をもらっているC子さんが、どの年金を選択するのか決めなければならない時期がもう一つあります。C子さんが65歳になったときです。さきほど、年金には一人一年金の原則があるとお話しましたが、例外のひとつが遺族厚生年金をもらっている妻が65歳になったときです。このときには次のような三つの選択肢が用意されているのです。
(1)妻自身の老齢厚生年金と老齢基礎年金
(2)遺族厚生年金と妻自身の老齢基礎年金
(3)遺族厚生年金の3分の2と妻自身の老齢厚生年金の2分の1と老齢基礎年金
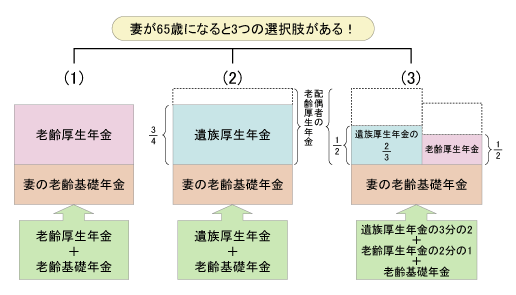
平成19年4月改正予定
どの選択肢の中にも妻自身の老齢基礎年金が入っています。これは、妻自身が払うべき年金保険料をきちんと納めていないと、65歳以降の年金額が減ってしまうこともあるということを意味しています。
どの選択肢を選ぶべきなのか、これは一概には言えませんが、妻がしっかり働いてきた場合は、(1)の「老齢厚生年金と老齢基礎年金」、妻自身の厚生年金加入暦が長くない場合は、(2)の「遺族厚生年金と老齢基礎年金」、そこそこ働いた妻ならば、(3)の「遺族厚生年金の3分の2と妻自身の老齢厚生年金の2分の1と老齢基礎年金」といったところでしょうか。
今まで6回シリーズで遺族年金について取り上げてきました。遺族年金は、老齢年金のように大多数がもらえる年金というわけではありません。しかし、いざというときにもらえる遺族年金は本当にありがたい給付です。複雑な点もたくさんありますから、もしものときには社会保険事務所の年金相談窓口で調べたり、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。あとで後悔することのないよう、納得したうえで手続きをしたいものです。


