- ホーム >
- 暮らし >
- 仕事 >
- 仕事をしながら療養する
傷病手当金、障害年金を上手に活用しよう
障害の状態など要件を認定してもらう書類を作成
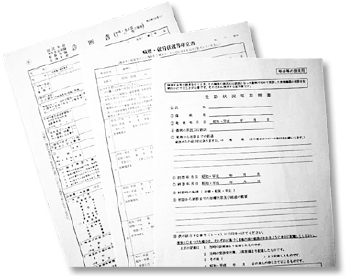
難点は手続きが煩雑でわかりにくいこと。受給要件は厚生年金・国民年金とも3つあり、❶障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医師の診療を受けた日)が年金の加入期間であること、❷障害の程度が、障害認定日に障害年金に定める級(国民年金は1~2級、厚生年金は1~3級)になっていること、*4 ❸保険料の納付要件を満たしていることだ。納付要件とは、加入している年金の保険料をちゃんと払っているかどうかだ。
今日要件が緩和され、上記❶の初診日の前々月から1年間に未納期間がなければOKだが、未納期間があると障害年金を受給できず、遡って納付することもできないので注意が必要だ。
受給が決定すると、1~2カ月後に年金の受け取りが始まるというものだが、手続はかなり大変だ。*5 申請書類の記入が煩雑で、そもそも納付要件を満たしていないと、申請用紙も受け取れない。
提出するのは「受診状況等証明書」、「病歴・就労状況等申立書」で(図3)、これに診断書など必要書類を添付するのだが、例えば「受診状況等証明書」は初診を証明するための書類なので、初診の病院に記入してもらう必要がある。しかし、カルテの保存期間(5年)を過ぎているなど証明が困難な場合は、当時の診察券を探したり、会社の総務部などに「この期間は病気で休んでいた」と証言してもらう必要がある。
初診日は障害年金を受給するために非常に重要なポイント。*6 障害認定日は初診日から1年6カ月後を経過した日だからだ。
認定されれば、認定日以降に請求しても、1年6カ月の日まで遡って支払われる。この意味でも、自分の今後の療養のスケジュールを思い描いて置くことは大事だ。
「カルテの保存期間である5年が過ぎる前に、初診の医療機関に証明書類をもらっておくといいでしょう。この証明期間には時効がありませんから」(石田さん)
「病歴・就労状況等申立書」も大変だ。初診から現在まで、がんのために受診した病院すべての治療期間とその間の状況、障害認定日の頃の状況、そして現状を書く。さらに、診断書は所定の用紙に現在の主治医に書き込んでもらう。両者の記述に不一致があると信頼性が低いとみなされ認定されないことがある。現状を医師に伝え、間違いなく書いてもらわなければならない。
*4=国民年金は20歳からの納入となるので、20歳未満の人や60歳以上65歳未満の人などは年金未加入でも受給できる *5=納付要件を満たしていれば担当機関のホームページからダウンロードもできる *6=人工肛門や人工膀胱を造設した場合は6カ月後の経過で認定される
給与が減った分を障害年金で補えた例も
体調の悪い人がこれらを揃えるのは大変なことに違いない。
「申請に行っても1回でOKとなることは皆無です。年金事務所で『平均何回くらい通えば手続きは終了しますか』と聞いたら、6回と言われました。『諦めました』という患者さんも多いのです」(賢見さん)
それでも認定されれば、障害基礎年金2級で年額約78万円、1級で約98万円、それに18歳以下の子ども1人に約22万円の加算がつく(3人目からは1人約7万円)。諦めるにはもったいない制度と言える。上手に利用した例について石田さんは語る。
「40歳代の女性で、傷病手当金を受給して休職していた方です。乳がん治療はうまくいきましたが、抗がん薬による末梢神経障害で指先に強いしびれが残ったため、パソコン入力が難しくなり、業務や勤務時間を変える必要が出て、相談にみえました。障害年金で3級が認められたため、減った給与に年金をプラスして、以前と同程度の収入が確保できたと喜んでいました」
思った以上に役に立つ傷病手当金や障害年金。多彩な制度を詳しく知るのは難しいが、上手に生かすには病院のソーシャル・ワーカーに相談することだと賢見さん、石田さんは声を揃える。
医師との間に入って調整をしてくれることもある。また、社会保険労務士のような専門家に相談するのも1つの方法。障害年金の申請は社会保険労務士が代行もしてくれる。賢見さんは言う。
「病気に備えて完璧に備えようと思ったら、大企業の会社員になるしかありません。でも、肝心なのは、安心して暮らせること。自分に使える制度がわかれば、それに合わせて支出を抑えるなど、生活をうまく切り替えられる人は少なくないと思います」


