がんとお金対談:がんになっても仕事がしたい…… 納得できる「就業」のための共助と自助
周囲の支援を引き出しやすい人
 高橋 ただ、人間同士ですから、支援のやりとりには人情もからみます。「がんになったけれど頑張っているあの人を助けたい」と周囲が感じる人もいれば、「これだけ助けているのになぁ」と思われてしまう人も。支援を受ける立場の人も、今できる貢献を考えたり、職場への感謝を示したりすることは、気持ちよく働き続けるためのコツではないかと思います。
高橋 ただ、人間同士ですから、支援のやりとりには人情もからみます。「がんになったけれど頑張っているあの人を助けたい」と周囲が感じる人もいれば、「これだけ助けているのになぁ」と思われてしまう人も。支援を受ける立場の人も、今できる貢献を考えたり、職場への感謝を示したりすることは、気持ちよく働き続けるためのコツではないかと思います。
私は、がんとQOLのことを長く研究してきましたが、就労という分野の特徴は、関与する人々が多いということと、問題の個別性がとても高いこと。なかなか難しいです。
黒田 その行動をサポートする体制はいかがでしょうか。
高橋 がん診療連携拠点病院の相談支援センターでは、看護師、臨床心理士、メディカル(医療)ソーシャルワーカー(MSW)らが相談にのりますが、現状では必ずしも就労関連の知識が高いとは言えません。
病院の外にどういう窓口があるかについてよくわかっていないことも。これからの課題です。
黒田 そうですね。メディカルソーシャルワーカーの方は、医療や公的制度のことには詳しいですが、民間保険や住宅ローン、ライフプランといった、いわゆる家計やマネープランに関することはあまりおわかりにならないようです。
それに対して、FP(ファイナンシャルプランナー)の守備範囲は幅広く、どの専門家にどのように橋渡しすればいいかわかっていると言えます。でも医療のことはわかりません。
高橋 厚労省では、産業カウンセラーやハローワーク職員の病院への派遣を始めました。院内外の専門家の連携は、一種、異文化コミュニケーションのようなものです。うまく連携するための方法を考えねばなりません。そういえば、FPは入っていませんね。
黒田 ぜひ、そこに入りたいですね(笑)。FP協会も無料相談をやっていますが、その場で特定の金融商品等は勧めません。相談者に対する営業活動も禁止です。あくまでも入口として、個別の事情に合わせて相談を受けています。
高橋 病院内のスタッフ以外にも院外の専門家が入ってくるとすれば、本人の説明力が一層大事になるでしょう。自分の状況をどこまで説明できるかは、本人と家族にかかっています。
専門家がいるだけで自動的に問題が解決するわけではなく、事情をきちんと説明してはじめて、個別の解決策を導くことができる。
黒田 自分で行動することが大切なのは、様々な補助を受けるときにもいえます。公的補助や民間保険など、すべてセルフサービスなのです。人は素晴らしい制度が天から降ってくる、誰かがしてくれると心のどこかで思っています。日本人は、制度やお金に対する知識が低いと言われています。社会保障や税、雇用保険などが給与天引きだからでしょうか。
高額療養費について話すと「知っている人だけが得をするのはおかしい」と言われたこともあります。
高橋 権利を活用するためには勉強も必要ですね。就業にしても、ただ「がんになったから、配慮して」と言うのではなく、配慮を引き出すつもりで説明することが必要。今の状況はこうで、3カ月後にはどうなっている見込みか。ただ、「頑張って説明力をあげよう」と本人にだけ言うのは酷だと思います。
医療従事者や相談支援センターにもまだまだサポートする余地がある。総力戦でいかないと。
就労の相談は患者さんの収入に直結します。最低限、治療を担当する医師は、早まってやめないようアドバイスをして、相談窓口への橋渡しをしてほしい。
準備された支援制度使うのはあなた
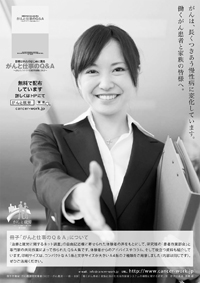 高橋さんの研究班が実施した調査に寄せられた体験者の声をもとにしたQ&A集の告知。体験者からのアドバイスやコラムも掲載(「がんと仕事のQ&A」)
高橋さんの研究班が実施した調査に寄せられた体験者の声をもとにしたQ&A集の告知。体験者からのアドバイスやコラムも掲載(「がんと仕事のQ&A」)高橋 企業での職位の面からいえば、若手も大変ですが、管理職の場合、部下への説明など管理職なりのたいへんさがあるでしょう。「自分がいないと会社が回らないと思ったが、休んでよかった。自分が休んでも代わりの人材はいた」と気づいた人もいました。大病をしたら、どんな職位でも働き方に影響が出ます。
黒田 収入面でいえば、会社員よりも自由業や自営業の方がたいへんです。
高橋 ネットワークをつくったりして、同業者での共助があるのでは。
黒田 もちろん、そうです。私も自由業ですから、働けない間は同業者に仕事をお願いしました。
私が仕事を続けているのは、がん患者でもこれだけ働けるということを周囲に知ってもらいたいからでもあります。「元気だよ。検査にも行ってるよ」と言うと安心する。何も言わなければ想像が膨らんでしまうでしょう。がんになったときに限りませんが、意思疎通をうまくはかることです。
本人がハッピーになるために「仕事への納得度」を考える
 「みんながハッピーになるために」と黒田さんと高橋さん(右)
「みんながハッピーになるために」と黒田さんと高橋さん(右)高橋 「がんと就業」は、これからサバイバーシップ支援のコアな部分になっていくでしょう。
黒田 患者さん本人がハッピーになるのが目標ですね
高橋 重要なのは、単に「仕事を続ける」ことではなくて、「仕事への納得度を上げる」ことではないかと。本人も職場関係者も、双方の納得度です。必要な情報を職場と共有し、継続的にコミュニケーションをとっていくことが大事ですね。
黒田 患者はすべて医師がお見通しでわかってくれていると思っている。
私は患者になって、自分で声を上げなければわからないことが多いことに気づきました。つらさや必要な配慮、できることについて、患者自身がきちんと考え、主張しなければならないということを多くの方に伝えていきたいですね。
本日はありがとうございました。


