薬の効果が高い人ほど現れやすい副作用。適切な対処をして治療を続けるには 「手足症候群」の初期症状を知って、セルフケアしよう
症状が重くなれば速やかに休薬する
| グレード | 皮膚の状態(臨床領域) | 日常生活への支障 (機能領域) |
| 1 | しびれ、皮膚知覚過敏、ヒリヒリ・チクチク感、痛みのない皮膚の腫れ・赤み、色素沈着、爪の変形 | 日常生活に制限を受けることのない症状 |
| 2 | 痛みのある皮膚の赤み・腫れ、爪の著しい変形や脱落 | 日常生活に制限を受ける症状 |
| 3 | 湿性のかさぶた、皮膚のはがれ、水ぶくれ、ただれ、強い痛み | 日常生活を遂行できない症状 |
症状が現れたら、「皮膚の状態」と「日常生活への支障」の両面から重症度(グレード)を判定する。グレードは図5のように3段階に分かれており、ポイントになるのはグレード2。グレード2になると休薬が検討されるからだ。
「手足症候群の有効な治療法は確立していませんが、休薬によって速やかに改善することがわかっています。そこでグレード2になれば休薬して回復を待ち、グレード1以下になれば投与を再開します」
ゼローダの通常の投与スケジュールでは、21日間または14日間の連日投与後、7日間の休薬日を設けている。グレード2以上で休薬する場合は、投与日でもすみやかに休薬し、グレード1以下に回復しても、引き続き通常の休薬期間も休薬を保ち、次コースの予定日から新たなコースで再開する(図6)。
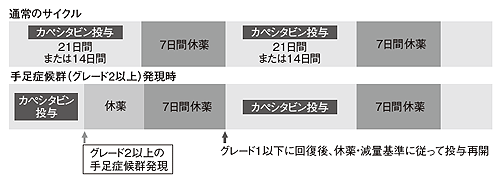
とくにグレード2以上の場合には、速やかに休薬をして、次サイクルの投与開始日に投与を始めるようにする
ゼローダの場合、休薬によって治療効果が下がることはない。ゼローダの投与を受けた266人を調査したところ、休薬した人はすべて手足症候群が軽快していたという。
ドキシルやネクサバール、スーテントでも休薬や減量の目安が示されているのでそれに従う。
「症状がグレード3と重くなると、その分、回復に時間がかります。そのため休薬期間が長くなり、治療再開が遅くなってしまいます。グレード2の段階で見極めて休薬し、グレード3に進行させないことが大切です」と田口さんは強調する。
「頑張って飲み続けてしまう患者さんが多いのですが、それよりもむしろ積極的に休薬するほうが治療を中止することが少なく、がんの治療効果が高まります。休薬して副作用症状の治りが早まれば、治療薬の投与を当初の予定どおりに再開でき、治療計画を守りやすくなるのです」
症状が強く出る人ほど薬がよく効いている
田口さんによると「化学療法における皮膚障害と効果の関係では、副作用が強く出た人ほど治療効果が高いというデータがいくつかある」という。
その1つが大腸がんの術後補助療法の標準治療である5-FU+ ホリナートカルシウム(*)とゼローダを比べた試験(X-ACT試験)。このゼローダ投与群で手足症候群が出た人と出なかった人の5年生存率(無病生存率)を比べると、出た人が61.3%、出なかった人が55.5%と、出た人のほうが治療成績がよいという傾向がみられた。
また田口さんが再発乳がんの患者さんに対するゼローダ単独投与について調べたところ、がんの大きさが半分になった人の割合は、手足症候群が出なかった人で約8%、出た人で25%。グレード2、3の人では約33%と、症状の重い人ほど薬によく反応していたことがわかったのだ。
「グレード2の手足症候群が出た患者さんは薬の効果が確認されたようなものです。グレード3や休薬後再びグレード2に至る人は効きすぎといってもいい。ですので、休薬後に投与を再開するには1段階減量します」
*ホリナートカルシウム=商品名ロイコボリン/ユ-ゼル
回復を促すため支持療法も大切
手足症候群は、症状が重くなるほど回復が困難になる。そのためステロイド軟膏を塗ったり、ビタミンB6を摂取するなど、副作用を軽快させる支持療法(対症療法)を積極的に取り入れて、回復を促進させる必要があるのだ。
どのグレードでも保湿を基本とするスキンケアは必須。グレード1なら保湿剤を用いて念入りなケアに努める。
保湿剤には、保湿効果に血行改善作用もあるヘパリン類似物質含有製剤(ヒルドイドなど)、手に傷がなければ尿素含有製剤(ウレパール、ケラチナミンなど)、ビタミン含有のもの(ザーネ、ユベラなど)、ワセリンがよく使われる。使い心地なども考慮して、自分にあったものを選びたい。選択に迷えば薬剤師に相談するのもよい。
| ◆ステロイド外用剤(軟膏) | |
| 薬 剤 | |
| 1. | はれ・赤みを認める皮膚炎部位に使用 |
| 2. | 抗炎症作用の強さとしては、 通常、ストロング以上を推奨 クロベタゾール ジフロラゾン ベタメタゾン ジフルプレドナート |
| 使用法 | |
| 1. | びらん/潰瘍を含むあらゆる病変に有効。 患部以外には塗らないように注意する |
| 2. | 刺激性はないが、べとつき感と照かりがみられる |
「水仕事や手洗いのたびに塗り直しましょう。シャワーや入浴後だけでなくいつでも塗れるときに塗ってください。とくに利き手は意識して多く塗るようにしましょう」
グレード2に進んだものは休薬と保湿ケアに加えて、炎症を抑えるステロイド外用薬を使用する。ステロイドは抗炎症作用の強さによってランクがあり、真っ赤に腫れていたら「ストロング」以上を使うべきだ(図7)。
「患者さんはステロイドを警戒するのか使用量が少ないようですが、それでは効果がありません。手のひら全体に塗るには、指先から第1関節くらいまでチューブから出してたっぷり塗り込んでください。怖がらずに正しい量をきっちり塗ればそれだけ効きます」
さらに皮膚の修復を促進するビタミンB6(塩酸ピリドキシン錠)を服用する。痛みがあれば、適宜手足を冷却することも効果的だ。
予防と悪化防止のため日常生活でも工夫を
「セルフケアをしっかりしている患者さんではグレード3に進むことは少ないという印象です」と田口さん。保湿の励行のほか、日ごろから心がけることとして以下ようにアドバイスする。
手足への刺激を避ける
・ジョギングや長時間の歩行などは足の裏に負担がかかるので控える。
・締め付けが強い衣服や靴下、靴など圧迫するものは避け、ゆったりしたものにする。
皮膚を守る
・石鹸や化粧品は刺激の少ない弱酸性のものを使う。
・保湿剤を塗った後は手袋や靴下で皮膚を保護する。
・水仕事やガーデニングなど土を触る際には手袋を。
あたためすぎを避ける
・血行が良くなると、薬剤が手足や爪に行き渡り症状が悪化することがあるので、長時間の入浴、炊事やシャワーのときの熱い湯に注意。
日焼けを避ける
・外出時は帽子や日傘を。日焼け止めクリームは刺激の少ないものにする。
症状を早期発見し、支持療法やセルフケア行うことが、手足症候群の悪化を防ぎ治療を継続するポイントだ。わからないことや、気になる症状、不安なことは何でも相談できるよう、医療スタッフといつでも連絡が取れるようにしてほしいと田口さんは呼びかけている。
※厚生労働省のホームページ( http://www.mhlw.go.jp/ )でも手足症候群について掲載されている
同じカテゴリーの最新記事
- 症状が長く続いたら感染併発やステロイドの副作用を考える 分子標的薬による皮膚障害
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 分子標的薬の皮膚障害は予防と適切な対応でコントロール可能
- 副作用はこうして乗り切ろう!「皮膚症状」
- 放射線治療開始前から副作用を推測して、患者に伝える
- 今後について決めるときに一番大事なのは「希望」
- 手足を冷やすことで抗がん剤の影響を減らし障害を軽減する 抗がん剤の副作用、爪・皮膚障害はフローズングローブで予防!
- 薬の効果が高い人ほど現れやすい副作用。適切な対処をして治療を続けるには 「手足症候群」の初期症状を知って、セルフケアしよう
- 皮膚障害が強く出るほど、薬が効いている証拠。だからあきらめないでケアを 分子標的薬による皮膚障害は出ること前提で、早めの対策を


