最初が肝心。最初から嘔吐をさせないことが抗がん剤治療の秘訣 やっかいな遅発性悪心・嘔吐に期待の新星制吐剤が登場
パロノセトロンの大規模臨床試験結果に注目が集まる
アプレピタントはMASCCのほか、ASCO(米国臨床腫瘍学会)、NCCN(米国国立包括がんネットワーク)などが公表する制吐療法ガイドラインで抗悪性腫瘍剤投与にともなう悪心・嘔吐の予防薬として使用が推奨されるなど、国際的に認められています。
一方のパロノセトロンは、近年の第2相臨床試験でパロノセトロン+アプレピタント+デキサメタゾンの併用が、高度・中等度催吐性の化学療法に有用であることがわかりました。
また、国内においてはパロノセトロン+デキサメタゾンと、旧世代のセロトニン受容体拮抗剤のグラニセトロン(一般名)+デキサメタゾンとを比較した第3相臨床試験を行った結果、シスプラチンなどの高度催吐性の抗がん剤と、乳がんでよく使われるAC療法〔ドキソルビシン(商品名アドリアシン)+シクロホスファミド(商品名エンドキサン)〕の引き起こす遅発性悪心・嘔吐に対しても、旧世代と比べて明らかに効果が高いことがわかりました。
この試験は私たちが昨年初頭に論文を発表し、国際的にも非常に注目を浴びました。
(1)千例を超える大規模臨床試験、(2)パロノセトロンにデキサメタゾンを加えた2剤併用の第3相臨床試験、(3)主たる目的が、遅発性嘔吐の抑制において2剤併用下のパロノセトロンの優越性―などが世界で初めての試みだったことがその理由です。
しかし、この研究が3剤併用で行われなかったこと、薬の用量が世界標準と違っているなどの理由で多くの議論を呼びましたが、結果を踏まえて、国際ガイドラインにいくつか変更が加えられました。
たとえば、シスプラチンと併用する制吐剤はどのセロトニン受容体拮抗剤でも同じとされてきましたが、2009年のNCCNのガイドラインでは「パロノセトロンを推奨する」という文言が追加されました。
また、MASCCのガイドラインでも、「催吐性が中等度の抗がん剤を使うとき、2剤併用の1剤としてパロノセトロンを推奨する」という文言が今年掲げられる予定です。
MASCCではさらに、乳がん���療で行われるAC療法に関して、「アプレピタントが使えない環境下では、パロノセトロンを推奨する」という文言も掲載される予定です。
AC療法の場合、薬剤そのものの吐き気の強さは中等度に分類されていますが、実際にはAとCの組み合わせにより吐き気が強まること、乳がん患者の多数を占める女性は、男性より吐き気が起きやすいこと(=女性という性そのものが嘔吐のリスク・ファクターとなっている)などから、「催吐性は中等度より高度」と考えられるようになっています。これに関しても、私たちのデータが影響を与えたと言っていいと思います。
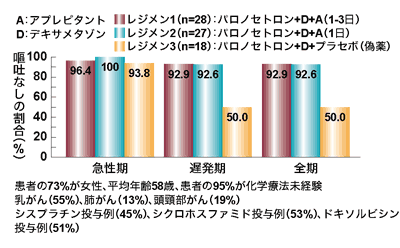
[パロノセトロンの嘔吐完全抑制率]
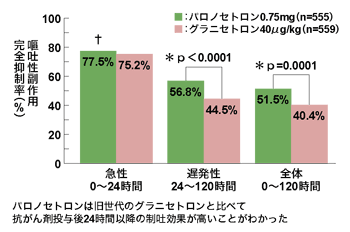
嘔吐を最初から起こさないことが抗がん剤治療の大原則
このように、20~30年で制吐剤は大きく進歩しました。患者さんが抗がん剤に抱く恐怖心も、ずいぶん減って来たと思います。
「抗がん剤は吐くもの」ではなく、「吐き気は薬でとめられる」と言ってさし上げられるようになったことは、とても大きいと思います。
日本でも、アプレピタントとパロノセトロンが承認され、アプレピタントには昨年12月に薬価(病院の薬の公定価格)がつきました。パロノセトロンにも今年4~5月には薬価がつく予定です。「今年抗がん剤治療を受ける方はタイミングがよい」と言えるくらい、よい状況になっていると思います。
アプレピタントは欧米では04年から当たり前に使われてきましたから、日本の状況は正直早いとは言えません。それでも、使えるようになって本当によかったと思います。
吐き気や嘔吐は体内に入った異物を排除しようという生体防御の反応で、生命維持のために欠かせません。しかも、その指令は1つではなく、複数の伝令によって伝えられます。何重にも防御されるようになっているのです。
心理的な吐き気もあります。
いやなものを見たり、いやな経験をすると、その経験を避けようという防御反応が起こります。ですから、抗がん剤治療の最初に嘔吐に苦しむと、2回目は薬を見ただけ、病院に来ただけで吐いたり、ムカムカするようになります。これを予測性嘔吐と言い、精神安定剤を投与する試みが行われています。
でも、大原則は第1回めの治療で嘔吐を起こさないことです。
急性期の悪心・嘔吐も、遅発性の悪心・嘔吐もしっかり抑え、「抗がん剤治療はいやな経験ではない」と患者さんに思っていただくことで、2回目以降の予測性嘔吐を防いでいく。
つまり、今日の抗がん剤治療は「吐かないのが当たり前」になりつつありますから、患者さんもそのことを知り、制吐剤をしっかり使っていただきたいと思います。
最新制吐剤2剤を使うときに、気をつけること
患者さんにも、知っておいていただきたいことがいくつかあります。
まず、どんな薬でも使いにくい状況があるということです。
たとえば、デキサメタゾンは糖尿病や胃潰瘍、鬱病などの精神疾患の患者さんには使わないほうがいいですし、ウイルスを活発にしてしまうため肝炎の患者さんにも向きません。
また、アプレピタントでは、一緒に使うデキサメタゾンと肝臓での代謝経路を共有するので、お互いの代謝に影響を与えます。ですから、併用療法でデキサメタゾンは少なめに使います。
副作用は便秘や頭痛が数パーセントずつで、セロトニン受容体拮抗剤もアプレピタントもほとんどありません。生命を脅かすような有害事象も、ありません。しかし、便秘は意外にしつこいので、がまんをせずに、薬を使ってコントロールしてほしいと思います。
もう1つ、アプレピタントは日本では飲み薬しか認可されていないため、抗がん剤治療の1時間以上前に投与しなければなりません。また3日間飲むのに1日目と2、3日目で用量が違っているので、間違わないように気をつける必要もあります。海外では承認済の注射薬(点滴薬)についても、早いうちに医療保険で使えるようになることを期待しています。
今後は経皮吸収、効果の持続性が高い薬の開発へ
最後に、抗がん剤治療にともなう正確な情報を患者さん自らが得ることを心がけていただきたいと思います。
たとえば、自分が治療している病院で最新の制吐剤がない場合、制吐剤の最新情報を知っていれば、患者さんが自ら、「最新の制吐剤であるアプレピタントやパロノセトロンを使っていただけませんか?」と聞くことで、薬を導入・使用してもらえるようになる可能性があります。
また、抗がん剤治療中の注意点としては、嘔吐が続いたり、悪心で水分摂取もできなかったりすると脱水の危険が高くなるので、水分補給を心がけることが大事です。脱水によって、脳梗塞などを起こすことも皆無ではありません。水分がとれない場合は病院に行って点滴を受けていただくなど、ご自分の体調にあわせ、細かく対応していただくことが大切です。
制吐剤の今後については、患者さんが治療を受けやすい方法の開発に向かうと考えています。たとえば、経皮吸収の薬や効果の持続性が高い薬(服用回数が少ない)の開発などです。
抗がん剤だけでも身体的・経済的に大変な負担なのに、その副作用を抑えるためにまた薬を使うというのは、気が進まないかもしれませんが、「吐き気を起こさないことが治療を続けるため、ひいてはがんを治すために必要」と説明しています。
制吐療法は、進歩しています。
どうか患者さんも抗がん剤を怖がらず、制吐剤などで症状をコントロールしながら、がん治療に臨んでいただきたいと思います。
同じカテゴリーの最新記事
- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明
- 大腸がん術後のQOLアップのために
- 婦人科がん化学療法における食欲不振に 六君子湯が効果発揮
- チーム医療で推進する副作用対策 オリジナル「患者手帳」と「冊子」の活用でQOLの底上げを
- 抗がん剤治療を受ける人のための新しい悪心・嘔吐対策 新しい制吐薬の登場で、悪心・嘔吐をこわがらなくてもいい時代に
- 最初が肝心。最初から嘔吐をさせないことが抗がん剤治療の秘訣 やっかいな遅発性悪心・嘔吐に期待の新星制吐剤が登場
- 抗がん剤治療中の吐き気と嘔吐は適切な予防で改善できる!
- 上手につきあうための悪心・嘔吐の管理術講座 ベッドサイドからみた患者さんと悪心・嘔吐
- 上手につきあうための悪心・嘔吐の管理術講座 悪心・嘔吐対策の実際~乳がん治療の場合~


