血液がんの上手な日常での副作用管理 感染症対策が最重要。骨髄移植した患者はとくに注意を!
出血に注意が必要
出血に対する注意も重要だ。
骨髄抑制により血液を凝固させる機能を果たす血小板が産生されなくなると、通常20~25万/μl(マイクロリットル)ある血小板数が減り、出血しやすくなるという。3万/μl未満になると皮下出血も起こしやすくなる。
「血小板が低下しているときは、容易に出血しやすく、また止血しにくいため体をぶつけたり、転倒したりしないように十分注意してください。例えば、薬の副作用で足が痺れているような場合も、感覚がなく転びやすくなります。小児の場合は動きも激しく突発的な動きをするためより注意が必要です。
また、口腔内に血腫ができていることがあり、そのような場合は、毛の固い歯ブラシは厳禁です。柔らかいものを選んで、やさしく磨くようにしましょう。鼻を強くかむのも、鼻出血の原因になります」
貧血になることもある。
赤血球数の減少により、酸素を運ぶ役割を担うヘモグロビンが低下したときだ。赤血球数が正常の70%程度になると、立ちくらみや転倒を誘発するようだ。59%以下になると息切れが起こり、40%以下では頭痛やめまい、耳鳴り、集中力低下、不眠、疲労感、手足の冷えなどが現れる。30%以下になると、食欲不振や吐き気、むかつきなどが現れる。ただし、個人差もあるため、その都度、主治医に相談することが大切だ(図2)。
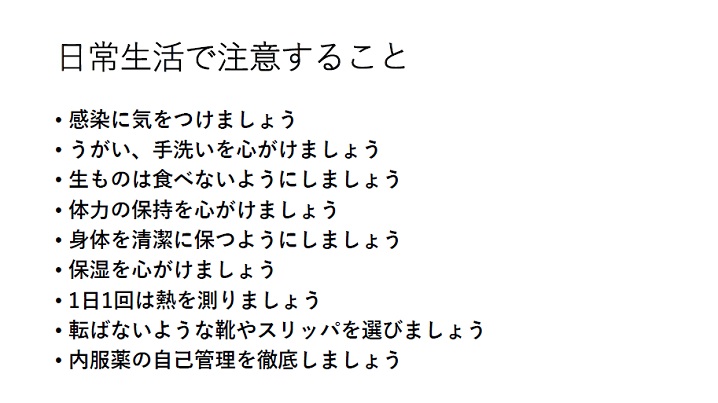
嘔吐した後は迅速に対応する
食事のQOLを低下させる副作用として、相互に関係しているのが、味覚障害、食欲不振、そして吐き気・嘔吐(おうと)だ。味覚障害や、吐き気・嘔吐が食欲不振につながる。
「味覚障害で食べるものが味気ない場合や、嘔気(おうき)で食事のすすまない場合、栄養士から食べやすいものをヒアリングしてもらい、自分の状況に合った食事のレシピや、食材をアドバイスしてもらうといいでしょう。
*口内炎の場合も、食事でのQOLに関わってくるため、同様に相談しながら対処していってください」
吐き気・嘔吐への対策は、制吐薬が内服と点滴であるため、ほぼ薬で対処できるが、嘔吐したあとは、すばやく対応することが重要だ。冷水、お茶などでうがいをしたり、サイダーのような清涼感のある炭酸系ものを少量飲むという方法もある。また、うがい水にレモン果汁を入れたりしてもさっぱりしてよい。
食べられないときは、お粥やうどん、ビスケットやクラッカー、そして、ゼリーやアイスクリーム、プリン、ヨーグルトなど食べやすい、さっぱりしたものがよい。
食欲と味覚障害とは関連性が強いため、脂っこいものは止めたり、温かい物はにおいが強くなるため、冷たいソーメンにするなど工夫が必要だ(図3)。
「日頃から食べられそうな物をリストにしておくのもいいです。あとは食欲が増すように、美味しそうに見えるよう器に気を遣ったりすることも大切です」(坂井)
*口内炎=詳しくは特集4に
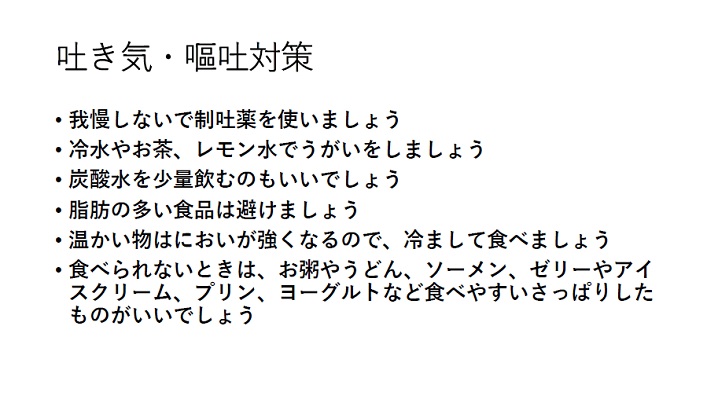
精神的につらいときはメンタルケアを受ける
メンタル面のフォローも重要だという。
初回入院時はもちろん、退院後も、繰り返し局面が変わる治療の状況に応じて対処しなくてはならない。
「最初は検査で血液がんの疑いが発覚すると、突然がんセンターへ行くように患者さんは告げられますが、症状のないような方は何が何だかわからなくなります。ところが病状によっては、その日から即入院即治療と告げられることもあるのです。
そのような場合は、ご本人もご家族も気持ちがついていけませんので、安心して治療に専念できるよう精神的な支援を心がけています」
場合によっては精神科の受診や臨床心理士によるカウンセリング、小児の場合はホスピタル・クラウン(道化師)の訪問や、様々な院内行事を行っているという。
「子どもさんの場合は、例えば治療のために通学していた学校へ通えず、院内学級に通うことになります。急に友人たちと会えなくなるなどつらい思いをすることになります。退院後も、入退院を繰り返すなかで心身ともにつらいことも多いですから、その都度対処が必要です」
患児の兄弟姉妹のフォローも大切だという。
「親御さんはどうしても病気の子の面倒に追われて、他の兄弟姉妹のことが疎かになってしまい、それが子どもたちの心の傷になることもあります。たまには患児を誰かに任せて、兄弟姉妹と触れ合ってあげるような時間を作ることも大切だと思います」(坂井)
調子が悪いと感じたら自己判断しない
血液がんの場合は、入退院を繰り返すケースが多く、繰り返しになるが、退院して日常生活を送る場合は、とにかく入院時に学んだ副作用対策を徹底するべきだ、という。
朝起きてから寝るまでに、「TO DOリスト」のようなものを作っておくと、ストレスを溜めずに、自然と生活サイクルの中に組み込んでいけるかもしれない。薬の内服についても、退院後は自己管理しなければならないため、リストを作っておくとよい、と坂井さんは話す。
「そして、退院後自宅で過ごすときに一番重要なことは、何かいつもと違う症状が出たり、調子が悪いと感じたときには、自己判断をせずに、些細なことでも病院に連絡して欲しいということです。例えば、熱を測って38度以上というような場合は、すぐ連絡してください」
治療時期、血液データの状況、病気の種類によって、主治医と看護師は、常に、個々の患者の対策を考えているという。
「ここでご説明したことはほんの一部ですので、必ずご自分が治療をしている病院のスタッフと相談しながら、よりよい副作用対策を身につけて、上手に日常生活を送ってださい」
同じカテゴリーの最新記事
- 接種したい4つのワクチンとそのタイミング がん患者・サバイバーのワクチン接種
- これまでの知見から見えてきた対応策 がん治療中のコロナ感染症
- がん患者での新型コロナウイルス感染症(COVID-19)防止対策
- 血液がんの上手な日常での副作用管理 感染症対策が最重要。骨髄移植した患者はとくに注意を!
- 見逃さないことが重要 化学療法時のB型肝炎の再活性化対策
- 副作用はこうして乗り切ろう!「感染症」
- がん闘病中の感染症対策 「手洗い」「うがい」で予防。徴候があれば医師に訴えて早めに対処
- 静岡県立静岡がんセンター感染症科の取り組みを追う 感染症対策はがん治療を確実なものにするために必要
- 患者にも医療者にも同様に危険な院内感染
- がん治療中のインフルエンザについてどう考える?


