がん闘病中の感染症対策 「手洗い」「うがい」で予防。徴候があれば医師に訴えて早めに対処
がん闘病中に気をつけたい感染症は?
肺炎、尿路感染、ライン感染などさまざま
がんの闘病中に起こりやすい感染症には、次のようなものがあります。
「いずれも、いったんかかるとセルフケアでは対応できず、ひどくなると治りにくくなり、命に関わることもあります。これらの徴候がみられたらすぐに医療者に症状を訴えてください」
まず、細菌が原因となって起こるものから――。
●肺炎
せきやたんが増え、発熱します。せきは風邪のときのような空せきではなく、たんがからんだような「湿性」のせき。たんも普段のように白色透明ではなく、黄色く粘り気があるのが特徴です。肺そのものに炎症があるので、ベッドから起き上がったり、作業をしたりするときに、息苦しさやだるさを感じることも多いもの。
風邪では鼻水、のどの痛みが出てくるのが普通ですが、肺炎でこれらの症状が出ることはあまりありません。ただ、風邪に肺炎が合併したり、移行したりすることもあるので注意が必要です。通常は抗生物質などで治療します。
「肺炎の中でも、誤嚥性肺炎というのは、食物を飲み込むときに食道ではなく気道に入ることが原因で起こるもの。口の中には細菌がいっぱいいますから、それが肺の中で増殖して炎症を起こすのです。誤嚥性肺炎は、食道がんや肺がんなどの手術後のほか、ターミナル期で体力が落ちているときなどにもみられます」
●扁桃腺炎
のどの両脇にある扁桃腺が感染症を起こして化膿し、発熱することがあります。
●胆道感染
消化器系、婦人科系のがんなどで腹部の手術をした場合、腸閉塞になることがありますが、それに伴い、胆道感染といって、胆汁を腸管へ輸送する管が感染を起こすことがあります。開腹手術をしている方で、吐き気や嘔吐、腹痛、悪寒などがあり高熱が出たときは、腸閉塞及び胆道感染の疑いがあり、緊急を要することもありますから、即刻医師の診察を受けてください。血液検査やエコー等で判断します。
●尿路感染症
頻尿や残尿感、排尿時の痛みなどがあるときは、膀胱炎や腎盂炎など、尿路感染症にかかっているかもしれません。尿道が長く、防御機構が働きやすい男性に比べて、尿道が短い女性のほうが発症しやすい感染症です。膀胱炎の場合は熱が出ないのですが、細菌が腎臓まで達する腎盂炎の場合は38~39度の高熱が出て、腰の両脇(背中側)が痛くなったり、たたくと響く痛みを感じたりします。手術の前後や、体力がなくて、トイレに行けないときに入れる導尿カテーテルの使用時は、尿路感染が起きやすいので、便などの雑菌が陰部に入らないように心がけ、陰部を清潔に保ちましょう。
●カテーテル留置時のライン感染
入院中は、前述の導尿カテーテルのほか、がんなどによって尿管が閉塞したときに腎臓から直接尿を排泄させる腎ろうチューブ、腹水や胸水を抜くドレーン、鎖骨下の静脈にさす高カロリー輸液用の点滴チューブなど、いろいろな管が入ることが多いものですが、これらの管が感染源になることがあります。皮膚にはもともと細菌が棲んでいますし、外から菌が持ち込まれることもあるからです。高熱が出たり、管の周囲に発赤、膿などがみられたら要注意。
●虫歯
意外とこわいのが虫歯。「高熱が出て感染症が疑われるのに、原因が見つからなくておかしいな、と思っていたら、虫歯が原因だった、ということがあります。神経を抜いてあると痛みもないのでわかりにくいもの。虫歯の菌が全身に回り、ショック状態から敗血症になり、命にかかわることもあるので、必ず虫歯の治療をしておいていただきたいですね」
●結核性の胸膜炎
免疫力の低下によって、もともと体内にもっていたり、外から入ってきたりした結核菌に対抗しきれなくなり、結核性の胸膜炎を起こすことがあります。なお、ステロイドの副作用として、結核の感染率が高くなるというデータもあるので、結核の既往症のある人は、その旨医師に伝えておきましょう。
「ステロイドは決して悪者ではなく、食欲を増すなどプラス面も非常に多いので、慎重かつ上手に使うことが大切です」
●炎症性乳がん創部の炎症
炎症性乳がんの創部(皮膚表面)に、細菌やカンジダなどのカビによる感染が起こると、ジクジクとただれたり、ニオイを発したりします。痛みやかゆみはあまりないのが普通ですが、患者さんの悩みは深いもの。
「抗生物質を投与しても改善しないときは、カビが原因と考えられます。この場合、ニオイや感染をおさえるフラジール軟膏を塗ると効果的です」
さて、ウイルス性の感染症で気をつけたいのは――
●帯状疱疹
体内にもっているヘルペスウイルスが増え、抑え込めなくなると、胸や顔など、神経節に沿って発疹が出る「帯状疱疹」が発症します。治療には、抗ウイルス薬の点滴静注剤、経口剤、外用剤などが症状に応じて使われます。
●インフルエンザ
「免疫力が落ちているときにかかると重症化しやすいので、予防のためにワクチンを打っておくことをお勧めします」
流行中は、人ごみを避けるなどの自衛策を。かかったときは、使用中の薬剤を医師に伝えて、併用できる治療薬を処方してもらいましょう。
感染症って抗生物質で治るの?
感染症は、細菌やウイルス、カビなどいろいろな種類の微生物が原因になっているため、原因や全身症状に合わせた治療が行われます。
細菌による感染症の治療には、抗生物質が使われます。結核の治療薬の1つ、ストレプトマイシンなどはもうおなじみでしょう。近年まで、医学の歴史は細菌との戦いの歴史でもありました。抗生物質の登場によって、その戦いに終止符が打たれたかに見えましたが、最近では、MRSA(耐性黄色ブドウ球菌)など、 抗生物質にも打ち勝つ強い耐性菌ができて、従来の抗生物質では効き目がなくなることが問題になっています。
なお、ウイルスやカビを原因とする感染症には抗生物質が効かないので、抗ウイルス薬、抗真菌薬などが使われます。
感染症予防とセルフケアの方法は?
予防には手洗いとうがいがいちばん。尿路感染には水分補給を
●1に手洗い、2にうがい
「予防は“手洗い”に尽きるといっても過言ではありません。患者さん本人も家族も、入院中なら見舞い客も、必ず手を洗って雑菌を流し去るのがなによりの感染予防策です」
手を洗うときは、普通の石けんをつけて、流水で15秒以上流します。手首まで洗うのがベスト。(下図参照)
「うがいにもウイルスや細菌を水際でせき止める効果があります。うがい薬を使ってもかまいませんが、うがいそのものに効果があるというデータがありますから、外出から帰ったときなど、水などでこまめにうがいをするといいでしょう」
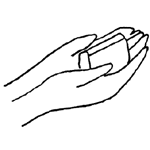
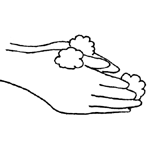
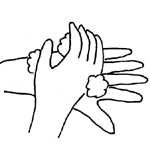
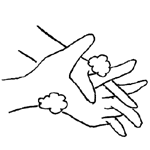




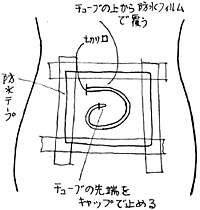
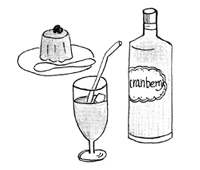
●入浴時は、シャワーで流す
手術後などは、医師の指示が出たらシャワーや入浴を開始。手術の傷口が治りきっていないときや炎症性乳がんの創部、床ずれなどは、シャワーで流すならOK。チューブが入っているときは、チューブの先を丸めてラップなどで覆い、まわりを専用の防水テープ(薬局で市販)またはビニールテープで密閉しておきます。「ただ、病院や医師によって指導法が微妙に違うことがあるので、医療者の指示に従ってください」
●尿路感染症なら水分を多めに
膀胱炎や腎盂炎などの尿路感染症の予防や改善には、水分を普段より多くとるのがコツ。
「お小水の流れをよくすると細菌などを洗い流すことができます。澱んでいると濁ってきて細菌が繁殖しやすくなるのです」
尿路感染には、画期的予防法があるそうです。
「クランベリーのジュースやゼリーをとると、尿が酸性化して尿路感染を防ぐことができます」尿路カテーテルが入っている方、膀胱炎などになりやすい方は、ぜひお試しを。
なお、女性は生理中なども、陰部を清潔に保つようにしましょう。便をふくときは、前から後ろへ。自己導尿をしている方も衛生面に注意してください。
●白血球減少時は人ごみを避ける
白血球が1000以下になったときは、人ごみや、劇場、デパートなど密閉された空間を避けて、感染を予防しましょう。
●虫歯を治療する
がんの治療前には虫歯や歯周病を治しておきましょう。
「感染症を生じやすいターミナル期の場合、私たち専門医も治療について悩むところです。ご本人だったらどう考えるか、家族の方も、そのような視点を忘れずに考えていただきたいと思います」
同じカテゴリーの最新記事
- 接種したい4つのワクチンとそのタイミング がん患者・サバイバーのワクチン接種
- これまでの知見から見えてきた対応策 がん治療中のコロナ感染症
- がん患者での新型コロナウイルス感染症(COVID-19)防止対策
- 血液がんの上手な日常での副作用管理 感染症対策が最重要。骨髄移植した患者はとくに注意を!
- 見逃さないことが重要 化学療法時のB型肝炎の再活性化対策
- 副作用はこうして乗り切ろう!「感染症」
- がん闘病中の感染症対策 「手洗い」「うがい」で予防。徴候があれば医師に訴えて早めに対処
- 静岡県立静岡がんセンター感染症科の取り組みを追う 感染症対策はがん治療を確実なものにするために必要
- 患者にも医療者にも同様に危険な院内感染
- がん治療中のインフルエンザについてどう考える?


