上手につきあって更年期を快適に! PART-1
心理的、社会的環境も更年期の症状に影響
更年期を迎える年代は、子供の独立や親の介護など、身辺に急激な変化が起こりやすい時期。
がんの患者さんの場合は、再発や命への不安を抱えていることが多いので、症状がより強く出る傾向があるようです。
「ホルモンの問題だけではなく、社会的、心理的な環境も更年期の症状に大きな影響を与えます。夫婦関係のトラブルが背景にある方も多いですね。イライラして眠れないと言って来院し、夫婦の悩みを話してすっきりして帰る方もいます。こういう場合は婦人科ではなく、カウンセリングのほうが合っているかもしれません」
なお、手術による卵巣摘出や放射線照射などで、20~30代の若いうちに卵巣機能が損なわれたときは、通常の更年期より症状が強い傾向があるそうです。
「普通はだんだんにエストロゲンが減っていって軟着陸するのですが、手術などで突然ホルモンが断たれたときはドスンと着地することになりますし、心理的負担も加わってつらさも大きいと思います」
子宮やその周辺組織を摘出しても、片側の卵巣が残っていればエストロゲンは分泌され、理論的には更年期症状は出ないはず。
「でも、子宮を失ったという心理的な喪失感のためか、症状を訴える方もいます」
更年期かしら?と思ったらSMIでチェックして
自分が更年期かどうか知りたいときや、症状の強さを判断したいときに便利なのが、簡略更年期指数(SMI)という表3です。
「日本人向きに作られたSMIは、臨床現場でもよく使われるものです。各項目に○をつけ、合計点を出すだけで、自分でも更年期の状態をチェックできます。
このほか、朝、寝床の中で基礎体温を計り、2、3カ月グラフをつけてみてもいいでしょう。
グラフが低温層と高温層の2層に分かれない場合は、排卵がないと考えられ、更年期に入っている可能性が高いですね。
産婦人科で血液検査をしてホルモンの値を計れば、さらに正確な判定ができます」
血液検査では、一般にエストロゲン(エストラジオール=E2)と卵胞刺激ホルモン(FSH)を計ります。
「更年期のホルモン環境では、エストロゲンの値が低く、エストロゲンを分泌させようとするFSHの値が高くなります」
「簡略更年期指数」(SMI)
| 症状の採点(点数) | 強 | 中 | 弱 | なし | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顔がほてる | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | 汗をかきやすい | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | 腰や手足が冷えやすい | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 4 | 息切れ、動悸がする | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 5 | 寝付きが悪い、眠りが浅い | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 6 | 怒りやすく、すぐいらいらする | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 7 | くよくよしたり、憂うつになることがある | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 8 | 頭痛、めまい、吐き気がよくある | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 9 | 疲れやすい | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | 肩こり、腰痛、手足の痛みがある | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 合計 | |||||
| 合計点 | 評価 |
|---|---|
| 0~25 | 問題なし |
| 26~50 | 食事、運動に気をつけ、無理をしない |
| 51~65 | 更年期外来で生活指導カウンセリング、薬物療法を受けたほうがよい |
| 66~80 | 半年以上の治療が必要 |
| 81~100 | 各科の精密検査を受け、更年期障害のみなら、更年期外来で長期の治療が必要 |
エストロゲンの代わりに大豆が有効。ビタミン、カルシウムもたっぷりと
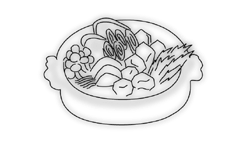
症状が気になるときは、まず、SMIで自己チェック。点数が低ければ食事をはじめ、日常生活に注意するだけで改善できることが多いものです。
「食物としては大豆や豆腐、納豆などの大豆製品がおすすめです。大豆に多く含まれるイソフラボンは、フィトエストロゲンといって、エストロゲンの中でも活性の高いエストラジオールと構造的・機能的に似た植物性の成分で、科学的なエビデンスも報告されています」
週2回以上、ホットフラッシュを経験している、閉経後の女性58人を2つのグループに分け、大豆抽出粉を12週間食べた人と食べない人を比較したところ、食べたグループの40パーセントは、症状が減少(出典・注1)したといいます。
「エストロゲンが減ると、コレステロールが増える傾向がありますが、大豆たんぱく質の豊富な食事をとることで、コレステロール値をおさえる効果もあります」
症状と栄養も、相関関係があります。
「不眠はビタミンB2とカルシウム、ビタミンB1、C、A、鉄、イライラはカルシウムやビタミンB2、気分が沈む症状はビタミンB1、肩こりはビタミンAの不足で強く出るようです(出典・注2)。ビタミンやミネラルもたっぷり補給しましょう」
ビタミンB1は豚肉、うなぎ、B2は乳製品や納豆、ビタミンAはレバーやニンジン、ホウレンソウなどの緑黄色野菜に豊富に含まれています。
(出典)
注1=『EBMを考えた産婦人科ガイドラインUpdate』(メディカルビュー社)「フィトエストロゲン/Murkies Al,et al.Maturitas 1995:21-3」
注2=『産婦人科治療』vol87 2003/9(永井書店) 『更年期の不定愁訴と栄養』(柴田みち他)


