患者さん自身でできるセルフケアもある 口の中をキレイにして味覚障害を改善しよう!
「しみる」ことがなくなれば味覚障害の改善も
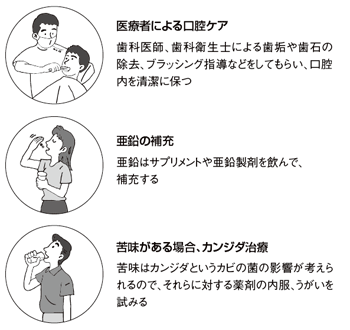
「まったく味がしなくなった」「味が変わった」など味覚障害の症状はいろいろだが、青木さんらが着目したのは「しみる」という訴えである。
「たとえば『レモンをかけていたのをやめている』とか『酸味が強く感じられるので、お寿司がこわくて食べられない』と言う患者さんに詳しく状態を聞くと、食事がしみて痛むので困っているということがわかりました。しみて痛いというのは抗がん剤で起こる口内炎の症状に似ています」
そこで口内炎の治療に準じて、「しみて痛い」と味覚障害を訴える患者さんにも、歯垢や歯石の除去を行い、ブラッシングを指導し、口の中を清潔に保つようにすると、味覚の異常も軽減、改善される患者さんが多かったという。
「歯に付いている細菌の塊、歯垢は酸を産生します。その酸で酸っぱさを感じることも考えられます。また経験的なことではありますが、カンジダ菌が多くなると、苦味を訴える患者さんが多いように思います」
患者さんにできる味覚障害の予防と対策
では味覚の障害が出てきたら具体的にどうすればよいのだろう。また、予防することはできるのだろうか。
青木さんは「抗がん剤で味覚障害になってしまったと思うより、自分で口腔内を清潔に保つことができれば障害が軽減できるという発想をしていただくのがいいかもしれません」とアドバイスする。
以下、青木さんに「患者さん自身でできること」を挙げてもらった。味覚障害は治らないと諦めるのではなく、試していただきたい。
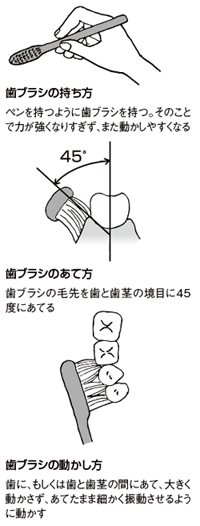
[歯ブラシ以外の清掃補助用具]
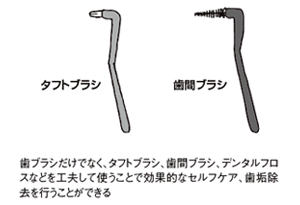
①プロの手で口腔内を清潔にしてもらう
歯科医師の立場から言うと、口の中を清潔にすることがなによりの対策です。
まず抗がん剤治療をすることが決まれば歯科を受診し、虫歯や歯周病の治療を終えてください。たとえそのときに痛い歯がなくても、抗がん剤治療で体の免疫力が落ちると虫歯や歯周病が生じたり、口内炎が悪化したりしますので、その前に原因となる口の中の細菌をできるだけ減らしておきます。
細菌の数を減らすには、まず、歯科医師や歯科衛生士による専門的口腔ケアにて歯垢や歯石を取り除きます。歯垢や歯石が付着した部分は表面がざらついているのでさらに歯垢がつきやすくなっています。歯の表面をつるつるにしておくと歯に新たな汚れがつきにくくなります。
次に、そのつるつるの状態を保てるように、自身での歯磨きの仕方を習得してください。
②ブラッシングで口の中を清潔に保つ
食べ物のかすはうがいで除去することができますが、細菌の塊である歯垢はうがいでは除去することができません。歯ブラシなどでこすりとることでのみ、歯垢を除去することができます。毎日、正しいブラッシングをしていただくことが重要です。
ただ、やはり治療中は身体のだるさなどもあると思いますので、歯科医師や歯科衛生士に磨き残しのあるところをチェックしてもらい、そこだけでも無理のない程度でブラッシングしてください。
当科では、抗がん剤治療で受診された際に当科も受診していただき、歯科衛生士により口腔ケアを行います。舌に近い上下の奥歯の内側などの歯垢を除去することで、「味が変わりました」とおっしゃる患者さんもおられました。
また、口腔外科のない病院で抗がん剤治療を受けられている患者さんは、地域の歯科医院で口の中をきれいにしてもらうことができたらいいと思います。地域の歯科医師会に問い合わせると、紹介していただけると思います。かかりつけの歯科医院を持つことが大切です。
③味覚を自己評価して栄養士に相談してみる
「甘味」「酸味」「苦味」「塩味」「うまみ」がわかるかどうか、それらがどのように感じるかどうか評価してみてください。わからなければ、一緒に食事をするご家族などに協力してもらいましょう。
また、食事の温度によって味の感じ方に変化がないか意識してみてください。細かく分析するとわかる味があると思います。たとえば「温かいスパゲティは不味いけれど、冷たいものは大丈夫」とか「醤油をかけた玉子焼きは食べられるけれど、みりんで味付けした甘い玉子焼きはだめ」とか。自身で美味しく感じる味を評価することで、調理方法や味付けを工夫してみてください。
食事については、ご自身で味覚を評価・分析したことを食のプロである栄養士に相談することをお勧めします。
一般に熱いものよりも冷たいもののほうが口当たりがよいため食べやすいようです。ちなみに関西地方では、食欲がないときには麺類やたこやきなどの「粉もの」が患者さんには好まれるようです。
④味覚の異常を医療者に伝える
「味覚は個人差があるから言ってもわかってもらえない」と諦めずに主治医にお話しください。患者さんが味覚の異常をどう表現をするのか、また「こんな工夫で乗り切った」という話は私も注意深く聞くようにしています。そして「よく似た症状の患者さんはこんなふうにしているとおっしゃっていましたよ」と別の患者さんにお伝えすることがあります。患者さんの経験というのは別の患者さんに役立つことも多いものです。
そして食べることをサポートする職種として、歯科医師と歯科衛生士がいることを覚えておいていただき、ご相談くださればうれしいです。おいしくごはんが食べられる口の中にしておいてくださいというのが歯科医師からのメッセージです。
同じカテゴリーの最新記事
- 化学療法治療前からの口腔管理で 口腔内の合併症を防ぐ
- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策
- 副作用はこうして乗り切ろう!「抗がん薬治療中の口内炎」
- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート
- 抗がん薬・放射線治療による口腔粘膜炎 事前準備で症状は緩和できる
- 口腔粘膜炎:重視され始めた口腔ケアによる合併症の予防効果とは 歯磨き、うがい、歯科受診で口腔粘膜炎を予防しよう
- 抗がん薬の副作用で起こる口内炎を短期間で治す漢方薬「半夏瀉心湯」
- 化学療法の副作用対策の重要性を、患者さん自らしっかりと理解することが大切 注目!粘膜炎(下痢・口内炎)の改善が期待される成分栄養剤
- 患者さん自身でできるセルフケアもある 口の中をキレイにして味覚障害を改善しよう!


