抗がん剤治療の新しい支持療法として期待され、臨床試験開始 見直され始めた成分栄養剤の口内炎軽減効果
休まず治療すれば成績も上がる
その結果、2002年以前と以降とでは治療成績の違いが大きく出た。CR(完全寛解)達成率を比較すると、2002年以前は44パーセントだったのに対し、それ以降では、なんと69パーセント、3年生存率では40パーセントだったものが65パーセントにまで伸びた(図5)。
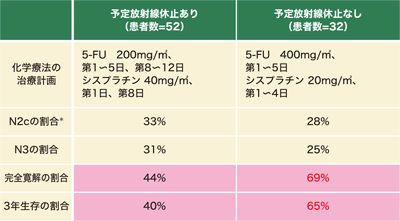
「この例を出すと昔の患者さんと進行度が違っていて、比較できないのではと批判する医師もいますが、そうじゃないです。たとえばリンパ節転移の度合いで比較すると、N2Cでは以前が33パーセントに対して28パーセント、N3だと31パーセントに対して25パーセントと転移の度合いが違っても大した差はありません。つまり、単純に治療を休むか休まないかの差で、結果が大きく違うことが明らかとなっているんです」
この結果を受け、さらに治療成績を向上させるために新しい臨床試験が考え出されることになった。これまで行ってきた抗がん剤治療5-FU(一般名フルオロウラシル)とシスプラチンの組み合わせのうち、5-FUをTS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)に替えて行う試験だ。
手術ができない頭頸部がんの標準治療?
これは『JCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)0706根治切除不能な頭頸部扁平上皮がんに対するS-1(※)+CDDP(シスプラチン)を同時併用する化学放射線療法の第2相試験』と呼ばれる臨床試験で、厚生労働省の研究助成金でJCOGの多施設共同研究として行われたもの。
「現在までに45例の登録が終了していますが、この調子でデータを積み重ねていけば、ようやく日本も海外と同様にしっかりとした日本発のエビデンスを発表していけるような体制が整ったということになります」
データの蓄積には最低でも5年はかかるが、もしこの治療法の効果が証明されれば、手術ができない頭頸部がんにおける日本の標準治療が確立することになるようだ。
※文中の「TS-1」と「S-1」は全く同じ薬剤
多施設共同試験で成分栄養剤の効果を検討へ
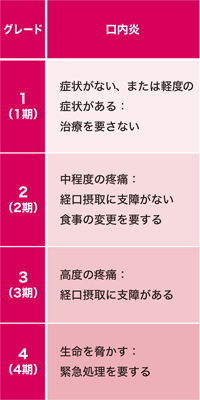
そうなるとますます重要になってくるのが、支持療法による副作用対策。なかでも、頭頸部がんの場合、口腔内周辺に放射線を当てるため、口内炎など、粘膜炎の発症頻度が非常に高くなるという特徴がある。ところが、疼痛薬や制吐剤などと違って、粘膜炎を抑える薬は現在のところまだ存在していない。
「支持療法の重要性は分かっており、さまざまなデータを精査すると、グルタミンに粘膜傷害を阻止、防御する作用がありそうだということがわかってきたんです」
そこで田原さんが注目したのがエレンタールだった。エレンタールは、腸管からほぼ100パーセント吸収される成分栄養剤。このエレンタール80グラムの中に、グルタミンが約2000ミリグラム含まれているのだ。これであれば、患者さんの体重低下を予防しながら、抗粘膜炎作用も十分期待できる。まさに一石二鳥だ。そこでこの効果を調べるために、従来の栄養剤と成分栄養剤エレンタールとの比較試験を現在計画中である。
「これまで栄養剤で粘膜炎に有効なものはなかったので、エレンタールの抗粘膜炎作用には大変期待しています」
田原さんの期待どおり、実際に臨床研究として成分栄養剤の副作用軽減効果が認められれば、今まで治療法がなかった口内炎対策に、初めてきちんとしたエビデンスが示されることになるわけだ。
支持療法成功の決め手はチーム医療の確立
主たる化学放射線療法を栄養管理面、副作用対策として文字どおりしっかり支えるのが支持療法なら、支持療法をきちんと機能させるのがチーム医療だ。なぜなら支持療法とひと口に言っても、その内容は体調管理から経済的問題の解決まで極めて多岐にわたるからだ。医師・看護師・栄養士・薬剤師・歯科医師・歯科衛生士など、さらにはソーシャルワーカーまでが1人の患者さんとかかわり、それぞれの専門技術を生かして互いに連携していかないと理想の医療には到達しない時代になっている。
たとえば、エレンタールは、医師が処方するだけでは、患者さんの口に入るかどうか不安な面がある。味に独特のクセがあるためなじめない患者さんもいるからだ。そこで重要な役割を担うのが、看護師をはじめとする、医師以外の医療スタッフである。彼らがどこまでエレンタールの重要性を認識しているかで、患者さんへのアプローチの仕方が変わってくる。このように医師だけでなく、チームとして医療スタッフ全員が患者さんをサポートしていくことを心掛けていけるかが、今後の支持療法確立において1番の課題といえるのかもしれない。
同じカテゴリーの最新記事
- 化学療法治療前からの口腔管理で 口腔内の合併症を防ぐ
- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策
- 副作用はこうして乗り切ろう!「抗がん薬治療中の口内炎」
- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート
- 抗がん薬・放射線治療による口腔粘膜炎 事前準備で症状は緩和できる
- 口腔粘膜炎:重視され始めた口腔ケアによる合併症の予防効果とは 歯磨き、うがい、歯科受診で口腔粘膜炎を予防しよう
- 抗がん薬の副作用で起こる口内炎を短期間で治す漢方薬「半夏瀉心湯」
- 化学療法の副作用対策の重要性を、患者さん自らしっかりと理解することが大切 注目!粘膜炎(下痢・口内炎)の改善が期待される成分栄養剤
- 患者さん自身でできるセルフケアもある 口の中をキレイにして味覚障害を改善しよう!


