抗がん剤治療の新しい支持療法として期待され、臨床試験開始 見直され始めた成分栄養剤の口内炎軽減効果 | ページ 3
口内炎の重症化を防げれば、治療継続への貢献度は大
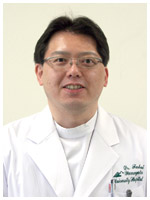
臨床腫瘍学講座助教の
福井忠久さん
山形大学医学部臨床腫瘍学講座助教の福井忠久さんが、副作用対策としてエレンタールに含まれるグルタミンに注目したのは2010年の4月だった。対象は食道がんの患者さん6人だ。食道がんでは、5-FUが5日間とシスプラチン、ネダプラチンといった白金製剤1日が組み合わされて治療が行われるが、副作用の口内炎がよく起こる。
「唇や口腔内が赤くなって熱い食べ物がしみるといった程度の軽症の段階では、患者さんは医師に申告してこないことはよくあります。問題なのは、そういった軽症口内炎を放置していると重症化することがあることです。口内炎は5-FUを投与し始めて7~10日前後に起こり、その時期は好中球減少の時期とも重なります。ほんとの重症の口内炎になってしまうと、細菌感染を併発して最悪の場合敗血症などの重篤な事態に陥ります。水も飲み込めないような痛みも出ますし、当然、食事は摂れない。点滴をしながら回復するまでに2~3週間はかかり、治療を1カ月あまり延期しなければならなくなってしまうんです。栄養状態が悪くなり、治療が中断されると、治療成績も落ち生存率も落ちます。ですから口内炎も初期段階のグレード1で抑えられれば、治療を継続していく上でかなり大きなポイントになるのです」
今後はエレンタールの予防的効果に注目したい
併用療法を行ったところ、ある時期に1コース目で6人の患者さんがグレード1の口内炎を発症した。そこで2コース目に入る1週間前から、エレンタールを1日1パック、2週間服用を続けたという。
「いろいろな文献や資料を調べた結果、グルタミン自体に組織内の活性酸素の影響を抑えたり、抗炎症効果や組織修復作用があるという論文が結構出てくるんです。
口内炎の発症には、グレード1からグレード4へ��進行する段階的なメカニズムがあることが分かっています。抗がん剤や放射線による活性酸素の影響によって粘膜障害が引き起こされますが、グルタミンは口内炎の発症を抑える作用や、重症化した口内炎の治癒を促進させる可能性が期待できます。実際に6人の患者の皆さん全員の口内炎も、グレード1からグレード0になっていますので、やっぱりエレンタールの口内炎軽減作用は期待できるんではないでしょうか。ある患者さんなどは、2サイクルやって2サイクルとも口内炎が出なかった。すると2回目の治療を始める時には患者さんのほうから『あの薬くれ!』って言って申し出てきたほどです(笑)」
ただし、これだけの症例では、まだきちんとしたことは言えない。やはりちゃんとした比較試験が必要である。
「ただ、食欲が低下してくると、患者さんの好みによって好きなものしか食べられなくなります。そうすると栄養のバランスが崩れる。その意味ではエレンタールでいろんな栄養が補給できるというのは良いと思います。今の段階でも、このことは言えますね」
今後は客観的に認められるデータとして、エレンタールを投与した場合と投与しない場合の比較試験を行いながら、エレンタールの副作用予防効果についても観察していきたいと福井さんは締めくくった。
「スープに入れて飲んでみたい!」ホットエレンタール

消化器内科の
中山昇典さん
どんなに時間のない時でも、患者さんの声に耳を傾ける。この気持ちを大事にしているという神奈川県立がんセンター消化器内科医師の中山昇典さんはある日、外来でビックリするような質問を受けた。
「先生、これスープに入れて飲んじゃダメですか?」
これとはエレンタールのことだ。エレンタールと言えば、独特の味を和らげるために、今までなら冷やしてジュースで、あるいは凍らせてシャーベットでと、温度を下げることで、クセのある風味を抑える飲み方をするのが一般的だった。だが高齢で消化吸収力も衰えた患者さんには、温かいスープに入れたほうが飲みやすいというのだ。
「今までいかに飲んでもらうかを一生懸命考えていたんですけど、これは言われるまで気づかなかった。ホント、患者さんに教えられましたよ」
もちろん、エレンタールに含まれたアミノ酸やビタミンは熱湯で溶かすと分解してしまう。しかしぬるま湯程度で溶かすのなら問題ない。また温度を上げると臭いがきつくなりそうに感じるが、スープなど味の付いたものに入れてしまえば、気にならないのだ。
「冬場は特に温かいほうが飲みやすいだろうし、ホットは良いアイデアだと思います。もちろん、冷やして飲むにしてもソーダ割りにするとか、まだまだ考えればいろいろ飲み方はありそうですね」
確かにエレンタールは、他の栄養剤と違って甘味をつけていない分、逆にそれがさまざまなモノと合わせやすいメリットとなっている。
体力がない人よりある人のほうが成績良くて当たり前
中山さんがこれほど患者さんにエレンタールを飲ませたくなる理由は、図7の口内炎軽減効果があるからに他ならない。抗がん剤治療をおこなっている患者さん7名で調べてみると、治療開始時の口内炎の度合いはグレード2~3と高かった。しかし、治療2コース目からエレンタールを投与すると、2週間でグレード3はグレード1へ、グレード2はグレード0へと低下。ものの見事な改善を見せたのだ。また口内炎と同じように、粘膜の損傷から起こる下痢症状に対してもエレンタールの効果は期待できるとして、今後データをとっていきたいという。
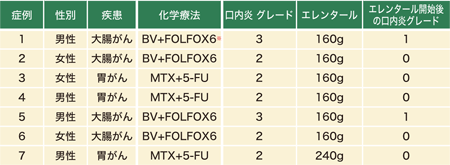
「とかく抗がん剤の効果ばかりに目がいきがちで、患者さんの全身状態に注意がいかないことも少なくありません。それを考えれば、僕たち医師こそ、もっと支持療法の大切さを認識しなければいけないと思います。状態の良い人を治療すれば治療成果が上がるのは当然のことですから」
患者さんの栄養管理・体力向上のための治療は、いわば抗がん剤治療のための土台作りといえる。この重要な治療を「支持療法」などといった傍流の治療のような呼び方をすること自体に、中山さんは、違和感があるようだ。
「ゆくゆくは支持療法なんていう言葉がなくなって、僕はエレンタールも抗がん剤治療時に、当然使われるべき薬剤の柱の1つになり得るとさえ思っているんです」
同じカテゴリーの最新記事
- 化学療法治療前からの口腔管理で 口腔内の合併症を防ぐ
- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策
- 副作用はこうして乗り切ろう!「抗がん薬治療中の口内炎」
- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート
- 抗がん薬・放射線治療による口腔粘膜炎 事前準備で症状は緩和できる
- 口腔粘膜炎:重視され始めた口腔ケアによる合併症の予防効果とは 歯磨き、うがい、歯科受診で口腔粘膜炎を予防しよう
- 抗がん薬の副作用で起こる口内炎を短期間で治す漢方薬「半夏瀉心湯」
- 化学療法の副作用対策の重要性を、患者さん自らしっかりと理解することが大切 注目!粘膜炎(下痢・口内炎)の改善が期待される成分栄養剤
- 患者さん自身でできるセルフケアもある 口の中をキレイにして味覚障害を改善しよう!


