抗がん剤、放射線治療の副作用 つらい「口内炎」にも、予防法・治療法の選択肢がまだまだある!
口内炎の治療法は?
粘膜保護剤、ステロイド軟膏、抗生物質などを症状に合わせて使う
- どこにできているか
- 紅斑、白斑や潰瘍があるか
- 痛みがあるか、ないか
- 食事ができるか
- 熱があるか
「口内炎ができてしまったら、毎日口の中を見て症状を確認し、痛みがあるか、食事ができるかなど、症状を的確に医師に伝えることが大切です(右表参照)。引き続き口の中を清潔に保ち、粘膜保護剤や消炎・鎮痛薬で悪化を防ぎ、症状を改善させながら粘膜が再生するのを待ちましょう」 歯ブラシが口の中の粘膜を傷つけそうなときは、ソフトなものに替えます。
●粘膜保護剤で、悪化を防ぐ
口内炎対策の柱は、いくつか出ている粘膜保護剤をうまく使って悪化を防ぐことです。市販薬も出ているので、自分に合う方法を見つけてください。
(1)ハチアズレでうがい……ハチアズレ(一般名アズレン)という粘膜収れん、修復効果のある粉薬を水にとかして、2、3時間から数時間おきにうがいをすると、粘膜を保護して治癒を早める効果があります。
なお、予防で使っていたイソジンガーグルでうがいをするなら、口の中を刺激しないように、通常よりさらに薄めて使いましょう。
(2)マーロックスでうがい……マーロックス(一般名水酸化アルミニウムゲル)は粘膜親和性が高い液状のコーティング剤です。胃の粘膜を保護する胃薬として使われていますが、水に溶かして口の中全体にゆきわたるようにうがいし、そのまま飲み込めば、口腔内粘膜の保護効果もあります。
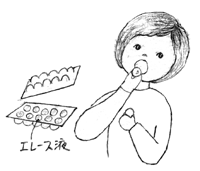
丸形の製氷皿でボール形のアイスを作る
(3)エレース・アイスボールをなめる……エレース(一般名フィブリノリジン・デオキシリボヌクレアーゼパウダー)は患部を清浄化して、粘膜の再生を促す粉薬です。普通は水に溶かして床ずれなどに塗布しますが、水溶液を丸い形に凍らせた「エレース・アイスボール」を口に含んでなめると、痛みや症状を和らげることができます。口当たりがよく、食欲のないときや、水を飲めないときの水分補給にも有効です。
●局所的な炎症にはステロイド軟膏が有効
局所的な軽度の口内炎には、ステロイド入りの軟膏(デキサルチン軟膏やケナログ)を1日1、2回程度、少量塗布する方法もあります。1週間程度でよくなれば問題ありませんが、��まり長期間持続して使うとかえって悪化し、治癒が遅れることがあります。医師と相談の上で使用してください。
●感染症を合併しているときは、抗生物質を
白血球、好中球が減少してくる時期に、感染を合併して炎症が続く場合は、抗菌薬(抗生物質)、抗真菌薬、抗ウイルス薬を適切に使うことが大切です。
「一般に、白血球が下がって発熱していれば、感染を起こしていると考えられます。感染を放置すると、敗血症などに進み、生命の危機につながりますが、適切な薬剤を使うことで危険を回避でき、口内炎も早く治る可能性があります」
●白血球、好中球減少には、G-CSFで対処
骨髄抑制が見られた場合は、好中球を増やすG-CSF製剤を数日間皮下注射します。「使う目安は、好中球数が500以下で、熱、口内炎など感染の兆候があったとき。好中球が500以下の場合に保険が適用されますが、症状がなければ使う必要はありません」
●放射線による口腔内乾燥には、保湿を
放射線照射で唾液腺が傷害され、ドライマウスになったときは、うがいをした後、人工唾液を塗布またはスプレーする、オーラルバランスというゲルタイプの保湿剤を粘膜にはりつけるなどの方法で湿潤を保ちましょう。ケナログなどの薬剤とも併用できます。
●サプリメントの有用性は未知数
「このほか欧米では、ビタミンEやビタミンC、グルタミンなどのサプリメントや、新しい治療法としてレーザー治療、KGF(ケラチノサイトグロースファクター=繊維芽細胞増殖因子)製剤などの有用性が報告されていますが、大規模臨床試験がしにくい分野でもあり、まだ確立された方法ではありません」
●痛みは、鎮痛剤でコントロール
「口の中が痛いときは、適切な鎮痛剤で痛みをコントロールすることが大事ですね」
通常用いられるのは、バファリン、ロキソニン(いずれも錠剤)、ボルタレン(錠剤、座薬)、ポンタールシロップ(水薬)など、NSAIDと呼ばれる非ステロイド系の消炎鎮痛剤です。局所麻酔薬の入ったゼリー(キシロカインビスカス)を薄めて口に含む方法もあります。これらの薬でコントロールが難しい場合は、モルヒネに代表される麻薬系の鎮痛薬を使います。麻薬系の痛み止めにも、飲み薬のほか、貼り薬、座薬、注射薬などいろいろな種類があるので、飲み込めないときでも大丈夫。
「痛みをコントロールしても食べられないときには、入院して点滴で栄養を補給します」
食事にはどんな工夫をすればよい?
ゼリー系食品などを活用し、食べられるものを見つけよう
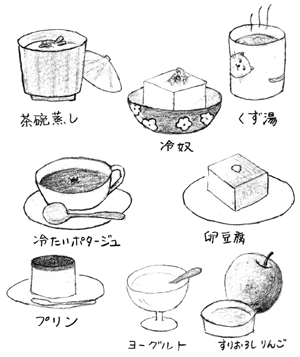
「口内炎にしみる刺激物や固いものは避け、味付けは薄め、温度は人肌程度を基本に、良く煮込んで柔らかくする、きざむ、ミキサーを活用するなど調理法を工夫しましょう。粘膜の再生にはビタミンB2、B6が必要ですから、できれば野菜や魚もとれるといいですね」
痛みが強くて固形物が食べられないときは、上のイラストのような食品を試してみてください。ゼリータイプ、流動タイプの栄養食、経腸栄養剤(エンシュアリキッドやラコール)なども活用してみましょう。痛いところを避けてストローで流し込むのも一案です。
「クッキーをミルクティーに浸したり、パンを牛乳に浸して食べている患者さんもいます。キャンディーやガムも唾液の分泌を促すのに効果的です。 とにかく、トライアンドエラーで食べられるものを探してみてください」
実例
化学放射線治療で、水すら飲めなくなって……
栃木県・板谷正人さん(58歳・仮名)
2年前、食道がんに下咽頭がんを合併し、化学放射線治療を受けました。照射3週間目くらいから口の中全体がのどの奥までただれて潰瘍化し、痛くて水もつばも飲み込めない状態に。最初はうがいや鎮痛薬で対処していましたが、効き目がありません。そこで、モルヒネを処方してもらったら、痛みがかなりおさまり、流動栄養ドリンク(エンシュアリキッド)やヴィダーインゼリーくらいは飲み込めるようになりました。
麻薬は怖いと思っている方がいるかもしれませんが、医師の適切な処方で使えば安心。
治療終了後、1カ月ほどで粘膜が再生し、今ではよくかめば大体なんでも食べられるようになっています。
同じカテゴリーの最新記事
- 化学療法治療前からの口腔管理で 口腔内の合併症を防ぐ
- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策
- 副作用はこうして乗り切ろう!「抗がん薬治療中の口内炎」
- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート
- 抗がん薬・放射線治療による口腔粘膜炎 事前準備で症状は緩和できる
- 口腔粘膜炎:重視され始めた口腔ケアによる合併症の予防効果とは 歯磨き、うがい、歯科受診で口腔粘膜炎を予防しよう
- 抗がん薬の副作用で起こる口内炎を短期間で治す漢方薬「半夏瀉心湯」
- 化学療法の副作用対策の重要性を、患者さん自らしっかりと理解することが大切 注目!粘膜炎(下痢・口内炎)の改善が期待される成分栄養剤
- 患者さん自身でできるセルフケアもある 口の中をキレイにして味覚障害を改善しよう!


