抗がん剤、放射線治療の副作用 「味覚障害」は食事の工夫や亜鉛の補給で乗り切ろう!
味覚障害が起こったらどう対処する?
亜鉛を含む食品、唾液腺を刺激する食品をとり、バランスのよい食生活を
以上のようなメカニズムを考えると、抗がん剤や放射線による味覚障害は、治療を終えるまで「モトから断つ」ことができないため、ある程度は避けられないことです。「そこで、できる限り味蕾に必要な亜鉛などの微量栄養素の損失を防ぎ、外からも補給して味蕾の再生を助けつつ、唾液腺の働きを促して、味の成分を味蕾に取り込みやすくすることが最良の改善策となります」
- 亜鉛の働きを阻害する薬を減らす
- 亜鉛、鉄などを食物や薬剤で補給する
- 唾液腺の働きを活発にする
- 口内に、湿り気を与える
亜鉛の吸収を妨げる降圧剤などは最小限に
亜鉛の吸収を妨げる薬は、抗がん剤だけではありません。よく使われている降圧剤や、高脂血症の治療薬をはじめ多くの薬剤が、亜鉛の働きを阻害します。
「治療中は抗がん剤以外の薬剤を最小限にしてもらうように担当医に依頼して、亜鉛の損失を抑えましょう。また、多量のカルシウム摂取は亜鉛や鉄の吸収を妨げますから、サプリメントで大量にとるのは避けます。食物でとる程度の量なら問題ありません」
さらに、ハムやかまぼこなどの加工食品、清涼飲料水等に使われるポリリン酸やフィチン酸という食品添加物は、舌ざわりをよくする半面、亜鉛の吸収を妨げるので、治療中は控えめにしましょう。
亜鉛を多く含み、唾液腺を刺激する食品をとる
亜鉛が豊富な食品は、カキをはじめ、ゴマやヒジキなどの海藻類、肉類などです(下図参照)。1日の必要量は、成人男性なら10~12ミリグラム、女性なら9~10ミリグラムで、カキなら5、6個食べれば補給できます。
「カキは季節のものですし、肉類のとりすぎは高脂血症などの原因にもなるので、私は黒ゴマを上手にとることをおすすめしています。ゴマはすらずに、毎食小さじ1杯くらいをご飯にかけて食べると、よくかむことで唾液腺の刺激にもなって一石二鳥。亜鉛の補給にはパン食よりご飯のほうが有利ですから、ご飯食を1食でも増やすとよいでしょう。酸味のある食品も唾液の分泌を促すので、亜鉛の豊富な海草と組み合わせた、のどごしのよいもずく酢などもおすすめです」なお、極端な菜食主義を続けると、亜鉛の吸収が妨げられるそうです。

鉄やビタミンB12も必要
味蕾の新陳代謝にもっとも必要なのは亜鉛ですが、鉄やビタミンB12も欠かせません��鉄はほうれんそう、ビタミンB12はシジミやサンマなどに多く含まれています。
「吐き気や口内炎など、つらい症状がある方も多いでしょうが、1日30品目を目安に、いろいろな食品をなるべくバランスよく食べられるように工夫してみてください」
亜鉛入りの薬剤やサプリメントを
食物だけで味覚障害が改善しないときは、亜鉛が含まれる薬剤やサプリメントで補います。
「現在、亜鉛製剤で保険が適用になる薬は、亜鉛入りの胃薬(商品名=プロマック)だけなので、味覚障害にも処方されています。内科で処方してもらってもいいですね。亜鉛単独の製剤やサプリメントは、自費扱いになります。市販のサプリメントを利用するときは、信頼できる日本のメーカーのものを選ぶとよいでしょう」
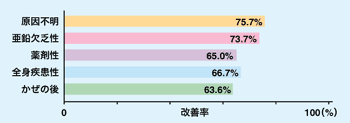
肉類に嫌悪感を覚えるときは
肉類などのタンパク質を食べると金属味がしたり、嫌悪感を覚えたりする人も多いもの。子供のお弁当や夕食用のハンバーグや肉団子は、たねの半量を豆腐で代用したり、肉をワインや果汁に浸して調理しているという患者さんもいます。
痛みがあって、食べにくいときは
口内炎やのどの痛みを伴う場合は、調理法を工夫し、口に合うものを探しましょう。前述の古山さんは、ぞうすいやグラタンなど離乳食風のものや、先の曲がるストローで液体を飲むなどの工夫をしていたそうです。また、放射線治療中に何を食べても奇妙な味に感じられ、痛みもあったため、はちみつをつけたやわらかいパンだけでしのいだ、という患者さんもあります。
「口内炎は痛み止めやうがい薬で改善できても、食べ物がアロエをかんだように苦く、のども腫れて食べられない、という患者さんもいます。このような方の苦痛を即効で止めることはなかなか難しいのですが、味覚障害の改善にはバランスよく栄養をとることが大切ですから、ご家族の愛情と根気強いサポートがなによりの薬になると思います」
のどが痛くて飲み込みにくいときは、ミキサーにかけた具沢山のスープや冷たいじゃがいものスープ、ホワイトシチュー、ゆるめのマッシュポテト、バナナジュース、市販のゼリータイプの栄養食など、のどごしがよく刺激の少ないメニューを試してみてください。
うがいや保湿剤で、口内を潤す
唾液が減少しているときは、なるべく食べ物をよくかんで唾液腺の働きを促します。人工唾液や保湿スプレーなどで口の中を潤したり、こまめにうがいをするのも効果的。「最近では、唾液腺や粘膜の修復剤を配合したうがい薬も出ているので、医療機関で処方してもらうといいでしょう」
味覚障害の専門外来もある
抗がん剤や放射線治療が終了後、味覚障害がいつまでも続くようなら耳鼻咽喉科へ。
味覚障害の専門外来を設けている医療機関(日本大学医学部付属板橋病院 電話03―3972―8111〈代表〉など)もあります。
生井さんより一言

味覚テストで、味覚障害の程度がわかる!
「テーストディスク」という簡単なテストで、味覚の感度を判定することができます。甘味、塩味、酸味、苦味の4つの味がそれぞれ5段階の濃度に作られている溶液を、小さなろ紙にたらして舌の上にのせ、どの味かあててもらう、という方法です。たとえば、甘味液の1~2で「甘い」と感じれば感度良好、3で感じれば正常です。2、3週間以上味覚障害が続くときは、この方法で障害の程度を判定すると、対策をたてやすくなります。食物のおいしさは舌全体や5感で総合的に味わうものですから、4つの味覚とも感度がよいからといってグルメとはかぎりません。
同じカテゴリーの最新記事
- 化学療法治療前からの口腔管理で 口腔内の合併症を防ぐ
- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策
- 副作用はこうして乗り切ろう!「抗がん薬治療中の口内炎」
- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート
- 抗がん薬・放射線治療による口腔粘膜炎 事前準備で症状は緩和できる
- 口腔粘膜炎:重視され始めた口腔ケアによる合併症の予防効果とは 歯磨き、うがい、歯科受診で口腔粘膜炎を予防しよう
- 抗がん薬の副作用で起こる口内炎を短期間で治す漢方薬「半夏瀉心湯」
- 化学療法の副作用対策の重要性を、患者さん自らしっかりと理解することが大切 注目!粘膜炎(下痢・口内炎)の改善が期待される成分栄養剤
- 患者さん自身でできるセルフケアもある 口の中をキレイにして味覚障害を改善しよう!


