化学療法の副作用対策の重要性を、患者さん自らしっかりと理解することが大切 注目!粘膜炎(下痢・口内炎)の改善が期待される成分栄養剤 | ページ 3
患者さんの副作用の状況を、経過看護記録票で医療スタッフがチェック
監修:磯貝 佐知子 新潟県立がんセンター新潟病院看護部・がん化学療法看護認定看護師
取材:「がんサポート」編集部
外来化学療法の患者さんは経過看護記録票で副作用を評価

付ける潤滑油のような役割と話す
磯貝佐知子さん
外来で化学療法を受ける患者さんが増えている。新潟県立がんセンター新潟病院も例外ではない。現在、月に約600件。看護師の磯貝佐知子さんによると、患者数が多く、また外来診療という限られた時間の中でも、患者さんの情報を医療スタッが共有することが重要だという。
「入院では医療スタッフが患者さんの状態をタイムリーに把握できますので、状態の変化に適宜対応ができますが、外来ではそうはいきません。患者さんが外来で診察・治療をうける時間の中で、看護師は患者さん1人ひとりの日常生活情報を収集し、マネジメントすることが必要になります」
外来化学療法では自宅での生活が主体になる。しかし化学療法の副作用により、日常生活に影響を及ぼすこともある。
「そうした患者さんの情報を、医師、看護師、薬剤師などの医療スタッフが、限られた時間内で共有することが重要です。職種それぞれの専門的視点からの意見を集約することで、患者さんのQOLの維持や向上につながる医療を提供できるからです。それがチーム医療だと考えます」
他職種間との情報共有のために、新潟県立がんセンターの外来化学療法室では、図5のような記録用紙を使い、診察前の採血結果を待つ間に看護師が、副作用チェックなどの問診や自己管理の指導を行っている。
グレードで表せない症状は「特記事項」に詳しく書く
| グレード | 口内炎 |
|---|---|
| 0 (0期) | 正常 |
| 1 (1期) | 症状がない、または軽度の症状がある :治療を要さない |
| 2 (2期) | 中程度の疼痛 :経口摂取に支障がない、食事の変更を要する |
| 3 (3期) | 高度の疼痛 :経口摂取に支障がある |
| 4 (4期) | 生命を脅かす :緊急処理を要する |
同病院で使われている外来化学療法のレジメン(抗がん剤の投与方法)は220種類以上あるが、それぞれに経過看護記録票が作られている。これに副作用を0~4のグレード(*)で記入し、数値化できない内容は特記事項の欄に記入する(図3)。
「グレードだけでなく、特記事項に記入することで、実態をより正確に伝えることができます。たとえば口内炎の場合、痛くて食べられなければグレード3ですが、痛みを我慢して食べると、摂食可能ということでグレード2になります。そういう場合は、評価の数字だけではなく、特記事項に詳細を記入することで、患者さんの状態を、より正確に伝えられると思っています」
患者さんの状況を正確に把握できれば、適切な支持療法につながる。この経過看護記録票の果たしている役割は大きい。
*グレード=副作用の度合い
消化器症状を悪化させない支持療法
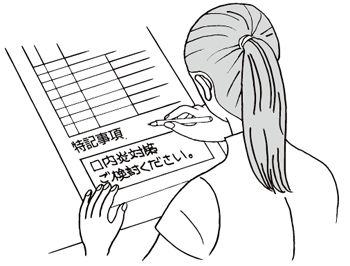
[図5 新潟県立がんセンターの経過看護記録票]
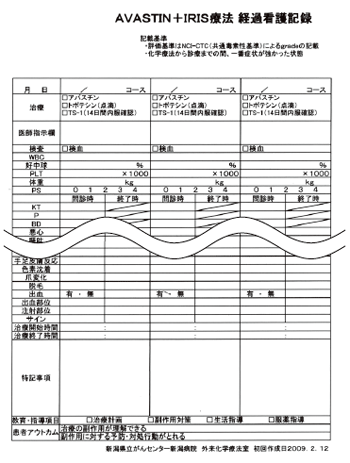
今回は支持療法の中でも、とくに栄養に関するケアについて聞いた。
まず、看護師が患者さんの副作用の状態などをチェックすると、医師もその情報をもとに診察し、必要な指示を出している。そこで最近、消化器症状に対して成分栄養剤が使われることが増えている。
「アミノ酸を組成とする成分栄養剤は、食事の摂取量が低下した患者さんに使うのが基本です。しかし最近、アミノ酸含有製剤が消化器系の障害を修復する作用があるという研究結果があったことから、粘膜炎(下痢・口内炎)などの消化器症状に対し、消化器系の副作用対策として使うケースがあります。例えば口内炎がつらい患者さんには、問診時に口腔ケアや食事の指導を行いますが、ほかにも薬剤師に相談をしたり、経過看護記録票の特記事項欄に『口内の痛みで経口摂取にとても苦痛を伴っています。口内炎対策をご検討ください』などと記入し、医師に口内炎治療の指示を仰いでいます」(図4・5))
成分栄養剤はあくまでまだ栄養剤という位置づけだ。したがって、粘膜を修復する効果があり、さらに栄養素の吸収性にも優れている成分栄養剤を処方しやすくするには、「粘膜障害による消化吸収不良」などと記入するのが良いようだ。
「看護師は医師の処方に対し、患者さんには使用根拠と方法をなるべく詳しく説明して処方通りの服薬を守ってもらうように心がけています。また患者さんだけでなくご家族にも説明することがありますし、薬剤師から説明してもらうこともあります」
支持療法は継続することで効果を発揮する
ただ、「役立つ」とわかっても、患者さんが成分栄養剤を簡単に飲めるとは限らない。吐き気があったり、味覚障害が起きていたりして、飲めないと訴える患者さんも少なくない。
「どうすれば飲めるかは人によってさまざまです。シャーベットやゼリーにしたり、料理に加えても問題ないという話をすると、試してみる患者さんもいます。このように患者さんの生活の状況に合わせていろいろな服用方法を提案しています。短い期間なら飲めるという患者さんもいました。その方は、ずっと飲み続けるのは嫌だけれど、1週間ならいいというので、症状のひどくなりそうな時期に1週間ずつ飲んでもらうようにしたのです」
成分栄養剤を飲む期間は、目的によって変えてもいいようだ。口内炎対策なら、症状の出そうな3~5日間飲むことである程度の効果は期待できそうだが、下痢対策ではもう少し長い期間が必要になる。また、血液がんの治療で強力な化学療法が行われるときには、ずっと飲み続けているのが理想的らしい。つまり成分栄養剤の特性を生かした服用方法が選択できるのだ。
「支持療法は、患者さんの状態維持と副作用症状による苦痛の軽減、また化学療法を継続するためにも並行して行うべき大切な治療です。外来では患者さんが自宅での生活の質を保ちながら化学治療を継続するためには、医療スタッフがタイムリーに情報を共有し、適切な支持療法を行うことが鍵だと考えます」
栄養面のケアをはじめとした支持療法のさらなる徹底が、患者さんの生活の質を守ることになり、がん治療の効果を高めることにもつながるのだ。
(構成/柄川昭彦)
同じカテゴリーの最新記事
- 化学療法治療前からの口腔管理で 口腔内の合併症を防ぐ
- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策
- 副作用はこうして乗り切ろう!「抗がん薬治療中の口内炎」
- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート
- 抗がん薬・放射線治療による口腔粘膜炎 事前準備で症状は緩和できる
- 口腔粘膜炎:重視され始めた口腔ケアによる合併症の予防効果とは 歯磨き、うがい、歯科受診で口腔粘膜炎を予防しよう
- 抗がん薬の副作用で起こる口内炎を短期間で治す漢方薬「半夏瀉心湯」
- 化学療法の副作用対策の重要性を、患者さん自らしっかりと理解することが大切 注目!粘膜炎(下痢・口内炎)の改善が期待される成分栄養剤
- 患者さん自身でできるセルフケアもある 口の中をキレイにして味覚障害を改善しよう!


