- ホーム >
- 副作用対策 >
- 下痢・排便/排尿障害
婦人科がん手術後の排便トラブル・便秘 上手にコントロールして気持ちのよい生活を
対策その1/日常生活の注意は?
水分、繊維質の多い食品を十分にとり、トイレ習慣をつける

自分でも便秘解消の工夫をしてみたい、という方は、まず、食べ物や排便習慣など、日常生活を見直します。
「水分や繊維質を多くとるなど、一般に便秘によいと言われていることは試してみるとよいでしょう」と神山さん。
(1) たっぷり水分補給を
水分の摂取量が少ないと便が硬くなるので、1日1~1.5リットルを目安にお茶、麦茶、ジュースなどを補給します。かき氷、シャーベット、果物などで代用するのもいいでしょう。
(2) 繊維質を十分に
便は、大腸にとどまる時間が長くなるほど水分が吸収されて硬く小さくなり、排便しにくくなります。繊維質を多く含む野菜や海草などをとると、便のかさが増して水分が含まれやすくなり、便を軟らかく保てます。寒天は腸の中の水分を吸収する働きがあるので、寒天ゼリーなどもお勧め。なお、糸こんにゃくやキンピラゴボウなどをよくかまずに飲み込むと、消化されないまま小腸の中でつかえて腸閉塞の原因になる可能性があります。繊維を断ち切るように小さめに切るか、よくかんで食べましょう。
(3) 乳酸菌で腸内を健康に
乳酸菌は腸の善玉菌を増やして腸内を健康に保つので、ヨーグルトや乳酸飲料を。アロエ入りヨーグルトも便秘に有効です。
(4) ウォッシュレットを活用
「便が肛門の近くまで来ている場合は、肛門をウォッシュレットで刺激してみましょう。赤ちゃんの排便を促すときの“こより浣腸”と同様に、排便を促す効果があります」(神山さん)。温水シャワーやビニール手袋をした指で刺激しても効果的。
(5) 朝食後、トイレに座る習慣を
朝食をとると、便意を生じやすいもの。食後はトイレに座る習慣をつけ、(4)の方法で排便を促してみます。朝食時や食後に、コーヒーを飲むと便意が起こる、という人もいます。
(6) 排便時に、肛門周囲を指で押さえる
肛門の手前まで便が来ているのに排便できないときは、肛門の周囲を指で押さえていきむのも一案です。
(7) 毎日、骨盤底筋体操を実行
骨盤の筋肉を強化するには、「骨盤底筋体操」がお勧め。「5秒に1回肛門を締める運動を5分間続け、これを1セットとして1日4回行うといいですね」
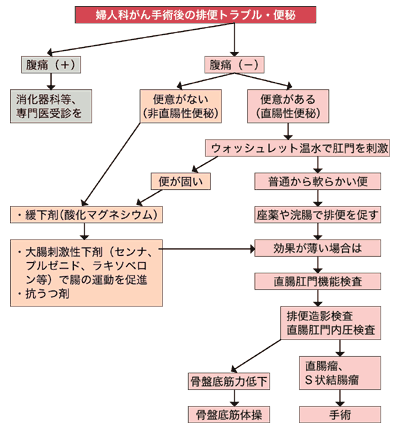
対策その2/下剤の効果的な使い方は?
緩下剤からスタート。直腸性便秘には肛門刺激や座薬で対処
生活の工夫だけでは便秘が改善できないときは、専門医に下剤を処方してもらいます。
下剤には、大腸内の水分を浸透圧で吸収して便を軟らかくする「緩下剤」(酸化マグネシウム=通称カマ)と、大腸の運動を促進させる「大腸刺激性の下剤」(センナ、プルゼニド、アローゼン、ラキソベロンなど)の2つのタイプがあります。これらはいずれも大腸全体に作用する飲み薬で、服用後10時間程度で効果が現れます。一方、肛門から注入する浣腸や座薬は、直腸またはその周辺だけを刺激して排便を促すもので、即効性があるのが特徴です。
「緩下剤は作用が穏やかですが、大腸刺激性の下剤は作用が強く、常習性になりやすい傾向があります。最初は緩下剤を使いましょう。緩下剤は粉薬で、標準使用量は1日1.5グラムです」
便の様子をみながら1日3回に分けて、0.3グラム入りまたは0.5グラム入りの袋を1袋ずつ使うこともできます。
「直腸性の便秘なのに、大腸刺激性の下剤を使っている人が多いのですが、これは、1本のピンを倒すために大地震を起こしているようなもの。使用不可というわけではありませんが、量の割に効果が上がらなかったり、腹痛を起こしたりします。また市販の便秘薬だから作用が弱いということはなく、むしろ病院で処方されるものに比べて刺激が強いものもあるので注意が必要です」
直腸性の便秘の場合は、まず、ウォッシュレットで肛門を刺激することから始め、それでもダメなら緩下剤や座薬(テレミンソフト、新レシカルボンなど)を処方してもらって排便を促します。頑固な場合は奥の手として浣腸を。直腸に便があるときにタイミングよく注入するのがコツです。
| 種類 | 薬剤名(商品名) | 作用 | 標準使用量(1日) |
|---|---|---|---|
| 浸透圧性下剤 | 酸化マグネシウム | 腸液の吸収を抑え、 便を軟化させる | 1.5グラム |
| 大腸刺激性下剤 | センナ(漢方成分・粉薬) プルゼニド(同上・錠剤) アローゼン(同上・粉薬) ラキソベロン(滴下液) | 大腸全体を刺激して 蠕動を促進させる | 1~2袋 1~2錠 1~2袋 10滴 |
| 座薬 | テレミンソフト 新レシカルボン | 直腸を刺激して排便を促す | 1個 1個 |
| 浣腸薬 | いちじく浣腸(グリセリン) | 直腸を刺激して排便を促す | 1個 |
Q&A
Q 下剤を飲めば、腸閉塞の予防になるってホント?
A 婦人科がんや消化器がんなどの手術後は、癒着による腸閉塞が起こりやすくなります。医師から「腸閉塞の予防のために下剤を飲みなさい」と言われ、下痢をしても下剤をやめられない患者さんが多いのですが、下剤を飲んでいれば腸閉塞にならない、というエビデンス(根拠)はありません。腸の癒着はおもに小腸で起こり、下剤は大腸に作用するものですから、便秘を防げば腸がつまらないという考えはナンセンス。腸閉塞が心配なら、食べ過ぎや早食いに気をつけ、よくかんで食べることが大切です。
対策その3/手術後、急に便秘がひどくなったとき、
下剤の量が増えて困るときは専門医に相談を
「個々の患者さんの便秘の原因がどこにあるのか、どんな対策をとればよいかは、患者さんにじっくり話を聞きながら、時間をかけて見つけるしかありません。手術後、急にひどい便秘になったとか、セルフケアでは改善できないとき、下剤の量が常用量をかなりオーバーしているときには、1度専門外来で診察を受けることをお勧めします」
緩下剤なら2~3グラム以上、大腸刺激性の下剤なら3~4錠(袋)以上、滴下剤なら20滴以上使わないと排便が難しい、という場合は、思い切って専門医に相談を。現在、排便障害の専門外来も各県に1科程度に増えているそうです。
「消化器科に排便障害に詳しい大腸・肛門の専門医がいるかどうか訊ねて、受診するとよいでしょう」 なお、神山さんの外来日に直接診察を受けることも可能です(下表参照)。
神山医師の診察日
昭和大学病院消化器外科外来
第1・3・5火曜日午前中 ※初診以外は予約が必要
〒142-8666 品川区旗の台1-5-8
TEL 03-3784-8557(一般消化器外科外来) FAX 03-3784-5835
松井病院消化器外科外来
毎週月・水・木・金午前中…予約不要
〒146-0082 東京都大田区池上 2-7-10
TEL 03-3752-1111 (受付・案内窓口) FAX 03-3752-1119
メール
排泄を考える会「排便障害手紙相談」
困っている人の年齢、性別、相談者との続柄、住所、さしつかえなければ電話番号、悩みの種類(排便、排尿、両方)と具体的内容を書いて、手紙で下記に郵送すると、質問内容にもっともふさわしい専門家に照会してから回答してくれる。ある程度時間がかかるが、3週間以上回答がない場合は、再度問い合わせを。
〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1
東大病院泌尿器科内 排泄を考える会事務局


