- ホーム >
- 副作用対策 >
- 下痢・排便/排尿障害
9割の人が日常生活に支障のないレベルまで回復 悩まないで!! 前立腺がん術後の尿失禁に「人工尿道括約筋手術」
人工括約筋手術後進国の日本
こうした手術が、米国では年間4400件あまり行われています。前立腺全摘術100件に3例の割合です。この数の多さは、「米国の全摘手術が日本に劣るからではなく、保険で中等度以上の尿失禁治療がカバーされているから」だといいます。オーストリアでも前立腺全摘術の1.6パーセント、韓国でも3年前に保険で認可され、全摘術は日本の3分の1ほどなのに、人工尿道括約筋手術は2009年の1年間だけで100件ほど行われています。
これに対して、日本では手術自体、まだ保険で認められておらず、実施件数は平均年間7例。「先進諸国の中で、1番遅れているのが、日本なのです」と荒井さんは嘆息しています。
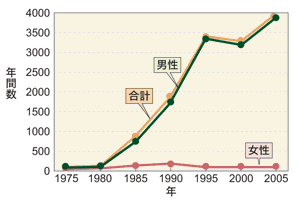
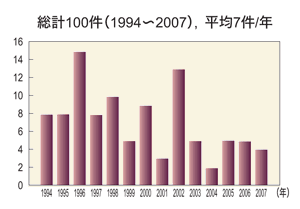
人に会えるのがうれしい
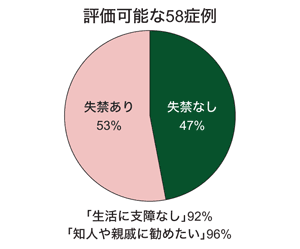
荒井さんたちが、人工尿道括約筋手術を始めたのは1991年です。
「当時は、5~6年に1例行う程度で、需要もあまりありませんでした。私の患者にも必要な人はいませんでした」と荒井さん。日本では、旧型の人工尿道括約筋は1990年に医療機器として承認され、93年には先進医療の認定も受けていました。
とはいえ、あくまでも先進医療であり、手術そのものは保険で認められていないため、患者さんには金銭的に大きな負担がかかります。
一方、手術を望む患者さんの数も、ここ数年増えてきたそうで、「他施設から紹介されてくる患者さんが増えたのです」と荒井さん。
そこで、荒井さんは人工尿道括約筋手術の保険認可を進めるために、2007年に推進委員会を立ち上げ、尿失禁の実態調査と人工尿道括約筋手��の治療成績を調べました。
これによると、パッドが1日3枚以上必要など、人工尿道括約筋手術の対象となるような重症尿失禁の患者は全国1202施設で推定2235人。原因として圧倒的に多いのは、前立腺全摘術でした。
人工尿道括約筋の手術件数は、年間平均7例。調査に協力してくれた24施設の患者64例のうち、半分以上(34例)が前立腺全摘を受けた患者さんです。
実際には、58例で評価を行いました。
これによると、「生活に支障がない」程度まで回復した人が92パーセントと、かなり高い治療成績でした。完全に失禁がない人は47パーセントでした。
とはいえ、なかにはくしゃみで漏れる人もいるそうです。
「普通は、クシャミが出る前に神経反射が起きて、自然に圧を高めて尿が漏れるのを防いでいるのですが、人工尿道括約筋ではそこまでは間に合わないのです」と荒井さん。結果として、アクティブに動く人は少し漏れることがあるといいます。
それでも、96パーセントの人が、知人や親戚に勧めたいと答えたそうです。患者さんの満足感は高いのです。
「会合にも出られるようになったし、人に会えるのがうれしい、家庭菜園で1日中仕事ができるようになった」などの感想が語られています。
バーゲンになると、おむつを山のように買ってくるのが恥ずかしかったという人もいます。
荒井さんが、患者さんたちの気苦労を強く感じたというのが、術前術後の排尿量の違いです。手術前は、1日1440ミリリットルだった排尿量が、人工尿道括約筋術を受けてからは、2375ミリリットルと1リットルも増えているのです。
「みんな患者さんは、尿失禁を気にして水分摂取を制限しているのですよ」
パッドを1日に8回も換えるほどの尿失禁が、たった1枚用心のために使うだけですむようになったのです。自由に水分をとり、失禁を気にしないで外出できる毎日。その解放感はどれほど大きいか、はかりしれないものがあります。
傷口から感染症の可能性も
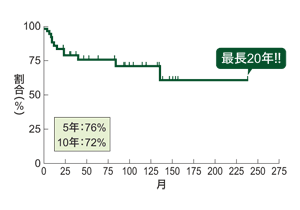
しかし、まだ日本では課題も残されています。
1つは、人工尿道括約筋自体の問題です。すでに改良型が認可され、2009年9月からは新しい人工尿道括約筋が使われていますが、調査の時点では人工尿道括約筋の初期不良が4例ありました。うまく装置が作動しないことがあったのです。
「問題が出るのは、最初の1~2年。ここをクリアできれば、5年でも10年でも使えます」と荒井さん。手術から10年たっても72パーセントは正常に稼働し、長い人は20年も使っています。
ただし、注意しなければならないのは感染症です。傷口から感染を起こす率が4.5パーセントから15パーセントという報告もあり、そのため実態調査でも、人工尿道括約筋を摘出しなければならない例が9例あったのです。
人工尿道括約筋は身体にとっては異物であるため、一旦感染が起こると摘出せざるを得ない例が多いのです。この場合、感染がおさまるのを待って、再手術を行うことも可能だそうです。
しかし、米国では感染の発生率は慣れた医師ならば1パーセント以下です。日本の場合、まだ熟練した医師が少なく、そのために手術時間が長くかかるというのも、感染を増やす原因になっているのです。
手術時間が2時間半以上かかっているか、それ以下で終わっているかで比較すると、2時間半以下のほうが、明らかに成績がいいそうです。ちなみに、荒井さんたち東北大学のグループの手術時間は1時間前後だといいます。中核病院などで集中して手術を行えば、技術も早く向上するのです。
普及を妨げている大きな問題
もう1つ、普及を妨げている大きな問題が、費用の問題です。人工尿道括約筋の手術は保険で認められていないため、自費で負担しなければならないのです。これが、170万円ほど。人工尿道括約筋の手術が、先進医療として認められている病院ならば、検査や入院費などは保険でまかなえるので、これを加えて200万円ということですが、それでもかなり高額な治療になります。
患者さんのなかには、高額な医療費を払っても、尿失禁が良くなってうれしいという人はいます。しかし、誰でもこの手術を受けられるようにするためには、ぜひとも保険で認可してもらう必要があるのです。
「人工尿道括約筋の手術を受けなければ、死ぬまで失禁が続くのです。その間に薬を使ったりコラーゲン注入をしたり、尿道をつりあげる手術をしたり……オムツだって年間数10万円かかるのです。かぶれて皮膚科に行けばまた医療費がかかります。それだけでも400~500万円になってしまうのです」と荒井さんは言っています。
人工尿道括約筋を使わなければ、尿失禁が治らない上、医療費やオムツ代がそれ以上にかかるのです。
今後は、医師の教育プログラムを作り、一般の人にも手術について知ってもらい、人工尿道括約筋のアフターケアシステムや何かあったときに対応できるネットワークを構築したいと荒井さんは語っています。
日本でも、早く保険で人工尿道括約筋の手術が受けられるようになってほしいものです。


