- ホーム >
- 副作用対策 >
- 下痢・排便/排尿障害
子宮がん手術後に多くの患者さんが直面する排尿障害 自己導尿の早期訓練で、排尿トラブルによる心身の苦痛も軽減する
退院前に自己導尿のマスターを……
手術後しばらくは自力で排尿することが難しいことが多く、膀胱内に尿が残りやすくなります。膀胱に尿を貯めきれず、あふれ出して失禁となることもあります(溢流性尿失禁)。残尿があると、膀胱内の古い尿に細菌が繁殖して膀胱炎や腎盂炎といった疾患にもつながりますから、適切な対応が必要です。
「以前は、入院中から膀胱体操(排尿訓練)や、お産の後に行う骨盤底筋体操を奨励していた病院が多かったのですが、排尿障害の主な原因は神経にあるわけですから、最近は筋肉だけを鍛えてもあまり意味がないと考えられています(注・骨盤底筋体操は、加齢や出産後の筋力低下による尿失禁には効果的)。現代では、膀胱内にカテーテルを入れて排尿する『間欠的自己導尿』をマスターして、残尿を徐々に減らしていくことがケアの主流になっています」
同大学病院産婦人科では、広汎子宮全摘術を行う場合、手術当日の麻酔後、膀胱内にバルーンカテーテルを留置し、手術後1週間は、自動的に排出された尿をバッグに貯めて尿量などを観察します。手術後6日目に、カテーテルを一時的にクリップではさんで(クランプ)膀胱に尿をため、尿意の有無を確認し、翌日カテーテルを抜きます。手術後1週間から退院(術後4週目頃)までは、尿意がない場合でも、4時間ごとにトイレに行き、自分で排尿した後、ナースのサポートでカテーテルを挿入して残尿を計量カップに出し、その量を測定します。残尿が100ミリリットル以上あれば、導尿回数を4~6回にします。
「人間の膀胱の容量は350~450ミリリットルほどで、大体150~200ミリリットル貯まるとトイレに行きたくなるのが普通です。100ミリリットルの残尿は相当残っているということで、そのまま放置してはいけません。手術後1週間以上自己排尿できない場合や、2週間で改善のない場合、残尿が100CC以上の場合は、入院中から看護師さんに指導を受け、間欠的自己導尿(CIC=コラム参照)」を積極的に導入するとよいでしょう。この場合、泌尿器科との密な連携が必要で、半年から1年を目安に自然排尿に切り換えていきます」
カテーテルの留置や自己導尿によって排尿障害の回復が遅れることはなく、むしろ改善に働くそうです。
「残尿が50ミリリットルを切ったら改善の目安と考えられますが、揺り戻しがくることもありますし、50ミリリットルの残尿でも1日1回程度の自己導尿が必要とする��見もあります。主治医とよく相談してください」
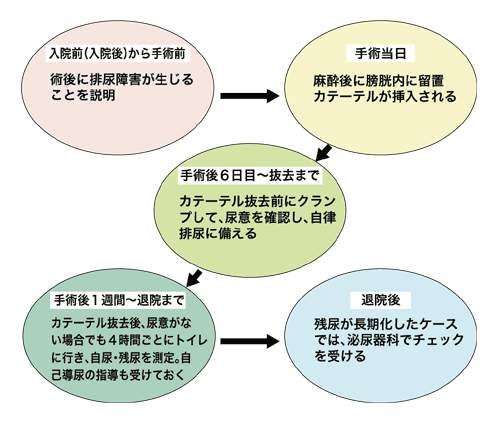
自力排尿のコツは、水分補給とやさしい腹圧
●自己排尿のコツ
尿意がある場合は、そのつどトイレに行くようにします。尿意がない、または弱い場合は、3、4時間ごとに時間を決めてトイレに座り、息を吐きながら、両手で下腹部をおなかをさする程度に軽く押してみます。あまり強く腹圧をかけると膀胱を傷めたり、尿が腎臓に逆流したりする可能性があるので、注意しましょう。
トイレに座り、おじぎをするように上体を前に倒して腰を少し浮かすと排尿できるという人もいます。 「1日に出る尿の量は1~1.5リットルとされています。それに見合う量(1.5リットル)の水分を少しずつ補給することも大切です」
このほか、シャワートイレで刺激する、水の流れる音を聞くなどの方法も排尿を促すきっかけになることがあります。
前述のように、残尿がある場合は、時間を決めて間欠的自己導尿で排尿します。
覚えておきたい自己導尿法
●用意するもの
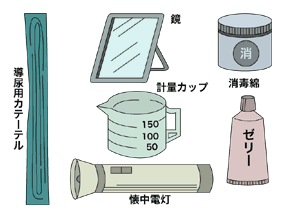
導尿用カテーテル 消毒綿 ゼリー 尿計量カップ 鏡 懐中電灯
●手順
(1) 石鹸で手をよく洗う。指先や指の間も忘れずに
(2) トイレに入り、まず自力で排尿する。できない場合は無理せずに
(3) 浅く腰掛けて脚を開き、尿道の入り口が自分で確認できるように鏡を足元に置く
(4) 尿道の入り口を消毒綿で十分に拭く。手や指も拭く
(5) カテーテルを利き手で持ち、先端部をゆっくりと尿道の入り口からやや上向きに、4、5センチ挿入する。カテーテルを落としたら、よく洗い、消毒する

(6) 尿計量カップにカテーテルを垂らして尿を出す。このとき、おなかをふくらませたりへこませたりすると尿がよく出ることがある。尿が出ないときは、カテーテルが抜けないように注意しながら、ゆっくりと引いたり奥に入れたりしてみる
(7) 完全に尿が出たらカテーテルを抜く。カテーテルを指でつぶすと垂れにくい
(8) 尿量を記録する。カテーテルは毎回水道水で洗う。週1回は外筒とともに専用ブラシと中性洗剤でよく洗う。カテーテル用消毒液は1日1回交換する。カテーテルの寿命は半年が目安
排尿トラブルなら泌尿器科で検査、治療を
退院後も排尿障害が残っている場合は、泌尿器科を受診し、膀胱機能の状態をチェックする尿流動態検査(ウロ・ダイナミックス)を受けて、原因に応じた薬物療法など適切な方法をアドバイスしてもらいます。神経因性膀胱の場合は、下腹神経(交感神経)、骨盤神経(副交感神経)、陰部神経(体性神経)のそれぞれに対して蓄尿、排尿に作用する治療薬物があります(下の表参照)。
検査には、臓器の位置等の異常を調べる内診、残尿の程度を調べる超音波検査、膀胱機能の回復検査、水腎症等のチェックなどがあります。
「検査を受ける前に、日付と尿意、失禁、違和感の有無などを2、3日記録して持参するとよいでしょう。口頭のみで説明するより医師に症状が伝わりやすいですね」
なお、泌尿器科を受診する場合は、主治医に紹介状を書いてもらうのがベストです。泌尿器科によっては、男性患者さんの診療や治療を中心にしているところもありますから、婦人科がん手術後の神経因性膀胱に詳しい医師がいるかどうかを電話などであらかじめ確認しておくようにしましょう。
| 神経 | 種類 | 作用 | 畜尿障害 | 排尿障害 |
|---|---|---|---|---|
| 下腹神経 | 交感神経 | 膀胱体部 弛緩 | β2作動薬 | α1遮断薬 |
| 内尿道括約筋 収縮 | α1遮断薬 | α1作動薬 | ||
| 骨盤神経 | 副交感神経 | 膀胱体部 収縮 | 抗コリン薬 | コリン作動薬 |
| 陰部神経 | 体性神経 | 外尿道括約筋 収縮 | - | β2作動薬 |
[排尿障害の治療薬]
| 化学名(一般名) | 商品名 | 用量 ( )内は1日に分けて服用する | 副作用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 排出障害 | α1遮断薬 | ウラピジル | エブランチル | 30~90mg(分2) | 起立性低血圧 |
| コリン作動薬 | 塩化ベタネコール | ベサコリン | 30~60mg(分2~4) | 流涙、顔面紅潮、発汗、胃腸障害 | |
| コリンエステレース阻害薬 | 臭化ジスチグミン | ウブレチド | 5~20mg(分1~4) | 消化器症状 | |
| 蓄尿障害 | 塩酸イミプラミン | トフラニール | 30~50mg(分1~2) | 口渇、排尿困難 | |
| 塩酸オキシブチニン | ポラキス | 3~9mg(分1~3) | 口渇、排尿困難、便秘 | ||
| 塩酸プロピベリン | バップフォー | 20~40mg(分1) | 口渇、排尿困難、便秘 |


