もっと気軽に患者さんが心のケアを受けられるには
看護師さんの優しさで 心が救われることがある
患者の中には、看護師さんの「心のケア」に助けられたという声も多い。
松沢さんと同様に、乳がん患者でNの会の世話人であるK・Hさんは、検診で「余命1年と言っていいくらいの状態」と告げられた。腋窩、鎖骨下リンパ節にも転移があり、手術では「鎖骨下まで取れないかもしれない」と言われ、それでも手術をすることに意味があるのかと悩んだ。
「Nの集いの会合のあと、歩きながらオブザーバーの乳がん認定看護師さんと手術の話をしました。その方は手術をしたほうがいいとも、しないほうがいとも言わず、『ただ手術をしないと、花が咲いたようになります(がんが乳房から出てくる状態になる)』と、教えてくれました。本やインターネットで調べても、手術をしなければどうなるかわからなかったので、それを聞いて手術をする気持ちになれました」
前出の八谷さんも、看護師さんの対応に救われたことがあると言う。
「娘の治療の手立てがなくなって茫然自失の状態だったとき、顔見知りの看護師さんが背中をさすりながら、『お母さんの愛情は、娘さんにいっぱい伝わっていますよ』と励ましてくれたのです。私は緊張の糸が切れたように、看護師さんに寄りかかって号泣しました。あの看護師さんの優しさで、心につかえていたものが、取れたような気がしました」
診療科の名称が統一されるとわかりやすくなる
緒方さんは、がん患者の心のケアの現状について、次のように話す。
「多くの患者は不眠などの症状があっても、受診をしようとは思いません。これが心の病気だと気づかないのだと思います。これについては、私たち患者も学ぶ必要があると思います」
また一方で、患者が心のケアを受けるにあたって分かりにくいのではないか、と医療側の問題も指摘する。
「心のケアをしてくれる診療科には各病院でいろいろな名称があり、大きく分けて緩和と精神の2つのカテゴリーに分けられているようです。緩和のカテゴリーでは、緩和医療科(部)、緩和ケア科、緩和ケアチームなど。精神のカテゴリーでは精神腫瘍科、腫瘍精神科、心療内科、サイコオンコロジー科などです。病院によって心のケアに対する名称が違っていては、心のケアを必要とする患者や家族に届きにくいのではないでしょうか。患者目線の荒唐無稽な発想かもしれませんが、ずばり『心のケア科』という名称にしたら、わかりやすいと思うのですが……」
1人でも多くの人に患者会に参加して欲しい
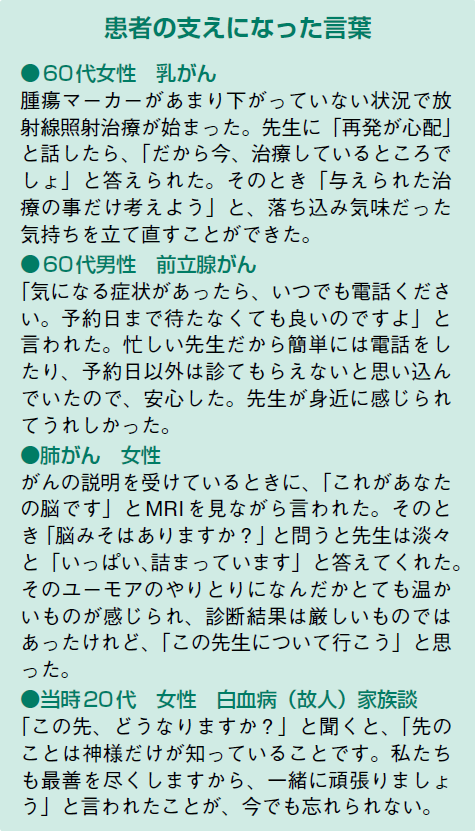
患者会に参加して前向きな気持ちになれる人は少なくない。患者にとって今の状況や思いを語り合うことで、1人ではない、仲間がいると感じられることは心強いもの。
「乳がんでは治���の選択肢が増え、なかなか自分で決められず、迷う人がたくさんいます。主治医の他に、治療のことを相談できる医療相談室やピアサポート、患者会と3方向の関わりがあったら、悩みや心の負担も少なくなると思います」と松沢さん。
続いて緒方さんは、「この神奈川県立がんセンターはそうした取り組みがすでになされていると感じています。例えば『怖くて検査結果を1人では聞けない』という方が患者会に相談にいらっしゃったのですが、そのことを患者支援センターに伝えたところ、その方の受診のとき看護師さんが同行してくれました。看護師さんが先生の話をやさしく伝えてくれて、彼女も安心したようでした。
私たちの患者会も12年続き、患者同士お互いが励まし合い、支え合う場作りに貢献できているのではないかと思います。ただ、患者会にもつながらず、1人で悶々と殻に閉じこもっている患者さんがいることも事実です。そんな患者さんが、患者支援センターやその他の情報を通じて、1人でも多くの方に患者会に参加していただけたらと思います」
緒方さんは今後も患者会として、患者支援センターと連携しながら、世話人みんなで力を合わせて継続して行きたいと言う。


