薬物療法とカウンセリングで治療成績も向上 QOLを低下させる心の病。早期治療で改善を
治療の柱は薬物療法とカウンセリング
適応障害やうつ病などの心の症状、病気に対する治療法として、カウンセリング、薬物療法という2つの治療が行われている。原則として症状が軽度の場合にはカウンセリング、うつ病など一定以上の場合には薬物療法が行われるが、現実の治療はもっと柔軟に行われている。
「うつ病患者さんの中にも、薬は使いたくないという人もいるし、逆に軽度の適応障害でもスパッと治したいと自分から薬物療法を求める人もいる。現実の治療は患者さんの希望も加味するのでケース・バイ・ケースです」
もう少し具体的に見ていこう。
薬物療法はその人の症状に対して大きく3種類の薬剤が使い分けられる。
「一般的に不眠が続いている場合は睡眠導入剤を、不安やイライラが収まらないときには抗不安薬を処方します。これらは大きな区分では精神安定剤に含まれる薬です。
| 薬剤名 | 初回投与量 (mg/回) | 臨床用量 (mg/日) |
| 定型抗精神病薬 ハロペリドール(セレネース) クロルプロマジン(コントミン/ウインタミン) | 0.5~2.5 10~25 | 0.5~10 10~50 |
| 非定型抗精神病薬 リスペリドン(リスパダール) クエチアピン(セロクエル) オランザピン(ジプレキサ) | 0.5~1 25 2.5~5 | 0.5~4 25~100 5~10 |
一方、症状が悪化してうつ病に移行している場合には、SSRI(*)やSNRI(*)など、比較的副作用が少ない抗うつ薬が処方されることが多いです。またせん妄に対しては、その原因となる症状を取り除く治療が行われます。例えば、高熱が原因となる場合は、解熱剤の投与などが行われます。それでも改善が難しい場合、抗精神病薬が用いられます(図4)」
当然ながら、これら薬剤にも副作用の不安がある。そこで抗がん剤など、治療による副作用を確認したうえで薬剤処方の是非、さらに薬剤の選別が行われるという。また睡眠導入剤などには、依存性という問題もつきまとう。症状が収まれば、使用も中断するのが鉄則だ。

一方、カウンセリングには薬物療法のような即効性は持ち得ない。しかし、面談を重ね、話を続けるなかで混乱していた心のありようが整理され、本来の落ち着きを取り戻す患者も多いという。
具体的なカウンセリング方法として、清水さんはまず患者さんに共感することから始めるという。
「よろしければ今1番困っていらっしゃることを教えてください、という言葉かけから面談を始めることが少なくありません。基本的には相手に話をしてもらう。私たちは共感を持って話を聞くという立場に徹しています」
カウンセリングで話すことで、自らの状況を整理し、心の平穏を取り戻す患者さんも少なくないという(写真5)。
*SSRI=セロトニン再取り込み阻害薬。パキシル(商品名)など
*SNRI=セロトニン・ノンアドレナリン再取り込み阻害薬。トレドミン(商品名)など
早期発見と早期治療が大切
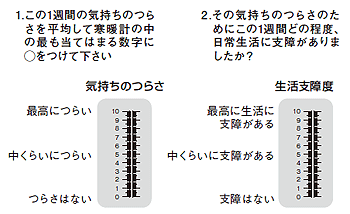
このように医療現場では、心の症状、病気に対して薬物とカウンセリングという2本柱の治療が行われている。清水さんは心のケアに関しては、早めの対策が重要だと語る。
「大切なのは症状が現われた段階で、すぐに対処することです。とくにうつ病対策としては、意欲の低下を感じたときに、早期に対策を講じていただきたいと思います」
自らできる具体的な方法としては、散歩やストレッチなどで体を動かし、気持ちを切り替える。例えばパチンコやカラオケなど、好きなことをして気分転換することも対症療法としては有効だと清水さんはいう。
「心が落ち込むのは病気のことばかり考えていることにもよります。現実逃避が必要な場合もあり、1日の中で少しでも病気を忘れる時間が大切です」
また症状が進行し、生きることの意味が分からなくなり、無価値観に苛まれるようになった場合は、自らの歴史を回想することも有効な手立てになりうるという。
「どんな人にも歴史があり、そこには必ず人に誇ることのできるエピソードが秘められているものです。そのことを振り返ることで自らの価値を再確認するのです」
最近では早期発見を助けるため、「つらさと支障の寒暖計」というチェック表がスクリーニングとして使われている(図6)。これを使い、つらさの点数が4以上で、かつ支障の点数が3以上の場合は適応障害や、うつ病である可能性が高いので、精神腫瘍科で診療することが望ましいという。
また、そうした早めの対策とともに、医療者との連携も重要だ。「困ったと感じたら、1人で抱え込まず、とにかく医師や看護師に伝えてほしい」と清水さんは話す。自分の殻に閉じこもらないことこそが、心の症状、病気を緩和する最大の原則といえるのかもしれない。


