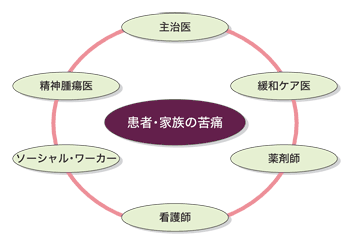心理的に追い詰められないためのケアと専門家へのかかり方 これだけは知っておきたい! 心のケアの基礎知識 | ページ 3
重症のうつ病の場合
死にたいほどつらい患者さんは必ず専門家につなぐ
患者さんをサポートする方に気をつけていただきたいことは、うつ状態に陥っている患者さんが「死にたい」という言葉を口にするときです。
それは、『死にたいほどつらい』という気持ちを打ち明ける言葉ですから、「そんなことをいってはだめ」などと否定せず、「そんなにつらいの?」と患者さんの気持ちを聞いてください。
そして、専門家につなげていただけるようお願いします。主治医に相談し、専門家を紹介してもらってください。主治医への相談が難しいときは、先にお話ししたがん拠点病院の相談支援センターに相談してください。
がん患者の自殺率は、一般の人の自殺率の2倍といわれています。(1)進行がんの方に多い、(2)告知からまもない――ことが特徴です。このほか、痛みが強いケースでも、自殺率は高くなっています。サポートしている患者さんがこうした状況に当てはまる場合は、注意深く患者さんを見守ることが大切ではないかと思います。
適切で十分な情報も、がん患者さんのつらさを和らげるものだと思います。
はじめての抗がん剤治療でどんな副作用が出るのかなどを心配している方もいるでしょう。
私たち精神腫瘍科医から主治医の先生に患者さんの心配ごとをお話しし、主治医の先生から患者さんに説明していただくこともあります。
ただ、進行がんや再発がんの場合、実際に病気の先が見えないことは事実です。いちばん大きいのは、「私の命はあと半年あるのか、1年なのか」という点です。残された時間を有意義に過ごしたいと考えて、今日、稲を植えようと思っても、半年後に自分が倒れてしまうかもしれないと思うと、とても稲を植えようという気になんてなれません。不確実な状況に向き合うのは、人間にとって本当に難しく、つらいことなのです。
そうしたつらさにも、薬物や専門家のカウンセリングなどを最大限に役立てていただきたいと思います。
とくに、大変なのは、抗がん剤などの効果が得られなくなり、治療が打ち切られるときです。見捨てられたように感じる患者さんも少なくないと思います。
しかし、ここでぜひ知っておいていただきたいのは、痛みや不快な症状をとる緩和ケアは、今はたいへん進んでいて、抗がん剤治療が終了しても、がん患者さんのためにできることはたくさんあるということです。「抗がん剤は使わないけれど、患者さんの体調を維持するための治療を精一杯やっていく」ことも、とても大切だと思います。
がん終末期の心の痛み
終末期に強くなるつらさ「スピリチュアルペイン」
もう1つ、がん患者さんが感じていて、とりわけ終末期が近づくと強くなるつらさに、「スピリチュアルペイン」があります。
人間の苦痛は、4つに分類できるといわれています。身体的苦痛、社会的苦痛、精神的苦痛、そして霊的苦痛(スピリチュアルペイン)の4つです。
身体的苦痛とは文字通り、体の痛みを意味します。社会的苦痛とは仕事を辞めなければならなくなるなど、社会的立場に打撃を受けること。そして、精神的苦痛は心を病んだ状態になることです。
けれども、4つめのスピリチュアルペインは、ほかの3つとはちょっと違ったつらさです。
思考力は正常に保たれているのに、置かれている状況に生きがいがない、生きる意味が感じられないといったものです。たとえば、プロ野球のピッチャーが、事故で効き腕を失ったときなどを想像してみてください。その人を支えているものが、なくなってしまったことにともなう心の痛みなのです。
がんの患者さんの多くは、4つの苦痛をいろいろな形で感じています。たとえば、仕事を失うことは社会的苦痛をともないますが、同時に支えているものがなくなる=スピリチュアルペインを感じる方も少なくないでしょう。そもそも、70歳まで生きられると思っていた人が、50歳で死を迎えなければならないことも、強いスピリチュアルペインを感じることではないかと思います。
もともとこの分類は欧米でつくられたもので、キリスト教信仰との関連もあるのでしょうか、「霊的(スピリチュアル)」と呼ばれています。そのため、日本では少し意味合いが違っているのですが、日本人の患者さんに多いスピリチュアルペインとしては、「家族に迷惑をかけてしまう」「家族の負担になっている」などのつらさです。大黒柱だった自分が働けなくなり、逆に家族の負担になるのでは生きている意味がない、などといった苦痛です。
それはある意味、人生観、死生観にもかかわる苦しみです。日本人の多くは、「あまり死を意識したくない」と望んでいます。死に対する恐怖を根本的になくすことはできませんが、家族がそばにいることで安心を得ている人は少なくありません。
緩和ケアが充実し、痛みやつらさを感じずに過ごせるようになっていることは、この点でも患者さんの味方になってくれていると思います。患者さんが痛みやつらさを訴えずに少しでも長く過ごせれば、家族にかける負担もぐっと少なくなります。
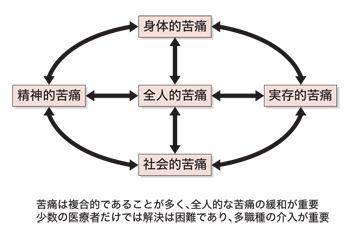
サポーターのケア
さえぎらずに話を聞き、励ましすぎない
最後に、がん患者さんをサポートしているご家族へ、がん患者さんのケアのポイントについてふれておきます。
1つめは、がん患者さんの話はさえぎらずに聞きましょう(=患者さんに共感する)。
2つめとしては、励ましすぎないことも重要です。
がんの患者さんは、常に全力疾走の状態です。たとえば、出された食事の3分の1をやっと食べているのに、家族に「もっと食べなくちゃ元気になれないよ」といわれると、ガッカリです。3分の1がご本人にとっては、「すごい量」なのですから。
ですから、「がんばれ」というより、むしろ「大変だね」という共感や「大丈夫?」という問いかけがよいと思います。
私たちのような専門家でも、患者さんの話を聞くとき、「こういうふうに変えてあげよう」と思うと、うまくいかないことが多いんです。その人の話を一生懸命聞き、「あなたはこうなんだね」と共感する――それはカウンセリングの基本ですが、結果として患者さんは「私の気持ちをわかってもらえた」という思いから気持ちが軽くなり、前に進めるようになるようです。
でも、気を許している家族だからこそ、なかなかうまく話を聞けないこともあります。
専門家の出番には、そうした意味もあるのです。
ご家族についてもう1つ大事なのは、サポートする家族の側も、がんによって傷ついているということです。「つらいのは本人だから、私はがんばらなきゃ」と気持ちを押さえ込んだり、つらい気持ちを患者さんにぶつけて落ち込んでしまうといったことがよくあります。
じつは、家族は第2の患者ともいわれています。家族のほうが、うつ病率が高いという研究もあるくらいです。家族の皆さんは「患者をケアするために、私自身が休むことが必要だ」と考え、ストレスをためない工夫をすることが大事です。専門家のいる病院では、家族の相談にも乗ってくれます。その場合は患者さんと一緒ではなく、別々に時間をとってもらうことをお勧めします。一緒だと、おたがいに遠慮してしまうからです。
がんになること、家族ががんになることは、とてもつらいことです。悩んだり、落ち込んだり、こわがったりするのは、あなただけではありません。みんな同じように悩んだり、落ち込んだり、こわがったりしているのです。あなたは、1人ではありません。
心をケアする場所は、たくさんあります。つらいときは、私たち診療科の扉を叩いていただきたいと思います。