まずは、「人と話す」ことが大切。それが適応障害やうつを予防する 効果的ながん治療は「心のケア」から
不眠・食欲不振・倦怠感の症状に注意する
- ●抑うつ気分
- ●通常楽しむことのできる活動に対する興味の低下
- ●活力の減退、疲労感の増加
- ●自信喪失、自尊心の低下
- ●自責感、過度の罪悪感
- ●自殺念慮、自殺企図
- ●思考力・集中力の低下
- ●焦燥、精神運動抑止
- ●睡眠障害
- ●食欲の変化(減退、ときに増進)
- これらの症状が1日中ほとんどで、毎日2週間以上続く
がんが見つかったばかりの初期段階では、このようなコミュニケーションによるケアが有効に作用する。ところが、初期治療が終わった後も、心の平静を取り戻すことができず、逆に心身の状態が悪化していくこともある。
「もともとナイーブで傷つきやすい性格の持ち主はもちろんのこと、本来はおおらかなタイプであっても、治療がうまくいかない、薬剤が効果を現さないなど、『悪い知らせ』が続くと、心の落ち込みが適応障害やうつ病へと進行していくことが少なくありません」
うつ病になると、心身が不調になりQОLが低下するばかりでなく、意欲が減退して根拠のない自責感が募り、最悪の場合には自殺衝動に駆られることもあるから要注意だ。ちなみに適応障害というのは、不安や恐れなどのネガティブな感情が高まった結果、日常生活に支障をきたすケースを指している。また、こうした心の症状は、ときにはがん治療よりも問題が深刻化することもあるからやっかいだ。
適応障害、うつ病の前兆として佐伯さんは次の3点を指摘する。
「眠れない、食べられない、そして倦怠感に見舞われるようになると、心の状態がかなり悪化していると考えるべきでしょう。とくに気をつけたいのは睡眠障害。眠れないことで体調が悪化し、それにつれて心の状態もどんどん落ち込んでいくようになります」
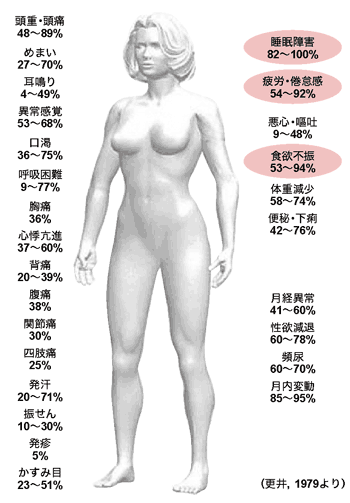
| 内科 | 高血圧症、 過敏性腸症候群、 糖尿病、 胃・十二指腸腫瘍 |
| 産婦人科 | 更年期障害、 月経前症候群 |
| 外科 | 術前・術後のうつ状態 |
| 整形外科 | リウマチ、 頸部外傷後遺症、 腰痛症 |
| 泌尿器科 | 膀胱神経症 |
| 耳鼻科 | 咽喉頭異常感症、 めまい、耳鳴 |
| 眼科 | 眼精疲労 |
| 皮膚科 | 慢性じんましん、 円形脱毛症 |
| 全科 | がん |
コミュニケーションに加えて薬物による治療も
佐伯さんは、そうした事態を回避するために、前にあげたコミュニケーションに合わせて、薬物の使用もケアに取り入れている。
これががん患者に対する第2段階の心のケアだ。
「不眠が始まったばかりの段階では、たとえばぬるま湯にゆったりつかって体を温めて気持ちをリラックスさせる方法も有効です。しかし、それでも眠れない場合は、睡眠導入剤の使用も積極的に考えるべきでしょう。また、痛みがあれば眠れるはずがありません。その場合は医療用麻薬などの鎮痛剤(痛み止め)を使用し、痛みを取り除く必要があります。不眠対策にアルコールが利用されることも多いですが、これは決して効果的な対策とはいえません。お酒を飲んでも寝つきがよくなるだけで、決して深い眠りは得られない。それに依存性も強く、薬物よりもはるかに危険です」
適応障害やうつ病に対する薬物の使用には、3つの段階があるとも佐伯さんはいう。
「眠れなくなったときは、適応障害やうつ病を予防する意味で、睡眠導入剤を利用する。しかし、その段階を通り越して軽度の適応障害やうつ病が現われた場合には自律神経の働きを調整する抗不安薬を、そして誰の目から見てもうつ病であることが明らかな場合には、抗うつ剤を使います。また、痛みがあれば医療用麻薬などの鎮痛剤(痛み止め)を使用します。
薬の使用には不安を感じる人もいるかもしれませんが、実際には安全面での不安はほとんどありません。たとえば睡眠導入剤などは、高血圧の人が使う降圧剤より体への影響は断然少ないことがわかっています」
もっとも、薬による治療を行ったとしても、コミュニケーションによるケアは欠かせない。
人と話すことで心を開放する――それが心のケアの最大の基本であることは変わりない。
「第2の患者」である家族にも心のケアを
- ●患者さんの話をよく「聴く」
- 聞く(耳に入れる)
- 訊く(たずねる)
- ●家族にも必要
- 家族も話を聴いてもらうことで癒される
- 話すだけでも気持ちが軽くなる
- ●場合によっては、薬も役に立つことがある
ところで、適応障害やうつ病など、心の症状が現われるのは患者だけとは限らない。患者をサポートする家族にも、同様の症状が現われることが少なくないと佐伯さんはいう。
「たとえばがんであることを告知されていない男性のがん患者さんが不安や恐れを口にし続けたために、奥さんが罪悪感からうつ病に陥り、自殺未遂まで起こした場合もあります。第2の患者と呼ばれるように、患者さんを支える家族もまた、不安や恐れから心を消耗しています」
このように家族も、患者と同じように自分を理解してもらえる相手を求めている。そこで佐伯さんは、介護に疲れた家族を見ると、必ず積極的に声をかけ、話を聴くようにしている。その際患者についてではなく、その人自身について話してもらうことが大切だとも佐伯さんはいう。
「毎日、ご主人を見舞っている奥さんを見れば、その人自身の話を聴くようにしています。家族も患者さんと同じようにギリギリのところでふんばりながら、患者さんの病気と闘いつづけています。でも、患者さんと違って誰もそのことを理解してくれず、ひたすらストレスが募っていく。そうした状況を理解して、その人自身の話を聴くことで、心が開放され、苦境から脱することができるのです」
言葉を換えると、患者の家族もまた、自分を理解してくれる誰かを見つける必要があるということだ。
がんという病気は、患者だけでなく、患者を支える家族の心にも暗く深い影を落とす。佐伯さんが家族を「第2の患者」と呼ぶのもそのためだ。
がんによって心に忍び寄る暗い影を振り払うために、患者自身はもちろん、患者を支える立場の家族もまた、「自分を語る」ことから始めたい。


