がん患者を襲う「心の副作用」うつ病に備える 手だては早期発見、早期治療。何もせず、ひたすら心と体を休ませよう
知られていないがん患者の「うつ病」
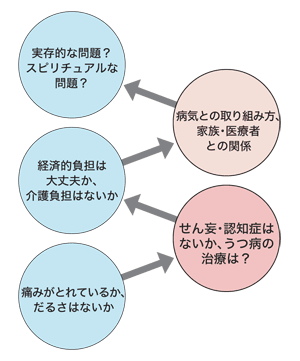
こうしてみると、がんという病気、あるいは治療の副作用としてもたらされる「心の危機」は初発直後にピークがあると考えてよさそうだ。では、じっさいに危機が訪れたときに医療機関では、患者に対してどう対処しているのだろうか。
まず知っておかねばならないのはそうした患者の心の状態について医師、看護師、そして患者本人も無自覚であることだ。
「医師や看護師は日々、仕事に忙殺されています。患者さんの心の状態を察知するには、その患者さんの来歴や性向を把握する必要がありますが、とてもそこまでは手が回らない。また患者さん自身もプライドが邪魔をすることもあって、自らの心の不安を他者に打ち明けようとは思わないケースがほとんどです。まして自分から精神科を受診することなどほとんどありません。そのため、すでにうつ病に陥っていても、多くの場合は、まだ大丈夫だと無理やりに自分にいい聞かせながら心の葛藤を繰り返しているのです」
さらに多くの医療機関では、がん患者を対象にした心のケアの対策が不十分な状態であることも見逃せない。がん対策基本法によって、この10月には全国375施設のがん診療連携拠点病院で非常勤以上の精神科医の常駐体制が整えられている。しかし、それがどう機能するかは不透明な状態だ。
内富さんが在籍している国立がん研究センター東病院のように、精神腫瘍科が設けられているところでも患者の精神科の受診率は決して高くはない。
「心の状態が心配な患者さんに、1度、精神科を受診してみませんか、と促しても、じっさいに受診するのは4人に1人。日本人の精神風土によるものでしょうか。患者さんにとって、精神科の敷居はまだまだ高い状態が続いています。また、うつ病になると精神科を訪ねようと思っている人も、自らの症状を過小評価するために受診が遅れる傾向があります」
患者さんの取り組み方、対処法を支持する
そこで、国立がん研究センター東病院では「つらさと支障の寒暖計」と呼ばれる物差し(指標)を用いて患者を診断している。
このチェックを行うことで、初めて自らがうつ傾向にあることがわかり、精神科を受診する患者も多いという。では、受診後はどのような治療が行われるのだろうか。
「どんな症状を訴える患者さんに対してもまずは100パーセント、カウンセリングを実施します。カウンセリングの内容は、患者さんが過去、つらい状況から抜け出すときのその人なりの取り組み方、対処法を支持していきます。じっさい、ほとんどの場合、患者さんは正しい選択をしています」
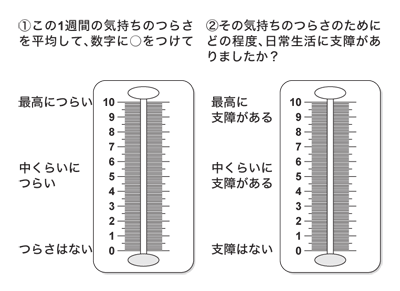
抗不安薬、睡眠導入剤、抗うつ剤などの薬剤が用いられるのは受診者の半数程度。そのなかでSSRIなどの抗うつ剤が処方されるのは2割前後だという。
がん患者の中には、これらの薬剤、とくに抗うつ剤の服用には不安を覚える向きもあるかもしれない。しかし内富さんはとくに抗うつ剤に関しては、「つらい時期に必要最小限服用する限りはまず副作用の心配はほとんどない」という。
「かつて用いられていた薬剤に比べると、現在の抗うつ剤は副作用がほとんどなく、効果も高い。じっさい、最近になって利用者も年間100万人台から200万人台へと倍増しています。ほとんどの人は、安心して服用することができるでしょう」
不安を払拭する3つの対処法
もっとも、現実にはこうした治療を受けているのは、ごく一部の患者に過ぎない。うつ傾向が現われても、大半の患者は「まだまだ大丈夫」と自分にいい聞かせながら、症状を重症化させているのが実情だ。この「心の危機」を打開するには、まずは患者が自らの心の状態を早期に察知する必要があるだろう。そのためには、どんな手立てが求められるのか。
「がんの告知などでショックを受けた後、2週間経ってもまだ仕事や家事に向かう気力が持てない場合は要注意でしょうね。不眠や食欲不振などの身体症状が続いている場合は、うつ状態に陥っている可能性はさらに高いと見るべきです」
と、内富さんは指摘する。
では、そうした危機が察知されたときには、自分自身に対してどんな取り組みが求められるのだろうか。内富さんは、がん患者が不安を払拭するための3つの対処法を提言する。
「まず第1は、自分自身を支えてくれるサポーターを見つけること。家庭で1人、職場で1人、趣味の会で1人。患者会に参加して、そこでも1人見つけられれば自分の中に引きこもってしまうことはまずないでしょう」
第2は、過去の自らの行動体験の振り返りだ。がん体験ほどではないにせよ、どんな人でもそれまでの人生で困難や心の危機(育児、転職など)などを克服した経験を持っているはずだ。
「そのときの対処法をもう1度、実践してみるのも効果的です」
と内富さんはいう。
そして、第3の対処法は先輩患者に学ぶということだ。
「たとえば患者会などに顔を出して、同じがん患者さんの先輩がどのように心の危機を乗り越えたのかについて、話を聞いてみることです。心の不安も身体的な痛みと同じで、先の見通しが立てばずっと楽になる。そうして気持ちが軽くなれば、うつ病や適応障害に陥る危険も解消できるでしょう」
さらにもう1つ、心の不安を乗り越える前提条件として、忘れてならないのはつらい時期に無理に不安を解消しようとしないことだという。
「ショックを受ければ、誰でも落ち込むのが当然です。そんなときには引きこもってじっとしていればいい。がん告知を受けたり、ホルモン治療でうつ傾向が現われた場合は2週間は無理をせず、食べて寝る以外は、仕事も何もしないというのんびりした生活を続ければいいのです。多くの場合は、そうしているうちに自然とまた元気が出てくるものです」
無理をせず、何もしないでひたすら心と体を休ませる――。
こうした心と体の休養が、心の危機を回避するための1番の特効薬といえそうだ。


