もう怖くない!ダンピング症候群や骨量低下などの後遺症。しびれやめまいの新しい原因も判明 胃がんの術後後遺症とそのQOL改善策
逆流性食道炎になると食道ががん化しやすい?
手術によって胃の逆流防止機能が損なわれ、胃液などの消化液が食道に上がってきて起こるのが「逆流性食道炎」。胸焼けや胸痛、しみる感じなどの症状がみられる。欧米では逆流性食道炎から食道がんになる人が増えているといわれる。
「食道の粘膜は扁平上皮と呼ばれる細胞の集まりでできていて、普通、食道にできるがんは扁平上皮がんです。これに対して胃の粘膜は粘液を分泌する腺管と呼ばれる管のようなものが広がっていて、逆流性食道炎になると、食道の粘膜がどんどん胃の粘膜に変わっていき、がん化すると腺がんになります。日本では少ないのですが、今後増える可能性があります」(利野さん)
治療薬としてよく用いられるのは、FOY(タンパク分解酵素阻害薬)という膵炎の薬。消化酵素の働きを阻害する作用があり、「フオイパン」(一般名メシル酸カモスタット)という飲み薬がある。胃潰瘍薬で制酸剤のPPI(プロトポンプ阻害剤)も効果があるといわれている。
手術して胃を切除し、胃酸分泌がなくなったにもかかわらず胃炎に苦しむ人がいる。
「そこでヘリコバクター・ピロリ菌の有無を調べると、陽性の人のほうが胃炎の症状が悪く、除菌治療するとよくなるようです」(利野さん)
一方で、ピロリ菌の除菌治療をすると逆流性食道炎になる人が増えるという報告もある。ピロリ菌がいると胃の中はアルカリに傾くので、酸を出す消化管ホルモンの働きで胃の入口が閉められる。ピロリ菌がいなくなると、入口を閉めるホルモンが減るので、逆流しやすくなるといわれているのだ。別の報告では、除菌したからといって逆流性食道炎が増えることはない、という研究結果もあり、どちらが正しいかはわかっていない。
栄養が足りていない、は本当か?
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 30-40 | 2247 | 1760 |
| 40-49 | 2242 | 1813 |
| 50-59 | 2288 | 1875 |
| 60-69 | 2252 | 1810 |
| 70- | 1917 | 1647 |
[胃がん術後の術式別の食事摂取量の変化]
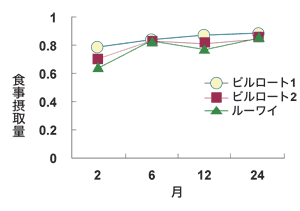
胃をとったり、小さくなれば、食事量が減る。また、胃液の分泌が減り、消化吸収も悪くなる。すると体重は減るばかりとなり、栄養障害に陥る危険性があるが、その点はどうだろうか?
「術後に体重が減ってくると、手術を経験した患者さんは、『再発したのでは?』と不安にかられがちになります。そこで、私たちは食事に関するアンケートをとりました」(利野さん)
利野さんら横浜市立大学の研究グループは胃がんの手術を受けた人を対象にアンケートをとり、術式別にみた摂取カロリーの推移を調べた。その結果、胃を全摘した人は手術直後は摂取カロリーが減るものの、退院後しばらくすると摂取カロリーが1000キロカロリーを超えていた。1年たってもう1度調べると、1600キロカロリーぐらいに回復していた。3分の2を切除した人でも、1年後を調べると1800~2000キロカロリーを摂取できていた。
以上は平均の数値だが、厚生労働省が定めた日本人の栄養所要量(必要量)と比べても男性の場合、胃切除術で40歳代で所要量の82パーセント、70歳以上だと89パーセントを摂れていた。胃全摘であっても40歳代で79パーセント、70歳以上では88パーセント摂れており、それほど少ないわけではない。
「みなさん、食べられないとおっしゃるが、実はそんなことはなく、普通に生活できるだけのカロリーは摂れるようになるので、心配いりません。ただし体重は戻りにくく、最初は元の体重の2割減ぐらいになり、1年たって全摘の人で1割減、3分の2をとった人で5パーセント減ぐらいになります。無理して食べるとダンピングになるので注意しましょう」(利野さん)
手術前は食べすぎていただけで、術後はむしろ正常な食生活に戻ったと理解できるわけだ。
ビタミンE欠乏が原因で起こる神経症状
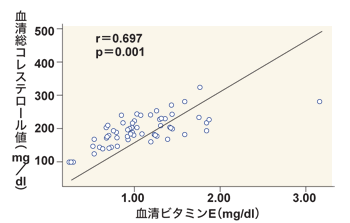
血清総コレステロール値と血清ビタミンEの間には相関がみられた
術後の後遺症としてあらわれるしびれやめまいは、これまでダンピング症候群によるものとされてきた。しかし、ビタミンEの欠乏が原因で起こることもわかり、注目されている。利野さんを中心とする横浜市立大学の研究グループの研究でわかったことだ。再発を認めない胃がん術後例55例を対象に調べたところ、55例中12例(21.8パーセント)でビタミンEが正常値を下回っていた。術式の違いでみると、ビタミンE低下群12例中11例で胃全摘手術が行われており、再建術式では、食物が十二指腸を通過しない術式が12例中11例を占めていた。
さらに、ビタミンE低下の12例のうち、11例が神経内科を受診し、めまいやしびれなどの症状を訴え、ビタミンE(ユベラ(商品名)、150~300ミリグラム/1日)を投与したところ、全例で神経症状が改善した。
「ビタミンEは、胆汁酸や膵リパーゼがないとほとんど吸収されません。また、食事である程度の脂肪の摂取も必要です。このため、胃切除術を受けた症例では食事摂取量、特に脂肪摂取量が減少し、再建術式によっては胆汁酸と食べたものとが混ざりにくい状態になるため、術後に脂溶性ビタミンの低下が生じ、神経症状に発展する可能性があります」(利野さん)
研究結果を受けて、利野さんらが行う再建術式は、可能な限り胃と十二指腸をつなぐ手術に変更しているという。
術後の後遺症のあらわれ方自体は昔も今も変わらないかもしれない。しかし、QOL(生活の質)向上のため、さまざまな研究や改善が取り組まれ、成果を上げているようだ。
| テスト項目(正常域) | ビタミンE正常・高値群患者(n=43) | ビタミンE低下群患者(n=12) | P値 |
|---|---|---|---|
| ビタミンA(65-276IU/dl) | 171.8±52.2 | 134.3±51.9 | 0.032 |
| ビタミンE(0.75-1.41mg/dl) | 1.2±0.4 | 0.6±0.1 | 0.001 |
| ビタミンB12(249-938pg/ml) | 572.7±408.3 | 399.2±263.9 | 有意差なし |
| 葉酸(2.4-9.8ng/ml) | 11.1±3.0 | 12.9±5.2 | 有意差なし |
| トリグリセリド(136-266mg/dl) | 100.0±50.7 | 73.4±38.0 | 有意差なし |
| 総コレステロール(男性41-201,女性24-134mg/dl) | 206.7±39.3 | 147.3±35.8 | 0.001 |
| 総タンパク質(6.9-8.3g/dl) | 7.3±0.5 | 7.4±0.7 | 有意差なし |
| アルブミン(4.4-5.4g/dl) | 4.4±0.3 | 4.4±0.3 | 有意差なし |
| 白血球(3,300-9,400/μl) | 5,674±1,206 | 6,717±2,029 | 0.028 |
| 赤血球(男性414-534,女性365-490×104/μl) | 388.5±54.0 | 387.5±60.3 | 有意差なし |
| ヘモグロビン(男性13.8-17.2,11.3-14.5g/dl) | 12.5±1.6 | 12.8±1.6 | 有意差なし |
| ヘマクトリット値(男性40-50,女性34-43%) | 36.9±4.7 | 38.2±4.9 | 有意差なし |
| 血小板(18-39×104/μl) | 22.0±6.2 | 24.5±10.4 | 有意差なし |


