適切なリハビリで快適な食生活を がん治療に伴う嚥下障害とその対策
嚥下トラブルを防ぎ、嚥下機能をスムーズに回復させるには?
入院中、早期からのリハビリテーションがきわめて有効
「頭頸部がんや食道がんなどの手術後、誤嚥性肺炎や栄養障害などのトラブルを未然に防ぎ、個々の患者さんの状態に合わせた食事の仕方にスムーズに移行するためには、手術後早い時期から適切な嚥下リハビリテーションを行うことが最大のポイントです」と辻さんは強調します。
トラブル防止とQOLアップを両立できる「嚥下リハビリテーション」の基本的な流れをご紹介しましょう。
「嚥下障害は外から診ても判断しにくいので、飲み込むときの状態をX線で透視できるビデオ嚥下造影検査(VF検査=下コラム参照)を行って、嚥下機能を客観的に評価(診断)しながら、それぞれの患者さんの状態に適した嚥下リハビリを行うのが理想的です。VF検査では、むせやせきがない不顕性の嚥下障害も見つけることができます」
まず、手術後2~3日目ごろから、食物を用いずに口や舌などを動かす「間接訓練」を始めます。術後1週間ほどでVF検査をして、きちんと飲み込めているか、誤嚥がないか、たんやむせ、せきの有無、誤嚥なく飲み込める食物の形態(きざみ方やとろみのつけ加減)、1口量などの嚥下機能(飲み込みの状態)をチェックし、嚥下障害の程度に応じてリハビリのプログラムをたてます。
嚥下障害が重い場合(食材の状態や食べる姿勢など、いろいろな工夫をしても誤嚥が起きるとき)は、とろみのついた水やゼリー、ペーストなどから食事の訓練(「直接訓練」)を始め、1口の量や、誤嚥の起きにくい姿勢などを工夫しながら、キザミ食、軟らかめの食事へと進めていきます(後述)。
「頭頸部がんや食道がんの手術後、嚥下障害が起こると予想される場合は、VF検査をしながら適切なリハビリを行うことで、リハビリをしない場合に比べて、入院期間も劇的に短縮され、食事の摂取もスムーズにできるようになることがわかっています」
静岡県立静岡がんセンターで2002年9月の開院時から約2年半、当時リハビリ科部長だった辻さんを中心に、頭頸部がん(口腔がん、咽頭がん、喉頭がん)、甲状腺がんの患者さん78名を対象に、VF検査をしながら嚥下リハビリテーションを行った結果、入院期間は平均24.8日(±10日)と劇的に短くなり、69名(約9割)は口から食べられるようになって退院。退院時に、胃ろう(PEG)や間欠的経管栄養(患者さん自身がチューブを出し入れできる経管栄養)など、チューブによる栄養補給が必要だった��腔がん、舌がん、咽頭がんの9名(手術後再建)も、週1~2回の外来での訓練や家庭での反復により、退院後3カ月で、5名は口からの食事摂取が可能となり、4名も口からの食事と経管栄養を併用できるようになりました。
「従来、頭頸部がん手術後の入院期間は、術後の感染などの影響もあって3カ月程度と長めでしたが、嚥下リハビリの効果と、術前からの口腔ケアで感染症の発症率が低下したことの相乗効果で、かなり短縮できました。また、退院後は、全員口からの摂取ができるようになったという意味でも、画期的な成績だといえます」
残念ながら、これらのがんの治療後、嚥下リハビリが行われていない医療機関がまだ多く、嚥下障害があるのに無理に口から食べさせて誤嚥性肺炎を招いたり、逆に口から食べられる可能性があっても「危険だから食事は無理」と判断されて、点滴や経管栄養だけになってしまうケースも少なくないのが現状です。
がん専門病院やがん拠点病院のなかで、頭頸部がん等の治療後の嚥下障害に対して計画的・総合的なリハビリテーションやVF検査を行っているのは、静岡がんセンターと東京都立駒込病院などごくわずかですが、他の医療機関にも広まることが望まれます。大学病院では、慶應義塾大学病院のリハビリテーション科をはじめ、VF検査を行っているところが多いので、治療後の嚥下障害で悩んでいる方は、1度受診されることをおすすめします(ページ下参照)。
Q ビデオ嚥下造影検査って何?
A 嚥下の状態を客観的に評価・判断できる透視検査です
慶應義塾大学病院の造影検査室。リクライニングチェアに嚥下障害の患者さんが座り、リハビリ科の医師2名が、造影剤入りのコーヒーやゼリーなどを注射器やスプーンで患者さんの口に入れていきます。
「とろみ2cc、いきまーす。はい、ゴックンと飲み込んでくださいね」
そばのモニターに、患者さんの横向きのシルエットが映し出され、飲み込んだ食物が口からのど、食道へと通過していく状態がライブで放映されます。
「のどに引っかかるような感じはしませんか?」
「しません」
検査室の様子がガラス越しに見える隣室では、同じ画像を見ながら、放射線技師が透視ビデオを操作し、他のリハビリ医、言語聴覚士(ST)、管理栄養士などのスタッフもモニターを囲んで、メモをとったり、患者さんの姿勢や嚥下の様子を評価(判断)したりしています。
「食べ物が、後ろ側(背骨側)の食道に完全に降りていれば正常。前のほう(おなか側)の気管に流れ込んだり、のどにひっかかっているときは、誤嚥の可能性があるので、注意しながらリハビリを進める必要があります。撮影中は微量のX線で透視していますが、放射線の量は、胸部X線検査とほぼ同程度で、ごく弱いものです」と辻さん。
ビデオの画像は、DVDに記録して、後から見直すことができるので、リハビリ法の検討の際にも役立ちます。
「ビデオ検査で嚥下状態を評価しながらリハビリを進めれば、患者さんの状態に応じたプログラムがたてられ、誤嚥などのトラブルも防ぐことができます」(同)
ちなみに、食道がん手術後12年目だという79歳の男性患者さんは、加齢とともに嚥下機能が弱まり、チューブ栄養になっていましたが、リハビリ開始後ほぼ4カ月で、ゼリーやおかゆを飲み込めるようになり、好物のトロをきざんだものにも挑戦中だとか。
「ビデオ嚥下造影検査」といういかめしい名前から、緊張した雰囲気を想像していましたが、和やかに検査が進められているのが印象的でした。

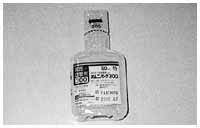





嚥下障害の診察・相談
慶應義塾大学病院リハビリテーション科では、月~土(第3土曜日を除く)の午前中(初診外来受付は8時40分から11時まで)診察を行っています(辻講師の診察日は、土曜日午前中)。紹介状があればベストですが、なくてもOK(所定の料金が必要)。セカンドオピニオンを受けたい方の受診も可能です。
連絡先/〒160-8582 東京都新宿区信濃町35番地 TEL03-3353-1211(大代表)


