適切なリハビリで快適な食生活を がん治療に伴う嚥下障害とその対策 | ページ 4
食道がんの手術後
食道がんの手術後は、気管のまわりの筋肉を切除するため、食道入口部が開きにくくなり、嚥下障害を起こすことがあります。また、のどの奥にある反回神経麻痺を合併すると、声帯が麻痺して気管の入り口にある声門という関所が閉じなくなり、誤嚥しやすくなります。
●嚥下リハビリのポイント
手術の前から食道通過障害によって食事がとれず、体力が低下している場合は、ミキサー食や液体の補助栄養剤(エンシュアリキッド、カロリーメイトなど)で補い、栄養状態を改善させて手術に備えるとよいでしょう。
手術後7~8日目に、誤嚥やのどに食物が残ってしまうと推測できる場合は、VF検査を行い、嚥下機能に合わせてリハビリを始めます。
・間接訓練で、喉頭マッサージ
喉頭挙上を促すために、喉頭のマッサージや前述のメンデルゾン手技、裏声発声訓練などを行います。
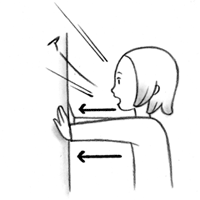
・プッシング・エクササイズも有効
反回神経麻痺が起こっている場合には、誤嚥予防のために、「プッシング・エクササイズ(声門閉鎖訓練)」や「息こらえ嚥下」の訓練を行います。
プッシング・エクササイズは、両手で力をこめて壁、机、椅子などを押しながら、できるだけ強く「アー」と発声し、声門を閉じる能力を高める方法で、上半身に力を入れるのがポイントです。「息こらえ嚥下」は、鼻から息を吸ってしっかり止め、ゴクンとつばを飲み込み、息をこらえたままで咳ばらいをするか、口から息を吐き出す方法です。何度も繰り返し練習しましょう。
・直接訓練はとろみ水かゼリーから
食事は、とろみをつけた水分かゼリーから始め、とろみつきミキサー食、とろみつきキザミ食、常食と上げていきます。息こらえ嚥下が体得できていれば、この方法で飲み込むと効果的ですが、うまくできないときは、逆に誤嚥を起こしやすいので注意が必要です。
頭頸部がんの放射線治療後
頭頸部がんの放射線治療は、単独または化学療法と併用される場合と、手術後の補助療法として行われる場合があります。およそ6週間の治療中、唾液腺分泌障害、疼痛などによって嚥下障害を起こすことが多いものです。
とくに化学療法との併用や術後の放射線治療では症状がより重くなり、回復にも時間がかかります。口から食べることが困難になることもままあります。
・頸の運動、アイスマッサージを
口から食べにくくなったときは、嚥下機能を維持するために、頸の運動やのどのアイスマッサージ、メンデルゾン手技などの間接訓練を中心に行います。放射線粘膜炎を起こしているときは無理をせず、粘膜を傷つけないようにすることが大切です。
・症状がおさまったら食事訓練
粘膜炎などの症状がある程度おさまり、直接訓練ができるようになったら、VF検査を行い、食事の訓練を始めます。ゼリーやとろみつきの水分から開始し、とろみつきミキサー食、とろみつきキザミ食、常食へと移行していきます。とろみをつけなくても誤嚥がないかどうか確認してから水分をとるようにします。
放射線照射による唾液腺障害や粘膜乾燥によって、食物がのどに張り付くように残ってしまうことがありますが、つばを飲み込む空嚥下を何度も繰り返したり、少量の水分ととろみつきの水分を交互に飲み込んだりすると、効果的です。また、唾液の代わりとなる人工唾液や、保湿剤、唾液腺を刺激する錠剤などを併用するのもおすすめです(「がん治療に伴う口腔合併症や感染症の予防と軽減」参照)。
脳腫瘍
脳腫瘍の場合、脳腫瘍そのもの、または手術後の脳浮腫によって嚥下障害が起こることがあります。いずれも、定期的な嚥下機能の評価を行い、そのときどきの状態に合わせた訓練や食事の調整が必要です。
・食事開始前に、検討
口から食べ始める前に、反復唾液テストや水のみテストなどのスクリーニング検査の後、必要に応じてVF検査を行い、適切な姿勢や1口の量、食事の内容、嚥下法を検討します。
・頸や口の運動で間接訓練
食事前から、頸や口腔器官の運動を行い、筋力低下がみられるときは、唇で舌圧子(舌を押さえる金属の平板なスティック。スプーンの背や割り箸などで代用できる)をはさみ、引き抜くときに、しっかり口を閉じるなどの方法を試してもらい、唇の閉鎖能力を高めます。
のどのアイスマッサージも、患者さん自身で行えるように練習しましょう。
意識障害がみられる場合は、氷を入れたポリ袋で顎下腺(のどの下にある唾液腺)や唇のまわりの皮膚をマッサージする「皮膚のアイスマッサージ」を試してみてください。唇を閉じる能力をアップさせ、よだれをたらすことも改善できます。
・食事はとろみつきから
全粥ととろみつきミキサー食、あるいはとろみつきキザミ食、水分にはとろみをつけてスタートします。患者さん自身が1口量の調整をしにくいときは、スプーンを小さくするなどの工夫をしましょう。集中力が低下しているときは、必要以上に声をかけすぎない、テレビを消すなど、食事の環境を整えることも大切です。
嚥下障害があるときは、どんな食べ物を選べばよい?
密度が均一で適度なとろみがあり、口の粘膜に張り付かず、のどごしのよいものを
「嚥下障害に適した食材の条件は(1)密度が緊密(2)適当な粘りがあってバラバラになりにくい(3)口の中やのどを通るときに変形しやすい(4)べたつかず、口の中の粘膜に付着しないことです」
●嚥下リハビリ開始時におすすめの食材は?
「液体は飲み込みやすいと思われがちですが、凝集性が低いため、のどで散らばり、もっとも誤嚥しやすい形態です。ポタージュ状、蜂蜜状のようにとろみがある液体はのどでまとまって、のどへの流入速度が遅くなり、誤嚥を防ぎやすいもの。誤嚥の危険の大きい場合には、お茶、味噌汁やキザミ食に増粘剤を加えて、適度なとろみをつけるとよいでしょう。なお、リハビリのスタート時点では、手術の部位によっても適する食形態がやや違います。舌がんの手術後は、唾液と混ぜ、1かたまりにしてのどに送り込むのが難しいので、
舌の運動に頼らずにのどに流し込めるさらさらの液体やみそ汁、コーンスープ、シャーベットなど粘度の低いペースト状のものが適しています。咽頭がんの手術後の場合は、ちらばる液体は誤嚥しやすいので、誤嚥を予防するため、ヨーグルト、ゼリーなど粘度の高いペースト状のものがおすすめです。その後は、嚥下機能の状態に合わせて、煮たりゆでたりしたおかずをミキサーにかけたミキサー食、軟らかいおかずをきざんだキザミ食、軟らかめに仕上げた軟菜食、常食へと進めていきましょう」
最近では、嚥下障害の方向きの手軽な増粘剤や加工食品、スプーンなどの自助具が通販で購入できるようになっています(下コラム参照)。「食事の一部を手軽な市販品で補うのもよい方法ではないでしょうか」

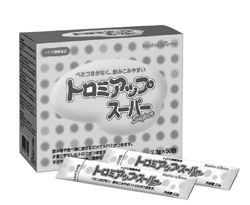
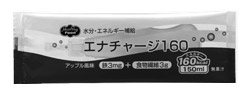

水分補給ゼリー。1本150mlで、エネルギー160KCalと、鉄、食物繊維を補給。105円

1袋でエネルギー130Kcalと、水分67g、微量栄養素を補給できるさわやかゼリー。りんご、桃、マスカットなども 各101円


