「眠れない」ときはこうする
不眠症の対策
以上の原因が単独でなく、いくつか重なって不眠症になるケースもあります。
これらの原因を解消するために、まず、次のA~Fのような対処法を実践してみましょう。簡単には原因を解決できないと思われるときも、「ダメモト」で試してみる価値はあります。
A 眠ろうと思わず、リラックス。

体を横にして、目を閉じて静かにしていれば、眠れなくても体の疲れはとれることがわかっています。「眠れない」ことばかり考えていると、ますます眠れなくなってしまうので、ことさら眠る必要はないのだ、と気持ちを楽にしてみましょう。
自分なりの入眠法を編み出すのも効果的。「羊が1匹、羊が2匹……と数えると、かえって目がさえてしまう」というAさんは、「ワン シープ、ツー シープと、息を吸ったり吐いたりしながら英語で唱えてみたら眠れるようになった」そうです。
B 「早起き早寝」で体内時計をリセット
毎日同じ時刻に、規則正しく睡眠がとれるようにすることも大切です。不規則な睡眠では、体内時計が進んだり遅れたりして、睡眠のリズムが狂ってしまいます。
「夜更かし、朝寝坊」の悪循環に陥ったら、リセットする日を決めて、前の晩どんなに遅く寝ても早起きし、1時間ほど屋外に出て外の光を浴び、昼だということを体に自覚させるのがポイント。昼寝せずにがまんして、夕食後、眠くなったらすぐに寝ます。翌日も早起きして朝日を浴び、その後は再び悪循環に陥らないように、規則正しく生活し、同じ時間帯に眠る「コア・タイム・スリープ」を保ちます。
「早寝早起き」ではなく、「早起き早寝」が大切です。
C コーヒー、お酒は控えめに
コーヒーやお茶に含まれるカフェインの覚醒効果は意外に長く続くもの。夜眠れなくて、昼間眠くなるからといって、午後にコーヒーをガブ飲みすると、夜寝付きが悪くなってしまいます。できれば、午後3時以降のコーヒー、寝る前の緑茶は避けるとよいでしょう。ビール1缶程度のごく少量のお酒は、寝付きをよくしますが、それ以上の量を飲むと、睡眠後半の質が悪くなり、途中で目が覚めたり、よく寝たという充足感が得られなかったり。また、アルコール依存症になると不眠がおきることも知られています。
睡眠薬よりアルコールのほうが安心とはいえません。お酒はほどほどに。
D 適度な運動をとりいれる
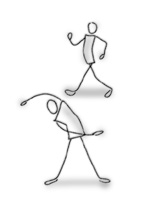
ウォーキング、軽いジョギング、ストレッチなどの軽い運動は、体に適度な疲れをもたらし、精神的なストレス発散につながるので、心地よい眠りを誘います。
ただし、寝る前の激しい運動は、交感神経の緊張を高めて逆効果。
E 寝室を快適に保ち、朝日を浴びる
ふとんやベッドパッド、枕を干し、清潔なカバーに替えると、それだけで気持ちよく床につけるものです。冷え症の方は入浴や足湯で末端の血行をよくしてベッドへ。
枕��に好きな香りのハーブを置いたり音楽を流したりするのも、気持ちをリラックスさせ、心地よい眠りにいざなう効果があります。真っ暗にしてしまうとかえって目がさえるという方は、スタンドの豆電球やフットライトをつけておいてもいいでしょう。
睡眠の質を改善するためには、いつも同じ安心できる場所で眠るのがよいとされていますが、「床に入ると目がさえる」という不安を伴う条件づけがされている人も多いようです。このような場合は、眠る場所を変えてみるのも一法です。寝起きが悪い方は、朝日があたるようにしておくと、自然に目が覚めるようになります。
F 食べ物にも一工夫
ビタミンB12には、光感受性を高めて体内時計を改善し、入眠を促進する効果がある、といわれています。また、レム睡眠の量やリズムを調節するために、卵黄などに含まれているレシチン(高コリン食)が有効であるという研究もあります。ビタミンB12が多く含まれるかきやあさり、しじみ、さんま、いわし、さけなどの魚介類、レシチンの豊富な卵や大豆を食事にとりいれるのもよいでしょう。
精神を安定させ、疲労を回復させるビタミンB1や、その吸収を高める硫化アリルを含むにんにく、神経を鎮め、精神不安を除く作用があるといわれる青じそなどもおすすめです。
ちなみに日本では認可されていませんが、アメリカではメラトニンという錠剤が、スーパーマーケットなどでビタミン剤と同様に売られています。これは、脳の松果体という場所で作られ、昼の間は分泌が少なく、夜になると増える「睡眠ホルモン」です。アメリカの研究では、入眠時刻の1時間前にメラトニンを1~3ミリグラム服用すると約40パーセントの人に睡眠作用が起こり、時差ボケや睡眠障害が解消されると報告されていますが、この効果に疑問をもつ人もいて、意見が分かれています。短期間の服用ならほとんど副作用の心配はありません。
これらの対処法を試してみても、不眠症が改善されないときは、かかりつけの医師か内科医、心療内科医、睡眠障害を専門とする病院などに相談してください。睡眠薬は正しい処方で正しく使えば、決してこわいものではなく、常習性にはなりません。


