副作用はこうして乗り切ろう!「抗がん薬治療中の倦怠感」
日記をつけてサイクルを知る
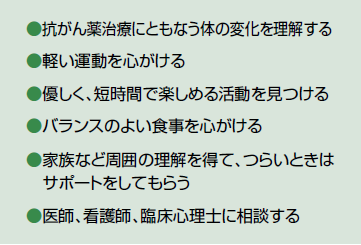
なかには、「吐き気や口内炎と比べたらまだマシ、倦怠感くらい我慢しなければ」と思っている患者さんもいます。ですが、倦怠感のために、外出どころか、家で寝て過ごすだけの生活をおくるのは、とてもつらいことですよね。倦怠感のために好きなことができなかったり、大切な人に会えないようであれば、それは「その人にとってよい治療」とは言えないかもしれません。「たかが倦怠感」、などと我慢するのではなく、まずはその程度や期間を医師や看護師に知らせて欲しいのです。
とはいえ、「だるさ」の程度は、なかなか伝えにくいかもしれません。ですから、日記をつけることをお勧めします。そのとき、ただ「食欲がない」「だるい」ではなく、「○日、○○が初めて食べられた」「○日、昨日より少しだけだるさがとれて、△△ができた」など、日にちごとに症状や食事量、前日との違いなど、気づいたことやできたことなどを細かく記録しましょう。
日記をつけることで、医療者に症状を正確に伝えやすくなりますし、倦怠感の経過を自分で把握しやすくなります。倦怠感が改善するタイミングや、できたことを書き留めることで、次回の抗がん薬後に、「あと○日経てば良くなる」「○日頃には△△ができるようになる」など、気持ちを前向きに保つことができると思います。ぜひ、日記をつけてみてください!
薬で対応する場合も
倦怠感でつらいときは、一時的にステロイドを使う場合があります。ただ、ステロイドは服用を止めたときの反動もあるので、飲み方に気をつけなければなりません。必ず、医師の指示に従ってください。
また、倦怠感の中でも「出かける気になれない」「何もする気になれない」といった心理的な要因が強ければ、抗うつ薬を処方する場合もあります。
1日の半分以上寝てすごしているなど、倦怠感の程度によっては、このような薬を使う以外に、抗がん薬の投与間隔を少し長くすることもあります。
とはいえ、倦怠感は副作用だけが原因ではないため、すべて解消することは難しいのが現状です。薬でコントロールしにくい副作用でもあるので、長い目でみてうまくつき合っていく方法を探りましょう。
外に出て、体を動かそう
倦怠感があるからといって、家でじっとして動かないのは、お勧めできません。倦怠感でつらい時期は割り切って無理をせず、少し和らいできたら、外出したり、体を動かしてみましょう。
ぜひお勧めしたいのが、翌日に疲れを残さない程度のウォーキングやストレッチ体操。体を大事にしすぎて、家から出ようと��ない患者さんが多いのですが、それはかえって逆効果。体力を落とすばかりではなく、ストレスをためてしまうこともあります。適度に体を動かしながら、体やココロの緊張をほぐしてみてはいかがでしょう? きっと、気分転換になると思いますし、気がついたらだるさを忘れていた……ということもありますよ!
思い切って体を動かしてみた患者さんは、皆さん「久しぶりに体を動かして、あ~疲れた」と言われるのですが、「でも、気持ちよかった」と続きます。
「ずっと倦怠感が続くと諦めていたのに、案外体を動かしてみたり、好きなことをやっているときは大丈夫だった」という成功体験の積み重ねは、抗がん薬治療の継続や、日常生活を自分らしく送る上での自信につながります。ただし、やり過ぎには気をつけて。心地良い疲れを感じる程度の運動を心掛けましょう。
ときどき患者さんから、「寝てばかりいないで少しは散歩に出かけたら……と家族に言われてつらい」と相談されることがあります。患者さんを大切に思うからこそ、心配してつい言いたくなるご家族の気持ち、本当によくわかります。ですが、「寝てばかりいないで起きなくちゃ」「食べないと栄養不足になるから」など、患者さんを励ますつもりでかけた言葉が、実は患者さんにとってプレッシャーになっていることも多いようです。同じ励ましの言葉でも、「一緒に歩いてみたいんだけど、どうかな?」「買い物につき合ってもらえると嬉しいな」など、ご家族の気持ちを伝えながら誘ってみると、ずいぶん違うと思います。
栄養補助食品をうまく活用しよう
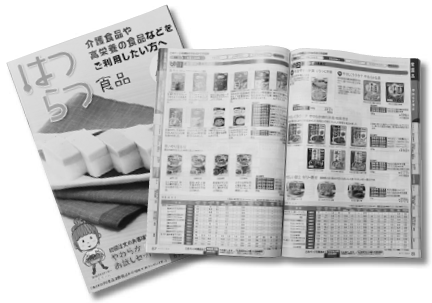
食事に関しては、基本的に、食べたいと思ったときに好きなものを好きなように食べることが栄養に繋がります。食欲がないときは、少量で高エネルギーの栄養補助食品を活用してみてはいかがでしょう。今は、少量で高カロリーの栄養補助食品もたくさんあります。
以前は、がん治療中は体力を消耗しないように無理せず横になりましょう、と体を大事にしすぎる傾向がありました。でも今は、がん治療を受けながら自分らしい生活を送っていこうという考え方に変わってきています。
好きな音楽を聴いたり、ウォーキングで体を動かすのもよいでしょう。太陽の光を浴びて、澄んだ空気をたくさん吸って、爽快感や心地よさを感じるのもよし。あなたらしければ、何でもよいのです。困ったら、1人で悩まず、いつでも私たち医療者にご相談下さい。一緒に考えていきましょう。


