オーストラリアがん瞑想セミナー体験記 “至福体験”を日本にも広めたい
厳密な菜食を中心に
1日3回の食事については、毎回「大変素晴らしい!」のひとこと。専属のコックと栄養士がいて、徹底した菜食主義。食材も新鮮で無農薬。油は亜麻仁、バターは使わない。作りたての野菜ジュース。パンは胚芽。デザートのケーキも手作りであった。お茶もハーブ中心に、コーヒーは駄目とのことで、タンポポで作られたコーヒー色の代用品。はちみつやレモンもよく使われていた。食事へのこだわりは素晴らしかった。セッションでも「食」に関するレクチャーがあり、それは日本の薬膳や食事療法、栄養の話と類似していた。どこの国でも「食」が大事なんだなあと感じた。
探し求めていたもの
10日間、参加者全員が寝食を共にし、おおいに歓談、交流することができた。初めて出会った者同士だったが、普段の人間関係より本当に密度の濃いものになった。合宿形式ならではと感じた。皆がこのプログラムに期待し、自己改善、自己成長したいと思っていた。そして、ガウラーの奇跡的な治癒をメディテーションで得られるものなら、自分もトライしてやるぞ! という意気込みの人が多かった。それもそのはず、約30万円余りを払っての参加である。もちろん私も。
私はがん患者だが、7年目の現在まで再発もないというラッキーな状態だ。が、今後の不安は抱えている。がん患者の生き方、心のもち方に、何かはっきりした教えが欲しかった。
2003年に乳がん患者会「わかば会」を立ちあげ、活動を始めて4年目になるが、多くの仲間から苦悩の声を聞くたびに、がん患者のセルフヘルプにつながるものを探し求めていた。遂に、このプログラムは私の期待に答えてくれた。みごとに自己の問題解決を導く内容であり、かつ人との交流の場として感動的なものだった。
学生時代の“学び”を追体験
もうひとつ、感動したことがある。それは、私の学生時代の学びにとても似た体験学習方式であったことだ。
私は1975年、愛知県名古屋市にある南山短大の人間関係学科に入学。ここで恩師リチャード・メリット教授のラボラトリー方式(体験学習)の授業を受けた。机のないところでのセッション。各自が主体的に意見をいえる授業展開。ガウラーが、参加者との対話を大事にしながらレクチャーを展開。体験学習的に話し合いつつ、テーマにそってまとめていくやり方が、メリット教授の授業の進め方と似ていることを発見して、とても興奮し感動した。
この体験を生かして
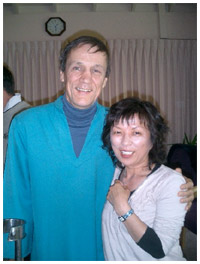
最終日。全員の前で自分の気持ちを発表し、拍手をもらった。1人ひとりと抱き合い、言葉を交わす。笑顔と感動の涙で完結し、本当に感動的だった。私も共に過ごした仲間との別れを惜しんだ。一期一会。異国で知り合った同じ病の友。みんなの幸福を祈り、いい経験と思い出のできたことに心から感謝した。
17日間日本を離れて、自分とゆっくり向き合う時間を作れたことは、満50歳を迎える私にとってとてもよいターニング・ポイントとなった。
そして、ガウラーのプログラムの内容を、日本のがん患者のセルフケアに役立てたいと強く決意した。ガウラーに私の気持ちを話したら、彼に「ぜひともやるべきだ」と大いに励まされた。「あなたのプロラムを真似ていいのか?」と聞くと、「もちろん。がん患者にとっていいことだし、セルフヘルプグループの役割が重要。僕の本を読みなさい」と言われ、英語版の彼の著書を2冊購入してきた。
いまやがんは社会の中で有病率が高く、多くの人が罹患後の生き方を模索している。そのことは患者会を通して実感している。そこで、学生時代の学びと、人間関係研究の課題と、ガウラーのプログラムの参加体験を生かして、私なりに創ったプログラムを実践したいと思うようになった。その第1歩として、がん患者のための「セルフケアと癒しのワーク」という1泊2日のプログラムを計画した。
必ずいい結果を生み、手ごたえを得られると信じている。そして、日本のあちこちのがん患者会で、このような試みがなされていくことを心から願っている。
堤寛さんのお話
(藤田保健衛生大学医学部第1病理学教授)

骨肉腫は、ティーンエイジャー(13~19歳)の膝にできる悪性腫瘍で、1970~80年代は致死性の高いことで悪名高い骨のがんでした。1970年代に私が医学部で習った骨肉腫は、以下のような病気でした。たとえ下肢切断術が行われても、5年生存率(治癒率)は5%で、大部分の患者は肺や骨への転移で短期間のうちに死亡する。5%生存する症例の多くは病理診断の誤りであろう。授業を担当した整形外科の教授は、丸山ワクチンで治癒したと称する症例を提示しつつ、そのように語ったと、明確に記憶しています。
そう、骨肉腫の病理診断はときに相当に難しいのです。米国の作家、アーサー・ヘイリー著の『最後の診断』を読まれたでしょうか。10代の看護師の膝にできた病変に対して、2人の病理医の診断がまっぷたつに分かれます。ベテランは骨肉腫、若手は骨折。結局、彼女は肺転移でなくなってしまう――。現在では、特別な化学療法が開発され、5年生存率が70%以上になっています。しかも、下肢切断をせずに人工関節をいれる患肢温存術が行われるのです。時代の変遷を実感させられる悪性疾患なのです。
膝にできる骨の腫瘍にはほかに「骨巨細胞腫」があります。これは20歳以上に生じ、ときに悪性骨巨細胞腫として転移することがあります。その名の通り、顕微鏡的に巨細胞が多数みられる骨腫瘍で、多くは良性です。たとえ肺転移しても進行は骨肉腫に比べてゆっくりのことが多い疾患です。しかし、悪性骨巨細胞腫が自然消褪することはありません。病理学的には、骨肉腫と巨細胞腫の鑑別診断が難しい場合は少なくありません。巨細胞が多い骨肉腫が経験されたり、巨細胞の少ない巨細胞腫(悪性例が多い)があるからです。
イアン・ガウラーの場合、骨肉腫の診断は臨床経過からみると全く矛盾しません。唯一非定型的な点は、年齢が高い点です。直感的には、悪性骨巨細胞腫の可能性を否定する必要があると思います。しかし、肺転移して血痰まで出した状態の患者が自然治癒することは通常考えられません。本当に奇跡的です。レポートには胸壁の写真が示され、明確な転移性腫瘤が撮影されています。骨転移の存在に疑う余地はありません。20歳以上の骨肉腫はまれですが、全くゼロではありません。
奇跡を起こすメディテーション。この世には、説明できない現象が多々あるようですね。
一般に、がんが自然治癒を生じることはありませんが、ごくまれに生じる自然治癒症例はいずれも、ほっておけば早晩死亡する悪性度のきわめて高い腫瘍のようです。胎盤細胞由来の絨毛がん、皮膚のメラニン産生細胞由来の悪性黒色腫、小児の副腎由来の神経芽細胞腫が有名です。ガウラーの場合もこの点で、例外ではないようです。上に述べたように、骨肉腫は悪性度がこの上なく高い疾患だからです。このような現象を科学的に解き明かせることができれば、患者さんにもたらされる福音は、間違いなくとても大きいものでしょう。
同じカテゴリーの最新記事
- 新しくWell-beingをテーマに 4つの活動を柱に日本骨髄腫患者の会の輪を広げたい
- 患者会E-BeC「第10回 乳房再建全国キャラバン」を広島で開催
- 「小児脳幹部グリオーマ」患者会 厚生労働大臣に直接陳情
- 「医師と患者で、一緒に考えよう」をテーマに BCネットワークが第6回乳がんタウンホールミーティングを開催
- 乳がん体験者ががん患者を支える 患者の悩み、必要なサポートとは?
- リンパ浮腫について知ろう、語ろう、「リンパカフェ」
- BCネットワークでは初めて、患者さんの経験談をメインに開催
- 患者さんや家族の気持ちが、少しでも楽になるように「まる」と名付ける
- 「小児脳幹部グリオーマ」に関する要望書を厚生労働大臣宛に提出


