「がんサポート」からの提言 自分の再発見、自分らしい生き方の追求を目指して、社会にムーブメントを
もはやがんは慢性疾患になった

ウェルネス・コミュニティーのプレジデント兼CEO。全米臨床試験サミット教育・コミュニケーション委員会の共同議長、全米心理社会がん協会(APOS)諮問委員会メンバーなど、各種がん医療コミュニティで指導的役割を担う
またこのシンポジウムにはウェルネス・コミュニティーのキム・シボーCEO(最高経営責任者)も参加し、「米国におけるがん患者のサポート・システム」と題した基調講演を行った。
それによるとアメリカでもがんと診断される人は増えているが、死亡者数は減っている。すべてのがんの5年生存率は63パーセントで、20年前にがんと診断されて現在も生存している人は約140万人。全米のがん生存者数は1000万人を超えているという。
こうしたことについてシボー氏は、もはや「がんは慢性疾患と考えていい」と指摘している。
がんが慢性疾患といえる状況になった理由としては、検診の重要性についての認識の向上、マンモグラフィや大腸内視鏡術などの検査利用が増加したこと、年齢ごとに受けられる検査についての国民の理解が進んだことなどをあげ、その結果として早期診断、早期発見が可能になったとしている。
また治療法に関しては、「外科手術、放射線治療、化学療法などの伝統的な治療法を超える動きが出てきた」として、こう述べている。
「行政、教育機関、研究機関、医療施設、各地のがんセンター、製薬業界、患者、そしてプロフェッショナル団体などとのパートナーシップが強化されました。米国がん研究所の医師は共通協議項目として、『われわれは国立がん研究所の内外、とくに医師、看護師、その他の医療専門家およびがん生存者のコミュニティとのパートナーシップを通して、積極的に共同活動するための新しい、より効果的な方法を探求する活動をしている』と書いています。1996年には米国立がん研究所が、がん生存者権事務局を設立しました。がんとともに、がんを通して、がんを超えて、回復機会とよく生きる機会への認識の向上のために、伝統的な医学的療法のみならず、医療、精神、心身の各方面からがんを扱う方法の探求をする総合的医療への取り組みが行われているのです」
もちろん「がん生存者のコミュニティ」のなかには、シボー氏がCEOを務めるウェルネス・コミュニティーも含まれている。
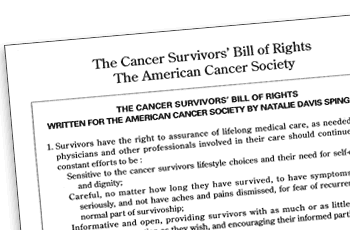
「ウェルネス・コミュニティーはすべてのがん患者の知る権利に応え、ともに活動していきます。患者は教育を受け、地位の向上がはかられ、ウェルネスのような団体を通して情報と資源を利用できれば、必ず希望を見出すことができるでしょう」
がん患者の側から発せられたこうした声や活動は次第���大きなうねりとなり、サバイバー運動としてアメリカに広がっていった。そして1988年には米国がん協会が「がん生存者の権利の章典」を発表。全米各地にがん患者や家族を支援するグループなどが組織され、支援するためのプログラムも数多くつくられるようになった。米国立がん研究所には、がん生存者対策局も新設された。
日本でも広がるウェルネスの活動
こうしたアメリカのムーブメントの影響も受け、日本でもサバイバー運動を起こそうという動きがある。日赤医療センターの外科部長や日赤看護大学教授などを歴任した医師の竹中文良さんが2001年に設立したジャパン・ウェルネスもそうした運動の一つだ。自身も大腸がんの経験者である竹中さんは、ウエルネス・コミュニティーのプログラムが日本でも有効であると考え、ジャパン・ウェルネスの設立に踏み切った。現在、ジャパン・ウェルネスでは、サポートグループの運営(同病者同士の小グループでの話し合い)、自律訓練法、瞑想法、坐禅会などの開催、講演会やセミナー、ホームページ、会報などによる医療情報の提供、複数の専門医によるセカンドオピニオン相談などを行っている。
前出の北里大学病院の近藤さんたちも、がんサバイバーの支援に取り組んでいる。
「患者が自らの権利を主張するサバイバーシップの運動は、まず患者が自分の病気や病状について知っていくことから始まります。だから告知の問題は避けて通れません。医師や看護師だけでなく、医療のさまざまな職種も、患者さんに病名や病状をどう伝えていくかということを考えないといけません。それと同時に告知後のサポートが重要です。サポートを行うグループや機会、あるいはペイシェント・エデュケーション(患者教育)の機会などを提供していくのが、私たちにできる支援のあり方だと考えています」(近藤さん)
医療の現場でも患者を支援する動きが
近藤さんたちのグループは、患者が自分の価値観で選択したことを主張していく力がこれから大事になっていくと考えている。そしてその力を高めていくためには問題解決力、情報探求力、自己決定力など6つの力が大切になるとし、情報探求力を支援するプログラムをつくって臨床に導入している。
「これまで医療者は患者さんの情報探求支援にあまり注目してきませんでした。でも情報を知りたいというニーズは明らかにありますし、またそこにも個別性があることがこれまでの私たちの研究で分かってきました。だから医療者は患者個別の情報に対するニーズに注目して支援していかなければいけない。そういう視点を臨床に導入して、時間はかかりますが少しずつパラダイムを変換させていきたいと思っています」
という近藤さんによれば、最近は日本でもがん専門病院などでは患者や家族を支えるサポートグループをつくる施設が増えてきているという。もちろん患者自らがそうしたグループをつくることも多い。北里大学病院でも、「つくしの会」という患者の自助グループがある。そうした患者会もサバイバー運動の一つと考えていいだろう。聖路加国際病院では、がんとの共生を支えるサポートプログラムが「がんとともにゆったり生きる会」として実用化されている。
20人に1人がサバイバーになる時代
ウェルネス・コミュニティーのゴラント氏がいう。
「アメリカでも以前はアクティブな患者はそんなにいませんでした。けれどもウェルネス・コミュニティーの活動によってアクティブな患者が広がり、サポートグループなどで患者同士が話し合うことによって孤独感が解消されQOLが上がることが患者自身にも分かってきました。日本でもウェルネスの組織ができたのですから、これからは日本人のがんに対する気持ちも変わり、いずれアメリカのようになっていくでしょう」
もちろんアメリカと日本では国民性も文化も違う。
「日本には日本のサバイバーの形があると思いますし、支援の仕方があるでしょう」
と、近藤さんはいう。
がんサバイバーには、治療中の人もいれば治療を終えて経過観察中の人もいるし、治療終了後5年以上がたって“治った”可能性が高い人もいる。そうしたがんサバイバーが日本には現在約298万人いるが、2015年にはその数が533万人に達すると見られている。国民の20人に1人が、がんサバイバーという時代が訪れることになる。
しかもこうしたサバイバーの前には幾多の困難が立ちはだかっている。患者が入院中であればまだ医療者をはじめ、さまざまな支えがある。ところが、退院し、サバイバーになると、そうした支えがなくなり、孤独感にさいなまれる。それどころか、社会のがんとがん患者に対する誤解や偏見、無理解と戦っていかなくてはならない。これは治療でがんと闘う以上に大変な困難を伴う。
ざっと整理するだけでもがんサバイバーにはこれだけの悩みや負担がある。身体的問題として疼痛、疼痛以外の症状、副作用、こころの問題として不安、恐怖、怒り、生きがい問題として疎外感、孤独感、残された日々、社会生活上の問題として家庭生活、収入、仕事、地位、医療技術者との関係として意思疎通、説明不足などだ。
しかも、家族も含めて周囲の人たちは、退院後の患者、サバイバーがこのような困難な問題を抱えていること自体を知らない。そこで、静岡がんセンター総長の山口健さんはこう指摘している。
「本人や家族の努力とともに、社会が『がん生存者』の悩みや負担を理解し、心の緩和ケアや医療相談のシステムを充実させていくことが大切である」(中日新聞2004年3月2日)
だから今こそ私たちは、がんサバイバーとしての生き方やがんサバイバーをいかに支えるかということを、まさに自分自身の問題として真剣に考えなければいけないのである。


