- ホーム >
- 連載 >
- 中医師・今中健二のがんを生きる知恵
第5回 「カゼかな?」と思ったらすべきこと
汗をかいて邪を外へ出す
邪を速やかに体から追い出したいとき、発汗という方法もあります。汗と一緒にウイルスなどの邪も出ていってもらおうというわけです。
葛根湯(かっこんとう)や麻黄湯(まおうとう)という漢方薬を聞いたことがある方も多いと思いますが、これらは体を内側から温めて発汗させる作用があるので、カゼのひきはじめに推奨されます。ただし、飲むタイミングが重要。体を温めることを手助けする漢方薬ですから〝汗をかきやすい状態〟を作り出してから服用します。
肌寒い夜、帰宅して冷えた体のまま服用しても効果は期待できません。帰宅後、上着を脱がず、まず暖房をつけて部屋を暖め、体が温まってきたところで漢方薬を熱いお湯で溶いて少しずつ飲む。もっと言うと、熱いうどんでも食べて体を内側から温めた状態で服用したら、なお発汗しやすくなりますね。「漢方は食前に」などと言われることもありますが、この場合に大切なのは食前か食後かではなく〝汗をかきやすい状態〟です。
ただ、発汗は邪を追い出してくれる一方、体力そのものを消耗し体の中の気も出ていってしまうので、体力がある程度ある人に向いています。抗がん薬治療中や放射線治療中で体力が低下しているときは避けましょう。
カゼ症状を緩和するマッサージ
カゼの諸症状が邪を追い出すための体の反応と知っても、やり過ごすのはつらいですよね。そこで、これらの症状を緩和するマッサージを2つ、紹介したいと思います。
カゼの引き始めに肩や首がこわばって痛むことがあります。そんなときは、U字型のマッサージ器具を使って、コリをほぐしてあげるのも1つの方法。
この器具には使い方のコツがあります。まず、U字型の突起部分が肩や首の凝っている部分、つまり押すと気持ちいい場所に当たるように、Uの角度を調節します。角度が決まったら、少し下を向いた状態で、器具を目の奥に向かって引っ張り上げるイメージでマッサージします。決して、U字で押し挟むマッサージはしないよう気をつけてください。肩凝り、首筋の痛み、そして鼻水や鼻づまりの緩和も期待できます(図3)。

もう1つ、手三里(てさんり)というツボを揉むのもおすすめです。腕の下から指を入れて、親指以外の4本の指でゴリゴリしていると気持ちいい場所が手三里。とても見つけやすいツボなので、ぜひ試してください。肩凝りはもちろん、頭痛も和らげてくれる嬉しいツボです。
ただ、これらのマッサージはカゼを治すのではなく、あくまでも症状の緩和と予防です。イメージとしては、ウイルスなどの邪と体の気(元気)が闘っているところに分け入って、「まあまあ、そんなに喧嘩しなさんな」と仲裁するような感じでしょうか。
カゼを寄せつけない体に
体の中を巡る気血の流れが混乱した状態��「カゼ」。なかでも「カゼ」を引き起こす代表格が風邪(ふうじゃ)で、六邪のボス的な存在です。北風が寒気を、台風が湿気を一緒に運んでくるように、風邪は皮膚や粘膜の扉を開け放って、湿った空気(湿邪)も熱い空気(熱邪)も冷たい空気(寒邪)も何もかも体の中に呼び入れてしまうという特性を持ちます。そして、それらが体の中で邪になるのです。
台風が近づいたら雨戸を閉めるように、体も風邪から身を守るために皮膚の表面を固めてこわばらせ、邪をそれ以上、中に入れないようにします(肩凝り・首凝り)。寒邪が入ってきたら内側から温めて冷えないようにし(発熱)、同時に入ってしまったゴミ(邪)をとにかく外へ掃き出そうとします(鼻水、咳、吹き出物など)。
そんなとき私たちがすべきは、咳や鼻水を無理やり止めることではなく、出したいものは吐き出させること。そして入ってきた邪を速やかに追い出せる体を作ることでしょう。夜9時にベッドに入る、発熱して食欲がないときは無理に食べない。これらは邪に早く体から出ていってもらうための知恵です。体調の異変を感じたときはもちろん、普段からこうした生活を心がけて、カゼを寄せつけない体作りをしていきましょう。(次号へ続く)
著書紹介
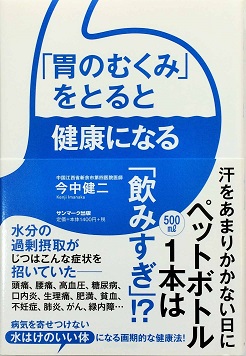
「胃のむくみ」をとると健康になる
今中健二著 サンマーク出版 1,400円(本体)
「水は飲むほど体にいい」に警鐘を鳴らす1冊。過剰な水分摂取が胃をむくませ、そのむくみが体中に伝わって不調が現われるのだという。その症状は、頭痛、腰痛、高血圧、糖尿病、生理痛、肥満、貧血、不妊症、肺炎、がん、緑内障など多岐に渡る。中国伝統医学のプロフェッショナルが教える究極の健康法
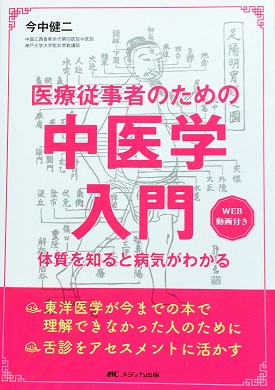
医療従事者のための中医学入門
今中健二著 メディカ出版 3,000円(本体)
整体観、陰陽五行学説、弁証理論など、複雑に思える中医学の概念を分かりやすく明快に解説。医療従事者はもちろん、家族の健康を気遣うお母さんたちにも知ってほしい中医学の知識を伝える。舌や顔色でわかる体質や対処法、それに合わせた食事や温度調整など、実際のケアに役立つ知識をまとめた1冊


