- ホーム >
- 連載 >
- 中医師・今中健二のがんを生きる知恵
第14回 子宮の異変は、胃や肝臓の不調が原因かも
むくみは、菌が培養しやすい状態
子宮がんの発生には、腎臓・膀胱の経絡が担う水分調節が大きく影響しています。
子宮を通る腎臓・膀胱の経絡は、前述のように子宮内の余分な水分を捨て、水分調節をしています。この調節がうまくできなくなると、水分が溜まってむくみになるわけですが、むくみが起こるのは常に下部。つまり、子宮頸部に溜まることになります。
子宮頸部に発生したむくみが、子宮頸部の異形成と呼ばれる状態。この状態がさらに進むと、異形成から悪性化し、子宮頸がんになっていくことがあるのです。
子宮頸がんというとヒトパピローマウイルス(HPV)という原因ウイルスが判明していますが、HPVに感染したからといってすべての女性が子宮頸がんを発症するわけではありません。むしろ、発症するほうが稀(まれ)。一説によると、HPV感染から前がん病変に至るのは1割弱、さらに浸潤がんにまで移行するのは1%ほどと言われています。
つまり、HPVに感染したら子宮頸がんになるのではなく、HPVにとって居心地良い子宮環境を維持してしまうと、HPV感染が子宮頸がんへ移行してしまうことがある、と捉えましょう。
HPVにとって居心地のよい環境こそが、子宮頸部のむくみです。水分でふやけてむくんだ状態は、HPVだけでなく、カンジダやヘルペスといった、あるゆる菌を培養しやすい状態。HPVに感染し、かつ、菌が培養されやすい子宮環境を持続させてしまうと、子宮がんへ移行するということです。
子宮内の水分を捨ててくれる腎臓・膀胱の経絡が、子宮がん発生に大きく関与していることを理解いただけたと思います。腎臓・膀胱の経絡を整えて、水分調節をしっかり行える体を作ることこそが、何よりの子宮がん対策になるのです。
子宮の異変は、3つの経絡いずれかの不調から
肝臓の経絡に不調が生じると、子宮内膜を作り出す材料そのものが不足します。内膜が十分に作られないと経血が産生されず、月経に影響を及ぼすわけですが、ここで大切なことは、子宮が肝臓の経絡に影響を受けるということは、子宮以前に、肝臓に異変が起きているということです。
このことは、血の通り道である子宮の宿命。子宮の不調は、子宮の問題というより、子宮に注ぎ込む3つの経絡のいずれか、つまり胃、腎臓・膀胱、肝臓のいずれかに異変があると考えるべきでしょう。
例えば、肝臓の経絡から来ている場合は、GOTやGTPといった肝臓関連の数値の異変はもちろん、コレステロール値や血糖値が高いといった状態が既にあることが多く、肝臓を発端として、子宮にも影響が及んでいると考えられます。
つまり、子宮そのものに何かが起きたと考えるより、まずは、子宮に流れ込んでいる3本の経絡のどれかに異変が起きている。そうした視点を持って、子宮の不調に向き合っていくことが、実は大切だと考えます。その視点から、最後に、子宮がんの予防法についてお話したいと思います。
食べ過ぎない、むくませない、疲労を溜めない
まず、子宮に異変があったときは、子宮を通る3本の経絡のうち、どの臓腑から影響を受けているかを考えてみましょう。
胃が詰まる感じや逆流性食道炎があったりするなら胃、先述の肝臓関連の数値が高い場合は肝臓、コレステロール値や血糖値の場合は肝臓も胃も考えられます。クレアチニンなど腎臓の働きに関する数値の異変は腎臓・膀胱でしょう。
これらは自分で明確に特定することはできませんが、わかりやすい別の症状がある場合は、そこから子宮に影響が及んでいる可能性があることを覚えているだけでも手助けになると思います。
繰り返しますが、子宮を通っている経絡は、胃と腎臓・膀胱と肝臓の3本。つまり、これらの臓器をいたわることが、子宮がん対策であり、予防策になるのです。
胃を労わるには、食べ過ぎない。腎臓・膀胱を労わるには、むくませない。肝臓を労わるならば、疲労を溜めない。以上です。
腹八分目、休息をとる。そして、水分を摂り過ぎないよう、さらに体内の水分を上へあげることを意識して暮らすこと。これが子宮がんの対策のすべてと言っても過言ではないでしょう。
中でも、むくませないことは、意識しないと続けられません。水分は必ず下に溜まり、むくみになります。ですから、水分を上にあげることのできる体を目指しましょう。それには、やはりウォーキング。太陽の光を浴びながらのウォーキングを、ぜひ習慣にして日々を過ごしてみてください。
著書紹介
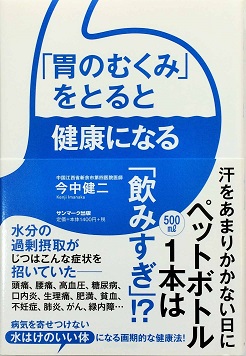
「胃のむくみ」をとると健康になる
今中健二著 サンマーク出版 1,400円(本体)
「水は飲むほど体にいい」に警鐘を鳴らす1冊。過剰な水分摂取が胃をむくませ、そのむくみが体中に伝わって不調が現われるのだという。その症状は、頭痛、腰痛、高血圧、糖尿病、生理痛、肥満、貧血、不妊症、肺炎、がん、緑内障など多岐に渡る。中国伝統医学のプロフェッショナルが教える究極の健康法
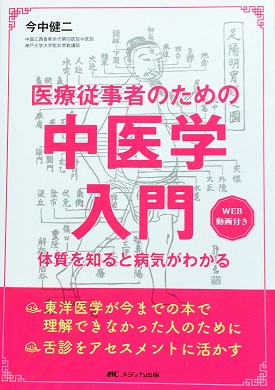
医療従事者のための中医学入門
今中健二著 メディカ出版 3,000円(本体)
整体観、陰陽五行学説、弁証理論など、複雑に思える中医学の概念を分かりやすく明快に解説。医療従事者はもちろん、家族の健康を気遣うお母さんたちにも知ってほしい中医学の知識を伝える。舌や顔色でわかる体質や対処法、それに合わせた食事や温度調整など、実際のケアに役立つ知識をまとめた1冊


