鎌田實の「がんばらない&あきらめない」対談 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター病院長・田中丈夫さん VS 「がんばらない」の医師 鎌田實
その人だけにしかできない大切な絵本
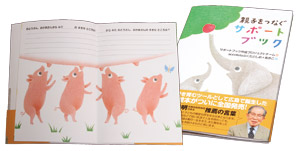
鎌田 「サポートブック」には、お父さん、お母さんが、お互いにどういう思いでいるのかを書く部分がありますよね。お互いにそういうことを真剣に書いていると、仲が悪かった夫婦も離縁しないで済むんじゃないですか(笑)。
田中 あり得ますね、はい。仲が良かった時代に気持ちが戻っていきますから。長いこと小児科医をやってきて、子どもさんの病気で離婚に至るケースをいくつも見ています。とくに障害児を持つ家庭に多いです。
鎌田 障害児を持った夫婦ほど協力し合わなきゃいけないんですけれどね。離婚に至った場合、お母さんが引き取るケースが多いですか。
田中 そうですね。そうしたケースを多く見てきた小児科医として思うことは、たとえば小児がんの子どもさんの治療を行う場合、治療を始める前に、おじいちゃん、おばあちゃんにも同席してもらって、病気や治療の説明をすることが大事だということです。両親が病気の子どもの看病にがんばればがんばるほど、他の兄弟が取り残されますし、両親も100パーセント関われるわけではありません。周りが分業することが必要で、人が多ければ多いほどいいのです。ですから、私は白血病の子どもさんを治療する前に、おじいちゃん、おばあちゃんにも同席してもらって説明するようにしています。
鎌田 私たちが乳がんの患者さんを治療する場合、一般的にご主人には説明しますが、子どもさんやおじいちゃん、おばあちゃんは呼ばないですよね。しかし、おじいちゃん、おばあちゃんに説明しておいたほうが、サポート態勢が強くなるような気はしますね。
田中 がんが見つかった最初の時点から、おじいちゃん、おばあちゃんを呼んで説明するのがいいかどうかはともかくとしても、治療方法が固まった段階からは、そこまで巻き込んだほうがいいと思います。
鎌田 いずれにしても、「サポートブック」には、その家族が自分たちにし���作れないという魅力がありますね。
田中 後で振り返ると、その人だけにしかできない大切な絵本になりますね。がん患者さんに限らず、いろんなシチュエーションで利用していただけると思います。広島県から「第2の母子手帳にしたい」という話がありました。お母さんが子育ての中で感じた思いを書いておけば、子どもさんが大きくなったとき、それを見れば、お父さん、お母さんの思いがわかると思います。それで私の病院や知り合いの看護師さんの中に、出産祝いとして「サポートブック」を渡すという人が増えましたね。1冊500円というワンコインの安い贈り物ですが、あとでそれ以上の価値が出てくるわけです。
「遺書を書くのか」と拒否する患者さんも
鎌田 若いお母さんが妊娠から出産、産後の子育ての過程で、マタニティー・ブルーといってウツになっていくケースがありますよね。赤ちゃんを産んだときの感動があるはずなのに、育てる過程で重荷に感じて、ぺしゃんこになってしまう。もし、妊娠したときから生まれてくる子に対する思いなどを、「サポートブック」に書いていたら、育児の苦しいときにも、それを読み返せば、感動を新たにして、ぺしゃんこにならずに立ち直ることができる。しかし、中には「サポートブック」に拒否反応を示す患者さんや家族もいらっしゃるのではないですか。
田中 「何か遺書を書くのか」というとらえ方をする人がいらっしゃいます。医療の現場でお渡しするのは、ちょっと難しい面がありますね。患者さんに「自分は治る」という思いが強い場合、「私は要りません」と言われるケースがあります。逆に、病気に不安を持っていらっしゃる患者さんの場合、渡し方を間違えると、「遺書を書くのか」ということにもなりかねません。
鎌田 たしかに渡し方が難しいという面はありますね。「サポートブック」が書店に普通に置かれるようになり、患者さんが自発的に購入して書くようになればいいと思いますね。また、広島県が第2の母子手帳にするという話がありましたが、みんなが「サポートブック」を持って、書くようになればいいですね。
今ふと思ったんですが、がんになった人全員に、さりげなく渡しちゃったらどうでしょう。東大病院で放射線医療を担当されている中川恵一先生が、中学生からがん教育をやるべきだと、今、がん教育用のDVDを制作されています。一家でひとり、がんになっても不思議ではない時代ですから、中学生にがん教育をすることは必要だと思いますが、同時に「サポートブック」による教育を並行してやったらいい。いのちのありがたさ、家族の絆の大切さを教えることができると思います。
田中 私が診療していて感じるのは、今の教育の中で、いのち、健康の大切さがうまく伝えられていないのではないかということです。そこで私は広島大学教育学部の非常勤講師として、将来学校の先生になる学生さんへ子どもの病気や成長のすごさについて毎年講義をさせていただいています。また、出前講座と称して積極的に地域へ出かけ、子育てをしている若いお母さん方を対象に、子育てのおもしろさ、子どもの楽しさなどをお話しています。
「サポートブック」は小学校教育でも使える
鎌田 中学生に対するがん教育、学校の先生方に対する講義、地域のお母さん方に対する出前講座、何でもいいわけですが、多様な取り組みをしながら、子どもを支える時代ですよね。広島から生まれた「サポートブック」も、全国展開をしてもっと広がりを持てればいいですね。
田中 先日も小学校の校長先生と話したんですが、「サポートブック」は小学校の教育にも使えそうだということでした。私も各地に出かけて、「サポートブック」の良さや使い方を積極的に伝えていきたいと思っています。
鎌田 がんはもはや国民病といってもよく、がん医療は病院の中だけでなく、家族、社会がサポートし合いながら国全体で取り組むべきです。そのとき「サポートブック」は大きな意味を持ってくるはずです。
田中 私は入院している患者さんに、「できるだけお家に帰ってね」と、よく言うんです。そのほうが患者さんははるかに元気になれるのです。病院という広い空間に長期間いることは、患者さんにとってはものすごいストレスです。白血病の治療をする子どもさんの場合、入院は半年をメドに考えています。最近、白血病は8割方、治るようになっています。ですから、「半年はがんばろうよ」と、最初に言っています。病院というところは異常空間ですから、早く家庭に帰ることが望ましいのですが、それには家族のサポートが欠かせません。やはり「サポートブック」が必要とされるのです。
小児科医をやってきて良かったと思うこと
鎌田 私は、小児科医の田中さんが「サポートブック」の普及に取り組んでいらっしゃるという点に、とても共感を覚えるのですが、田中さんが医師をめざされたのは?
田中 父が技術系の公務員で、もともと私は理系の人間でした。医師になったのは、小学校6年のときに生きるか死ぬかの大病をしたのがきっかけです。入院していたとき、担当の先生が朝晩、必ず私のベッドをのぞいてくれました。そのことで母はすごく安心したと言っていましたが、私も子ども心にとてもうれしかったのです。そして、高校を卒業するころ、あの先生のような医師になりたいと思うようになっていたのです。
鎌田 医師が患者さんと毎日コミュニケーションを取ることは大切なことですよね。
田中 小児科病棟を受け持っていたときには毎日忙しくても朝、夕2回患者さんの顔だけは見るように努めていました。それを続けることで、患者さんのお母さんの信頼が絶大なものになります。私の母の場合と同じですね。そういう意味では、私は子どものとき大病をして、本当にいい先生に巡り会えたと感謝しています。西野泰生先生という人で、89歳の今もお元気です。
鎌田 小児科医を選ばれたのはいつですか?
田中 私が広島大学医学部の学生当時は、学園紛争で大学が荒れている時代でした。その時代に見学に行った病院で、第2の恩師とも言うべき井田憲明先生に出会い、大学には残らずに、井田先生のいらっしゃる病院で小児科医としてスタートしたわけです。その病院は一般病院でしたから、一般の病気全般を診ることができたことは、私にとってとても勉強になりました。その後、いったん大学病院へ戻ったあと、アメリカの大学(UCLA)の血液腫瘍部門の研究室に飛び込んで、遺伝子治療の研究や、ライフワークとなったがん遺伝子の研究に携わり、帰国後、小児がんの臨床研究もやって、今日の立場に至ったわけです。
「サポートブック」に懸ける小児科医としての思い

鎌田 お話をうかがっていると、田中さんは幸せな医師人生を歩んでこられたと思います。最先端のがん医療の研究に携わってこられた田中さんが、現在は小児科医としての仕事と並行して、最先端医療とは対極にある、こころの問題を扱う「サポートブック」の普及にも全力投球されている(笑)。
田中 最近思うことは、医学は病気を治そうという方向に向いているのに対して、医療は治すことと、治らない人にどう対応するかがフィフティ・フィフティではないかということです。医学から医療の要素が抜け落ちてしまうと、医学は冷たいものになってしまいますし、医療から医学の要素が抜け落ちてしまうと、治せる病気も治せなくなってしまいます。医学と医療のほどよい調和が大切です。私が小児科をやっていて良かったと思うのは、小児科には病院の診療科のすべての要素があるということです。そして、患者さんであるお子さんの10年先、20年先の幸せを考えながら治療します。それは大人の患者さんを治療する場合にはないことです。私は小児科医を長いことやってきたから、「サポートブック」にのめり込んでいるのかもしれませんね(笑)。
鎌田 「サポートブック」のますますの広がりを期待し、私もサポーターをやっていきたいと思います。
(構成/江口敏)
同じカテゴリーの最新記事
- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)
- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)
- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)
- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている
- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)
- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)


