鎌田實の「がんばらない&あきらめない」対談 東京大学社会科学研究所教授・玄田有史さん VS 「がんばらない」の医師 鎌田實
希望が叶わなくても紡いでいく過程が大事

鎌田 玄田さんが『希望学』(中公新書ラクレ)で書かれていますが、希望を持つことによってどんな結果がもたらされるかということより、希望があることによって生き方が変わるということが大事ですよね。
玄田 希望学をやっていて、いろんなことを学びましたが、あるとき、希望と対になる概念とは何だろうと考えてみました。まず安心という概念を考えました。安心とは、ある程度見通しが立っている、メドが立っている、結果が伴なっている、という状態でないと、感じにくい。
一方、希望は、必ずしも結果が伴わなくても、結果を求めて模索するプロセスこそが希望になる。希望と幸福の関係も似ています。いまが幸せなら、人はそれを維持したいと思います。しかし、希望は、いまより明日を少しでも良くしたい、いまの苦しみを明日は少しでもやわらげたい、というように良い方向に変化を求めるものです。
希望と幸福は、両方とも人生に必要なものですが、その中身は微妙に違います。
鎌田 幸福は固定した状態で、希望はそこへ行くプロセスでしょうね。がん患者さんが大きな不安の中にも、少しでも良くなるという希望を持てれば、不安な状態から変わっていくことができますよね。
玄田 断定的には言えませんが、変わると思います。希望は叶えることにも意義がありますが、釜石の78歳の男性が言われたように、希望を育てていく、紡いでいくこと自体に意義があるのだと思います。たとえば、男の子に「将来何になりたい」と訊くと、「野球選手になりたい」と答えたとします。その場合、野球選手になろうとして、希望を紡いでいくプロセスが大事なのです。実際に野球選手になれなくて、野球の好きな芝生職人になったとしても、そんな新しい希望を探して行動することに、意味があるのです。
鬱々と日々を送るより希望を持って生きる
鎌田 希望どおりにならなくてもいい!
玄田 希望には物語性があります。希望を紡いでいけば、意味のある人生につながっていきます。希望は人生にとって欠かせないものです。希望を紡ぐことがなければ、人生の物語は描けないと思います。
鎌田 がん患者さんも、再発にヒヤヒヤして鬱々とした日々を送るより、希望を持って生きることが必要ですね。
玄田 周りとのかかわりの中で、希望が持てればいいと思います。
鎌田 希望は性格とか、経済力はあまり関係がなくて、子どものときから夢を持っているかどうかが大事だということですね。
玄田 とくに、子どものときに周りにどういう大人がいたかも、大事なようです。経済的に豊かな家庭に育ったから希望が持てるということではなく、家族から信頼されて育ったとか、見守られて育ったという記憶を持っている人のほう��、希望を持てるようです。
鎌田 親は子どもに期待していいということですか。
玄田 そうですね。親の期待が大きすぎてつぶれる子どもが多いといわれますが、私はむしろ、親に期待されることなく育った子どもたちのほうが心配です。子どもたちの地域の職場体験に関わっている人の話では、子どもたちは不安な気持ちで職場体験に参加していますから、子どもたちが良いことをしたときには、目で賞めてやるのだそうです。そうすると、子どもたちは期待されていることを感じ、自信を持つというんです。
鎌田 大人でも同じですよね。医師と患者さんの関係でも、医師が自分が手術をした患者さんには治ってもらいたいわけです。その思いを目で患者さんに伝えることは大事だと思います。
玄田 目で賞めるというのは、本当に大人ならではの所作だと思いますね。経験がないとできません。
ケチなやつになるな
ケチは良い学者になれない
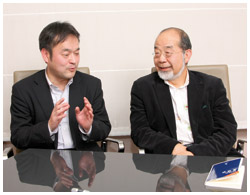
鎌田 大人にとっても、つらい状態にあるときは希望が大事ですが、どうすれば希望が持てるようになりますか。
玄田 希望学をやっている中で、「できるだけ損をしたくないですか」というアンケートをとったことがあります。損をしたくない人と、ときには損をしてもかまわないという人の比率は、ほぼ半々でした。希望を持って何かに取り組んでいる人は、明らかに後者のタイプが多いんです。
鎌田 あーあ、そう!
玄田 そのとき、私が大学の教師になったころ、当時の学部長がお酒を飲むたびに、「いいか、玄田君。ケチなやつは決して良い学者にはなれない。絶対ケチなやつにはなるな」と言っていたことを思い出しました。最初はよく意味がわからず、「割り勘で飲んでいるんですけどなあ……」なんて思っていたのですが(笑)、何が損で、何が得かなんてやってみないとわからない。目先の損得だけを考えて研究していたのでは、新たな可能性は生まれないんだということが、後になってわかったんです。
鎌田 私にも心当たりがあります。実は私は生みの親に育てられていないのです。私が1歳のときに拾ってくれ育ててくれた父親はタクシー運転手で、母親は重い心臓病をかかえていました。決して恵まれていたわけではなく、むしろ貧乏な家庭でしたが、困難を横に置いて、私を拾い育ててくれた。父がそれで得をしたかどうかは、私がどれだけ親孝行をしたかによるわけですが、少なくとも親は損得勘定を抜きにして私を育ててくれたわけです。だから私も、イラクの子どもたちを救済する運動に参加しているのです。みんなが自分のためだけでなく、他人のためになることをしたほうが、希望が見えてきますよね。
玄田 人生で苦しいことを経験された人ほど、人生にムダはなかったと言われますね。
同じカテゴリーの最新記事
- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)
- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)
- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)
- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている
- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)
- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)


