鎌田實の「がんばらない&あきらめない」対談 国立がんセンター総長・廣橋説雄さん VS 「がんばらない」の医師 鎌田實
均てん化の推進とは裏腹にかえって医療格差が拡大

鎌田 がん対策推進基本計画の1つの柱は、がん医療の均てん化だと思います。これはがんセンターや大学病院で行われている最先端のがん治療を、地方の病院でも受けられるようにするということです。現状はかえって医療格差、地域格差が広がっているようです。
廣橋 がん対策基本法が原因で医療格差、地域格差が広がったというより、いままで見えていなかった格差が明確に見えてきた、ということだと思います。それは出発点であり、それを見て、行政も医療側も格差を直すよう努力していくことが大事だと思いますね。地域によっては非常に優れた取り組みをしているところもありますから、それを参考にし、住民や患者さんの声も聴きながら、格差是正に取り組んでいくということです。
鎌田 格差がはっきり見えてきたから、いまはそれを改善していくプロセスだということですね。格差の問題のほかに、地域拠点病院の問題があります。本当に充実した拠点病院が少ないという声があります。また、拠点病院の下に位置づけられている、地域のナンバー2、ナンバー3の病院が弱体化しているという感じもします。
廣橋 均てん化については、拠点病院の全国レベルでの均てん化もありますし、その先の地域での均てん化も大事です。現在、がん診療連携拠点病院を中心に均てん化が進められています。5大がんの地域連携クリティカルパスの作成とか、地域の医療機関が参加する合同カンファレンスをやるとか、患者さんの受け入れ、あるいは紹介とか、専門的治療の相談に乗るとか、そういったことが連携拠点病院の指定要件になっています。それが徐々に機能するようになって、地域レベルの均てん化に結びついていけばと期待しています。
鎌田 地域連携クリティカルパスというのは、一般の患者さんや家族には難しくて、イメージできないのではないですか。
廣橋 これは患者さんの代表の方のご意見もあって、基本計画の中に盛り込まれたものです。このクリティカルパスとは、患者さんが受ける検査や手術、治療の予定、手術後のリハビリなどを、わかりやすい絵などを使って表にまとめた治療計画書のことです。ご自身の治療過程がわかるため、患者さんにとっても自己管理がしやすく、自ら積極的に治療に参加する気持ちになります。
また、病院が替わっても、医師による治療方針のばらつきや、看護師による説明のばらつきがなくなりますし、診療情報を医療スタッフが共有できるため、患者さんやスタッフ間のコミュニケーションがとりやすくなり、治療が円滑に進むメリットがあります。このクリティカルパスを機能させるためには、地域の病院の連携を密接にし��ければならず、それによって均てん化も進むというわけです。
拠点病院への集中化によって疲弊する医師や看護師たち
鎌田 ただ、拠点病院をどんなに充実させても、がんで亡くなっていく30万人の人の看取りはできません。ですから、拠点病院の下の病院を充実しなければならないと思います。しかし、厚生労働省がそこまで配慮しているとは思えません。
廣橋 拠点病院を必死に支えていることで精一杯、というのが現実でしょうね。
鎌田 拠点病院に集中化するのは間違いだとは思いませんが、現状は集中化することによって、拠点病院の医師や看護師たちが疲れ切って、治療が粗雑になっている面も出ているようです。
廣橋 集中するだけで、役割分担が進まないと、なかなか大変でしょうね。
鎌田 国立がん研究センターの場合、患者さんをどんどん手術して、手術後にその患者さんを引き受けてもらう病院をいくつも持っているわけですか。
廣橋 病病連携(病院と病院の連携)、病診連携(病院と診療所の連携)のためにカンファレンスを開いたりして、努力しています。その方向に進んでいることは間違いありません。
鎌田 がんの場合、患者さんの側に大病院志向があり、大きな病院に集中する傾向がありますね。ですから、有名な大病院はパンク寸前です。通常の治療は地域の中小の病院や診療所で行うようにすべきですね。その役割分担をするために、病病連携、病診連携が推進されているわけですが、まだ緒についたばかりという感じでしょうか。
廣橋 やっとその方向に向けて、歯車が動き始めたという段階でしょうね。
マンパワー不足がさまざまな問題の根底にある
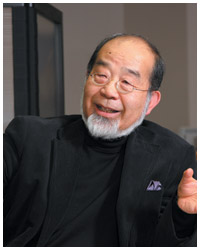
鎌田 私はいま「週刊朝日」で、「言葉で治療する」というテーマで短期集中連載をしています。その中で読者に、医師の言葉で傷つけられたことはないかとか、逆に医師の言葉に勇気をもらったり、元気をもらったりしたことはないか、といった呼びかけをしたら、ものすごい数の手紙やメールが来ました。しかも、その7割が医師の言葉に傷つけられたというものでした。この背後には、がん治療の集中化が進むにつれて、医療側が疲れ切っている状況があるのではないかと思うわけです。
廣橋 患者さんが集中することによって、そういう事態が起きているという面はあるのかも知れません。がん対策推進基本計画には、患者さん視点に立つことの重要性が盛り込まれています。患者さんの気持ちを考えていないわけではなく、まだ不十分だということでしょうね。
鎌田 地方のがん拠点病院の中には、設備、人材面で不十分な病院もあるようです。その理想と現実のギャップをどう埋めていけばいいのでしょうか。
廣橋 拠点病院はきちんとした基準を設け、評価をして選ばれています。また、一定期間をおいて見直しもすることになっています。予算の範囲内で国や地方から拠点病院に対して財政的な支援も行われていますし、診療報酬面でも配慮されています。しかし、やはりマンパワーが不足しているという問題が根底にあり、さまざまな問題点が出てきていることは否めません。
ただ、せっかく拠点病院の仕組みを作ったわけですから、きちんと育てていかなければならないと考えています。そのためには、拠点病院が何もかも抱え込んでしまうのではなく、地域の病院と役割分担を進める必要があります。拠点病院同士の役割分担も必要だと思います。
役割分担を明確にし拠点病院制度を機能させる
鎌田 拠点病院のもう1つの問題は、緩和医療を充実させなくてはならないのに、拠点病院の指定を受けるために、形だけの緩和医療チームを作っただけで、実質的に緩和医療を行っていない病院があることです。
私の病院には全国からがん難民となりかけた患者さんが来ますが、みんな拠点病院から流れてきた人たちです。この患者さんはなぜ心のケアが受けられずに、こんな遠くまで来なければならないのか。拠点病院はこういう患者さんたちを救っていない。経営の観点から、拠点病院の資格を取っただけで、拠点病院の役割を果たしていないようです。
廣橋 拠点病院の見直しのときに、そういう点をきちっとチェックできるような仕組みを作ることが大事だと思いますね。
鎌田 年間30万人以上の人ががんで亡くなるわけですが、その人たちにきちんとした緩和ケアが行われていない。拠点病院だけでなく、地域の2番手、3番手の病院に緩和ケアを分担するよう、しっかり意識づけをし、お金も流してやる必要がある。拠点病院と2番手、3番手の病院が連携してがん医療に当たれば、拠点病院も余裕をもって先端医療に集中できるし、2番手、3番手の病院も生き残ることができる。緩和医療などは4番手の病院でもできるはずです。
廣橋 地域ごとに病院の特徴をはっきりさせ、お互いに情報交換しながら、役割分担を明確にしていけば、拠点病院制度はしっかり機能するようになると思いますね。
鎌田 拠点病院のトップの意識改革が必要ですね。自分の病院のことだけを考えるのではなく、地域の医療に厚みを持たせるようリーダーシップを取ることを考えてほしいですね。
廣橋 病病連携、病診連携を真剣に推進していくことです。
鎌田 そのためにはやはり国がもう少し、がん医療にお金を投じてほしい。全国に2~3カ所、地域連携のモデル地区をつくって、思い切ってお金を投じてみたらどうかと思いますね。
廣橋 いま苦労しながら地域連携を進めているわけですが、その中から必ず成功例が出てくると思います。そこにスポットライトを当てて、お手本にしていくということも考えられますね。
同じカテゴリーの最新記事
- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)
- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)
- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)
- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている
- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)
- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)


