鎌田實の「がんばらない&あきらめない」対談 北里大学医学部外科学教授・渡邊昌彦 VS 「がんばらない」の医師 鎌田實
世界1の水準の内視鏡・腹腔鏡手術

鎌田 渡邊さんは内視鏡や腹腔鏡の専門医ですが、内視鏡でどの程度の診断ができ、治療ができるのでしょうか。
渡邊 基本的に内視鏡で治療できるものは、リンパ節転移がないものです。リンパ節転移の可能性があるかないかを判断するには、肉眼的に診断する方法と、切り取って調べる方法があります。肉眼的に調べる方法とは、拡大内視鏡や普通の内視鏡で、形態、広がり、色、とくに拡大内視鏡による表面の性状(ピットパターン)を観察することによって、リンパ節転移の可能性を判断する方法です。リンパ節転移の可能性がないまたは低い、すなわちがんが粘膜にとどまっていると判断したら内視鏡で切除します。判断に迷ったら内視鏡で取って、リンパ節転移の可能性がある、すなわち粘膜下層にがんが浸潤しているという病理の診断が出た場合には、手術に回します。
鎌田 内視鏡手術を行った後に、もう1回開腹手術をする。
渡邊 そういうことです。しかし、粘膜下層にがんが入ってもリンパ節転移があるのは、たかだか10パーセント程度です。「内視鏡手術をしたあと、10パーセントのリンパ節転移があるからと言って、一足飛びに開腹手術では、患者さんがかわいそう。腹腔鏡下手術も同じでは?」と言って、腹腔鏡下手術を導入し、その後徐々に広めてきました。
内視鏡による切除の利点は、患者さんの侵襲が少ないこと、診断的治療ができることですが、逆に、小さくても取りにくい場所がありますし、一括して取れるものは直径2センチ位、分割で取れるものも4センチ位という短所もあります。最近、内視鏡による粘膜下層剥離術(ESD)を大腸がんでも行えるようになり、かなり大きなものも内視鏡できれいに取れる可能性が出てきています。
鎌田 胃がんの手術でよく行われるように、生理食塩水を注入して少し盛り上がらせ、そこから切るという方法ですか。
渡邊 そうです。EMR(内視鏡的粘膜切除術)というのは、生理食塩水を注入して盛り上がらせて、スネア(金属の輪)をかけて取る方法です。さらにそれを分割して取るEPMR(内視鏡的分割切除術)があります。ESDは、腫瘍の周りにマーキングをし、内視鏡で何時間かかけて切開、剥離していくやり方です。最近、内視鏡診断や治療の精度と安全性はどんどん向上しています。もちろんそれらの技術は日本が世界1です。
早期の大腸がんには内視鏡・腹腔鏡で対応
鎌田 内視鏡治療にいくつものスタイルができたことと、それに腹腔鏡治療が加わったことによって、従来開腹手術をしていたものが、どれぐらい手術をしなくて済むようになったのでしょうか。
渡邊 早期の大腸がんですと、ほぼ100パーセント、内視鏡か腹腔鏡で対応できます。早期がんで開腹手術をすることは、最近ほとんどありませんね。
鎌田 何センチまでの早期がんなら大丈夫ですか。
渡邊 大きさはあまり関係ありません。大事なのは深さです。粘膜にとどまっていれば、100パーセント大丈夫です。粘膜下層に入っても1000ミクロン以内ですと、リンパ節転移は3パーセント未満です。それを超えると、10パーセント以上の確率でリンパ節に転移しますので、粘膜下層の浸潤距離によって手術の適応を判断しています。
鎌田 1回目の内視鏡検査のとき、細胞を取るバイオプシー検査で、大体どこまで進行しているか、診断がつくと考えてよろしいですか。
渡邊 見た目と形と表面性状だけで、これは粘膜下層まで行っていると診断がついてしまうこともあります。その場合、変に生検をやりますと、次に内視鏡で切除しにくくなりますから、その場できちっと内視鏡で粘膜切除したほうがいいと思います。完全に粘膜下層に達していると判断したら、すぐに外科に回して手術を行うケースもあります。
鎌田 そうなると、どういう病院にかかるかは重要ですね。また、外科と内科とでは、治療方針が異なるということもあるのではないですか。
渡邊 そういうことがないように、大腸癌研究会でガイドラインをつくりました。現在は内科、外科、あるいは病院による診断、治療の差はなくなっていると思います。差があるとすれば、内視鏡の技術です。ESDのできる病院は、限られています。EMRでも上手な人とそうでない人がいます。また、腹腔鏡はまだ導入していない病院も少なくありません。これは過渡的な状況で、仕方がない面もあります。
鎌田 腹腔鏡下手術をする場合、その先生は腹腔鏡下手術の経験がどれぐらいあるのか、訊いていいもんでしょうか。
渡邊 うーん、最近の患者さんは臆することなく訊きますね(笑)。
鎌田 訊いていいということですね(笑)。その病院が年に何回ぐらい腹腔鏡下手術を行っているかがわかり、ある程度納得できれば、地方の人が東京の大学病院まで来なくても、地元の病院で手術を受けられるわけですね。
渡邊 10年前とは事情がまったく変わってきています。どこの病院でもきれいな手術ができるようになりました。内視鏡手術はインターネットでも見られるように、上手い人の技術を真似して、一生懸命自分の技術を磨くことができます。開腹手術の時代より、急速に技術は進歩しています。
再発・転移しても大腸がんは治せる
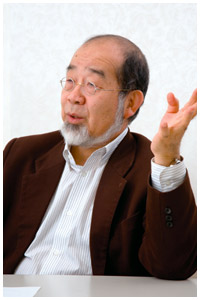
鎌田 大腸がんの特徴は、まず第1に治りやすいがんであること、第2に再発・転移しても治せるということです。その他のがんは、再発・転移すると、手遅れになるケースが少なくありませんが、大腸がんはそこから完治する場合もありますね。
渡邊 今でも、大腸がんが再発したら、切除できる場合は切除するのが原則になっています。きちっと切り取ることができれば、治る可能性は十分あります。大腸がんに多いのは肝転移ですが、肝転移をきれいに切除できれば、それで半分位の人は助かります。ほかの消化器系のがんで、そういう例は見当たりません。大腸がんは術後、定期的に経過観察をして、手術ができる段階で再発・転移を見つけて手術をする、というのが原則です。
さらにここ10年ぐらいで、化学療法が急速に進歩してきました。ただし、肝臓転移についてはがんを全部きれいに取った後に、化学療法を追加したほうがいいのか、あるいは再々発したときに備えてやらないほうがいいのか、まだよくわかっていません。
鎌田 外国ではFOLFOXなど、併用抗がん剤の予防投与が認められています。そのエビデンスはまだ出ていないのですか。
渡邊 きちっと切除できた場合、化学療法を加味することが果たして有効なのかどうか、よくわからないのが実情です。もう1つ、肝臓に転移しているのなら、まず化学療法を行い、がんを小さくしてから手術をしよう、という考え方があります。さらに、肝臓転移をしばらく化学療法しながら観察した後に、その他に転移していないかどうか確かめてから切除する、という考え方もあります。
鎌田 渡邊さんはどうしているのですか。
渡邊 私は今のところ、「待ってない派」です。切除をし、化学療法を加味します。化学療法を望まれる方は、FOLFOXを行い、FOLFOXをすでにやった人は、FOLFIRIにかえます。
鎌田 例えば、渡邊さんが進行がんの開腹手術をした患者さんで、目に見える形の転移はまったくないけれども、転移の可能性が否定できない場合、患者さんの希望で抗がん剤を使うことはありますか。
渡邊 希望された場合はやります。原則として、手術をしてリンパ節転移が1個でもある場合は、化学療法を加えます。経口抗がん剤が多いですね。多臓器に浸潤していたり、がんが腸の表面に出ているものでも、リンパ節転移がなければ、化学療法は原則としてやりませんが、患者さんの希望もうかがいます。
鎌田 現在、ステージ3までいった大腸がんの患者さんの、5年生存率はどれぐらいですか。
渡邊 結腸がんで70パーセントぐらいでしょうか。ステージ1が90パーセント、ステージ2が80パーセントですね。ステージ4でも、15パーセント前後ですが、最近はもっと良くなっているでしょう。だから、ステージ4でも決してあきらめる必要はありません。
同じカテゴリーの最新記事
- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)
- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)
- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)
- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている
- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)
- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)


