鎌田實の「がんばらない&あきらめない」対談 全日本社会人落語協会副会長/作家・樋口強 VS 「がんばらない」の医師 鎌田實
再発・転移の不安を乗り越えるには外へ出ること、笑うこと
鎌田 苦しい抗がん剤治療が終わった。次は心の葛藤が起きてくるんですか。
樋口 そうですね。再発・転移に対する不安や恐怖ですね。
鎌田 それは本当に怖いものですか。

樋口 夜、電気を消して真っ暗になると、自分1人の世界になります。その真っ暗な頭の中で、手を変え品を変え、いろんな形で死が近づいてくる。死に方はどうだ、葬式はどうする、彼岸から誰かが迎えにきたとか、死にまつわることが止めどもなくやってきます。これがやってくると、心理的な怖さを超えた状態と言いますか、自分が生きているかどうかがわからなくなりますね。その状態がずうーっと続く。これはつらいです。
鎌田 よくわかる。「がんサポート」の読者もそこを1回通ると思います。楽には通り抜けられないけれども、そこをどう通り抜けるかは、がん患者さんにとって、大きな問題だと思います。どうやって越えたらいいと思いますか。
樋口 2つです。1つは、外へ出て人と話しなさい。もう1つは、笑いなさい。この2つですね。がんになった人は、とかく何かをしてもらおうと思っている人が多いんです。がんになる前から、上げ膳・据え膳の生活に甘んじている。私もそうでした。だから、がんになる(笑)。
鎌田 がんになるのは、生き方が関係してると思いますか。
樋口 思いますね。自分がそうでした。私は各地でお話させていただくときに「タバコが肺がんの原因だと決めつけないでください」と言うんです。「タバコに手を出さなければならなかったあなたの生き方そのものが原因でしょう」と言いたい。タバコはあくまで手段です。
鎌田 あ、そう! それは、すごい!
樋口 がんになる前と同じ生き方をしていると、再発・転移がよけいに怖くなる。そうじゃなく、自分で1歩前に踏み出し、扉を開けて外へ出て、人と話してみましょうよ。生きているがんの先輩に会って話してごらんなさい。先を歩いているがんの先輩に会うだけでいいんです。その人が生きているという事実を見るだけで、ものすごい説得力があります。
鎌田 なるほどね。それから、笑いなさい、ですね。
樋口 笑いも、笑わせてもらうのではなく、自分から笑うことです。笑ってみると、悩んでいたことも、苦しんでいたことも、その瞬間、吹っ飛んでしまう。「笑いはその場で、あなたの考え方を180度変えてくれますよ」と、私は言っています。それは自分で心から笑って実感してみないと、わからないんです。
トラブルを避けるためマニュアル化が進む病院
鎌田 私が読者に言いたいことは、最近、医療ミスとか訴訟沙汰とか、医療現場がとてもギスギスしていますから、医師は万が一の場合、訴えられないように、悪いほうへ、悪いほうへと話す傾向があるということです。医師の言葉に惑わされると、かえって不安が高じます。だから、医師は2割ほど悪く言うと思って、医師が言うより2割ほどはいいと解釈したほうが、治る確率も高くなるんじゃないかと思いますね。
樋口 そのとおりだと思います。それに拍車をかけているのが、病院のマニュアル化です。病院でいろんなトラブルが起き、訴訟も増えてきているために、いろんなことをマニュアル化しています。これを言っておく、あれを言っておく。看護師さんがマニュアルシートを持って歩いています。CT検査を受けるだけで、たくさんサインを求められます。そのために1時間待たされる。
そんなことより、患者さんの顔をひと目見て、「いい顔ね。何かいいこと、あったの?」と、なぜひと声かけないんでしょう。マイナスをなくしてゼロにすることばかり考えている。以前の病院には、先生や看護師さんの患者さんを気遣う、プラス面のひと言がありましたが、それが最近、多くの病院から消えようとしています。
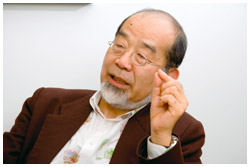
鎌田 なぜそういうことになるのか、病院側の人間として言わせてもらえば、最近、学校にメチャクチャな要求をするモンスター・ペアレントがいるように、病院にはモンスター・ペイシェントがいて、些細なことで訴えてみたり、文句を言ったりする状況があるからです。それに医師や看護師が疲れ切っている。
それに対応するためにマニュアルを重視するようになったんですが、そのことでまた、病院側も患者さん側も疲れてきている。輸血するだけで、万が一の場合のことを羅列して説明されても、患者さんは戸惑うばかりだし、説明する病院側だって決して気分の良いものではない。万一の話のあとに、病院側は最後に、「この輸血はあなたのために必要なことなんですよ」と、一言付け加えるべきですね。
樋口 私が治療しているころには、それがありました。この10年で大きく変わりましたね。
患者さんの側も受け身の姿勢を改めよ
鎌田 医療人が変わらなければならないことはたしかですが、では患者さんの側は今、どう自己防衛したらいいと思いますか。
樋口 やはり、自分はこう生きたい、こんなことがしたいということを、病院にきちんと声に出して伝えるべきです。嫌われてもいいから、言う。病院から言われるままに、「わかりました」と答える受け身の姿勢では、あとからつらくなります。
病院がマニュアル的な対応を改める努力をし、患者さんが受け身の姿勢を改める中から、新たな接点が見つかるのではないかと思います。病院は何のために治療をするのか。患者さんの生きたい生き方を実現させるためです。100人の患者さんがいれば、100通りの生き方があります。それを尊重することが命の尊厳を守ることにつながると、私は思います。そこに接点を見つけることではないでしょうか。
鎌田 自分の意志で治療法を選択してきた樋口さんだからこそ、言える言葉だ。
樋口 自分がしっかりした生き方を持っていなければ、セカンドオピニオンというシステムも使いこなせません。2人の先生から2つのメニューをもらっても、どうしたらいいか、わからなくなるだけです。サードオピニオンなどもらったら、なおさら混乱します。
がん対策基本法ができたのはうれしいんですが、それを活かすには、患者さんのほうがしっかりしなければなりません。自分の生き方をしっかり持っていれば、医療側からその生き方を支援するメニューがいろいろ出てくるはずです。黙っていると、標準治療というわずかなメニューしか出てきませんが、こういう生き方をしたいと言えば、もっと多くのメニューが出てくるんです。それを待っている先生が全国にたくさんいます。
同じカテゴリーの最新記事
- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)
- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)
- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)
- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている
- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)
- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)


