鎌田實の「がんばらない&あきらめない」対談 国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部部長・内富庸介 VS 「がんばらない」の医師 鎌田實
患者さんのつらさがわかる「つらさと支障の寒暖計」
鎌田 うつかどうか診断できる、簡単な指標が何かあるといいんだけどね。
内富 私たちは今、「つらさの寒暖計」という2本の棒グラフを使っています。1本はつらさを、もう1本は「生活にどのくらい支障があるか」を、それぞれ0から10の間で、患者さんにチェックしてもらいます。
鎌田 えっ、それだけでいいの?
内富 といわれると、悩みます(笑)。10年、悪戦苦闘した結果として、その程度なのかと思われるかもしれませんがまず第1歩になりました。
鎌田 何点以上で、気をつければいいの?
内富 4点と3点以上ですね。事実、「グレー」と出た人の約半数が、うつ病、もしくは適応障害という診断が出ています。
鎌田 患者さんたちも、これを使えば自己採点できますね。生活に支障があるかどうかというのも、非常にわかりやすい。
内富 ただ、自己採点で「黒」と出ても、私たちのところに相談に来てくれるのは、4人に1人というのが現状です。来ない3人に聞くと、「今はがん治療をやっているから、ちょっと待って」というんです。“心”のことを聞いてもらう余裕がないと。
鎌田 なるほど。それと、これで自己採点をした患者さんが地元の精神科に行ったとき、相手にしてもらえるかどうか、という心配もあります。
内富 日本の精神科医はどちらかというと、統合失調症など高度で専門的な治療に主眼を置いていますからね。もう少し一般の人を対象にしてほしいです。今年からはじまる拠点病院を中心とするサイコオンコロジー(精神腫瘍学)研修会などを精神科医の皆さんに受講していただけると、ずいぶんと状況も変わると思うんですが。
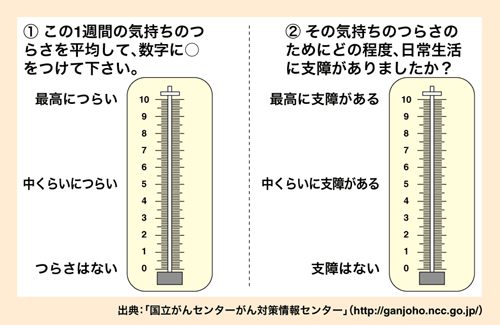
サイコオンコロジーとは、QOLを維持・向上する学問

鎌田 ちょうど言葉が出たのでお聞きします。サイコオンコロジーとは、具体的に何をする学問ですか?
内富 サイコオンコロジーの第1の目的は、がん患者さんとご家族のクオリティ・オブ・ラ���フ(QOL)の回復・維持・向上です。そのためにがんが患者さんやご家族の心にどんな影響を与えるのかを明らかにします。
もう1つの目的は、心ががんに及ぼす役割を解き明かすことにあります。心や行動をいい方向に保つと、がんにかかりにくくなるのではないか、またがんを抱えても長生きにつながるのではないかといった問題です。これもサイコオンコロジーを生み出す大きな原動力になりました。実際の治療の現場では、前者の目的が9割を占めています。
手法としては、精神医学や心理学の技術を核として、そこに基礎医学、免疫学、内分泌学、公衆衛生学、社会学、倫理学などを導入しながら、がんの人間学的側面を追及します。最終的には、「QOLとは何か」をずっと問い続けていく学問だろうと思います。
鎌田 つまり、ここでいうQOLとは何でしょう。
内富 うーん……、むずかしい。
鎌田 はっはっはっ。究極の質問だものね。QOLは「何かの質」ですが、どう訳したらいいのかな。人生? 生活?
内富 その人が普段、人生について考えていれば「人生の質」だし、生活を重視する人なら「生活の質」。ライフって多義的ですね。
鎌田 ぼくは命にまつわるエッセイを書くので、その視点でものを見る習慣があるんですが、生活の質を大事にすると、その積み重ねで人生の質が上がり、人生の質が上がると、いつかは魂の質、言い換えれば自分が存在している意味みたいなものがわかるんじゃないか、とわかりやすく、自分の頭のなかで整理しています。
最終的には、自分だけでなく、ほかの人の命や、人間を超えたすべての生命までをも含めて「命の質」なのかな、と思っています。でも、そんな難しいこと以前に、今日1日の生活の質がまずよくならないと、人生の質も魂の質も命の質も上がらない、と思うんです。
内富 おっしゃるとおりですね。QOLが何かは、いまだによくわからないけれど、1つ確かなことがあります。それは、「身体の痛み同様、うつ状態はQOLを最悪の状態にする」ということ。うつ状態からも頭痛、腰痛、肩こり、消化器症状と、さまざまな身体症状が出て、今日1日の生活の質が悪くなりますし、人生の質も魂の質も台無しになります。うつの苦しみは「いろいろながん治療を受け、あらゆる副作用を経験したけれど、これほどの心の激痛はない」という人もいるほどです。自殺してでも解放されたい苦痛なのですから、人間の最大の苦しみといえます。私たちはここに何とか手を差しのべたいんです。
悪い知らせを伝えるとき、患者さんが望むこと

鎌田 それで、シェア(SHARE)というものをお作りになったんでしたね。
内富 心のケアの第1歩です。精神腫瘍学開発部の藤森研究員が中心となって作成しました。いい知らせのときは問題が少ないけれども、悪い知らせのときは上手にコミュニケーションをとらないと、その後の治療にも影響しますから。すでに欧米でいろいろなプロトコル(手順)が考えられていますが、どうも日本の実情には合わないんです。
たとえば、悪い知らせを伝えるときは、患者さんの手や肩にふれる、とありますが、調査をすると、オーストラリアでも患者さんは「触ってほしくない」。まして日本人は、絶対触ってほしくないという結果でした。
鎌田 確かに、そうでしょうね。
内富 いや、鎌田先生のような方に触っていただくのは、むしろ特権的なことだと思いますが、自分の息子より若い医者に肩なんか抱かれたら、むかむか腹が立ってくる(笑)。
鎌田 はっはっはっ。そうだよねえ。
内富 そこで、医師7名、患者さん571名のあわせて578名に意向調査をしたんです。すると、4つの要点が明らかになりました。すなわち、適切な場を設定し、適切な手順で悪い情報を伝え、今後の治療や生活のことなどの情報も伝え、最後に気持ちをサポートする。この4つの要点の頭文字がSHAREであり、その内容を時系列に並べ変えたのが、悪い知らせを伝える際の「SHAREプロトコル」です。
鎌田 ここには、ああそうだなあと思う「技術」がたくさん入っていますね。たとえば、「伝え方」として、がんと明確に伝えることは大切ですが、がんとか腫瘍といった言葉をくり返さないとか、患者さんが希望を持てるように伝える、希望がもてる情報も伝えるとか。医療者が「悪くない」とウソは言えないけれど、患者さんが自分の頭のなかで考え直して、希望を持つのはいいことだと思います。
内富 そのとおりだと思います。今の社会には「会社のがん」というような隠喩が定着しています。そのなかで、信頼している医師からがんだがんだといわれると、なんだか厄介者になったような気がしてしまいます。
鎌田 そういえば、ラジオ番組で永六輔さんをゲストにお呼びしたとき、永さんも「がんという言葉がいけない。響きが悪すぎる」とおっしゃっていましたね。ちょうど奥さんがスキルス胃がんになり、在宅ケアで看取られたばかりだったこともあって、「ガンはやめて、ポンではどうですか」って。
内富 いいですね(笑)。
鎌田 国立ぽんセンター(笑)。がんのイメージが明るくなるかもしれないね。
それはともかく、先生はこのSHAREを使って、今年から医師に対する研修を本格的に開始されるのでしたね。
同じカテゴリーの最新記事
- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)
- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)
- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)
- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている
- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)
- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)


