鎌田實の「がんばらない&あきらめない」対談 埼玉医科大学病院臨床腫瘍科教授・佐々木康綱 VS 「がんばらない」の医師 鎌田實
交差耐性ができないメリット
鎌田 その2つはどういう形でがん細胞に作用するんですか?
佐々木 2つとも真のメカニズムはつかめていないんです。VEGF受容体チロシンキナーゼの阻害が中心であろうと言われていますが、いろんな分子に作用することがわかっていますので、どの標的分子にもっとも強く作用することでがん細胞を殺すのかまだわかっていません。だから、まだ効果を期待できる人を絞り込むことができないんです。
鎌田 今おっしゃられた3つの特徴以外に、最近注目されだしているようなことはないですか。
佐々木 従来の抗がん剤は、最初効果があってもだんだん効かなくなってきます。その大きな原因の1つに交差耐性ができることがあげられます。これは抗がん剤を使っていると、その薬だけでなく、まだ使っていない近縁の薬に対しても耐性ができてしまうことですが、そのため化学療法では抗がん剤を効く順番に使っていきます。そうなると当然、第2第3の薬はだんだん効かなくなってくるんですが、分子標的薬の場合は少し異なり、最初効いた薬に耐性ができても近縁の薬を2番手、3番手で投与すればよく効くことがわかっています。標的は同じでも攻撃のメカニズムを変えれば十分効果をあげる可能性があるのです。そのあたりがわかってきたので、今、ハーセプチンへの耐性ができた患者さんにターゲットは変えずに作用機序を変えた治療薬の開発が進んでいまして、日本でも将来認可されます。
鎌田 交差耐性についてもう少し詳しく聞きたいんですが、そうすると、最近休眠療法が注目されているようですが、あまり効かない抗がん剤を副作用が弱いからといって、やたらめったらに使うのは間違いなわけですね。
佐々木 そうですね。交差耐性をつくってしまう原因になりますね。低濃度の抗がん剤を使うメリットを主張すること自体はいいんですが、言うからには、ちゃんとした科学的根拠を持ってからやるべきです。まだ、標準治療よりいいというデータが出ていないのに日常臨床に使うことはやってはいけないと思います。休眠療法なんて耳障りがいいですが、ちょっと間違うと患者さんを大きな誤解に引き込むことになります。
イレッサには患者を限定した臨床試験データがない
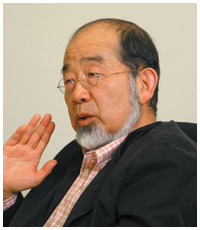
鎌田 ハーセプチンを中心にお話いただいたので、次にイレッサについて伺いたいんですが、これに関してはブレーキが掛かるんじゃないかと思ったら、それはそれで意味があるんじゃないかという声も強くあります。現時点で先生はどう評価されますか。
佐々木 イレッサの最大の特徴は、腫瘍への反応性、効果、��作用などに人種差があることがわかった最初のケースという点です。これはかつてなかったことで、人類最初の経験です。イレッサはがん細胞の上皮成長因子受容体(EGFR)のシグナル伝達を邪魔することでがんの増殖を抑えるのですが、人種間に差が出るのはEGFRのミューテーション(変異)が原因であろうといわれています。イレッサの場合、問題なのは顕著な腫瘍縮小効果が現れる「東洋人、女性、非喫煙者、腺がん」の方たちを対象に前向き評価をしたデータがないことです。延命効果がないというデータはそういうグループを対象にした試験のデータではありません。たとえば、ハーセプチンではHER2を過剰発現している患者さんに限定投与した試験で従来の抗がん剤より効果があるという結果を得ています。ところがイレッサの場合まだそれが出ていません。そういう人だけを対象として試験をしても変わらないんじゃないかという声もありますが、それはなんともいえません。一方で非常に劇的な効果が出る患者さんがいることも事実です。
鎌田 僕が相談を受けた肺がんでがん性胸膜炎を起こしていた女性は、大阪の病院でイレッサの治療を受け、骨転移もありますが、2年間元気に生活しています。今度「鎌田實とハワイに行こう」というツアーで一緒に旅をします。やはり劇的に効く人もいる。この方はそのことを世に問うて欲しい、簡単に発売禁止にしないで欲しいと言っていました。先生は、イレッサを肺がんの患者さんにそれほど使うことはないですか?
佐々木 使う場合は再発転移の2次治療以降に使って、最初に使うことはありません。その場合も、患者さんに強い副作用が出るリスクがあることもしっかりお話するだけでなく、全身状態がいいか、既存の肺の病変がないかといった点にも留意して、その条件を満たさないようであれば患者さんが希望されても使用しません。
鎌田 日本人に、本当に間質性肺炎が起こりやすいかどうかという問題には決着が付いたんでしょうか。
佐々木 まだわかっていません。ただ、間質性肺炎がすぐに現れる患者さんの場合は難治性である可能性が高いです。イレッサにはそういうわからない面が多いので、将来的には、肺がんに対しては欧米で標準治療薬になっているタルセバ(一般名エルロチニブ)が認可されれば、日本でもそれに順次変わっていくのではないでしょうか。
アバスチンによるドラスチックな副作用

鎌田 大腸がんに関してはアバスチンに大きな期待が寄せられていますが、先生から見て注意すべき点はどのあたりですか。
佐々木 ドラスチック(過激)な副作用が出ることです。とくに消化管穿孔は要注意です。先ほども申しましたように大腸がんの患者さんの場合、腸に病変があると穿孔を起こすケースがよくあります。去年のアメリカの臨床腫瘍学会では、卵巣がんの患者さんの10パーセントに消化管穿孔が起こっていることも報告されています。肺がんの患者さんには喀血が起きることがありますし、脳転移がある患者さんに脳出血が起きるというデータもあります。血圧が上がったり、蛋白尿が出たりするケースもあります。ですから、大腸がんの患者さんの場合、高血圧の患者さんが多くいることが予想されるわけですが、その場合がんの治療効果はあっても、血圧のマネジメントに難渋するケースが出ることが予想されます。
鎌田 そうなると、がんだけを診る医療だけでは対応できなくなりますね。
佐々木 総合力が勝負になります。私のいる埼玉医大の腫瘍内科ではすべての患者さんにチーム医療で対応しています。穿孔が起きる可能性が想定される場合は、外科の先生にこのような情報を提供するようにしています。
同じカテゴリーの最新記事
- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)
- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)
- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)
- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている
- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)
- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)


