鎌田實の「がんばらない&あきらめない」対談 北里大学生命科学研究所客員教授・白坂哲彦 VS 「がんばらない」の医師 鎌田實
多くのがんで、顕著な奏効率が認められている
鎌田 膵がんについてはどのくらい有効性があるでしょうか。
白坂 下の表に示すように、従来、遠隔転移、主に肝転移のあるステージ4bの膵がんは、余命3カ月から半年ですが、アメリカでジェムザール(一般名塩酸ゲムシタビン)と5-FUを比較したデータが出ています。1年生存率はジェムザール単独で18パーセント、5-FU単独で2パーセント。
この成績からジェムザールがアメリカでも日本でも承認されたのです。ただしこの試験で用いられた5-FUの投与法は週1回の急速静注で、5-FUの最適な投与法ではありません。我々が行った低用量シスプラチンのFP療法の1年生存率は26パーセント、TS-1単独では32パーセントでジェムザールより優れた成績が出ています。ただこれは比較試験ではないので、あくまで参考データですが。さらに、最近のTS-1隔日投与と低用量シスプラチンにタキソールの併用療法では1年生存率が73パーセントまで上がり、これに、放射線を併用すると1年生存率は実に86パーセントまでいきます。この臨床試験の平均観察期間は321日で、現在も治療継続中です。
鎌田 我々はジェムザールが出てきて初めて膵がんに有効な抗がん剤が出てきたという感覚を持っていますが、それに匹敵するほどですか。肺がんなどの成績はどうでしょうか。
白坂 肺がんについてはTS-1単独で約22パーセント、シスプラチン併用で約47パーセントで承認されました。かつて乳がん、肺がん、膵がんなどには「5-FUは効かない」という伝説がありましたが、それは、5-FUの使い方が違っていたため、5-FUががんに到達することが少なかったからなのです。
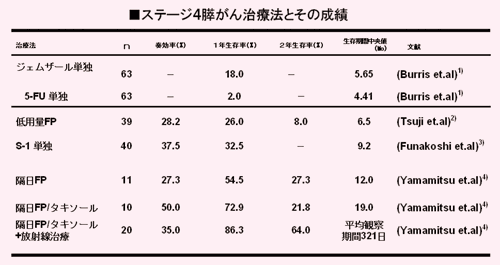
2)Am Soc Clin Oncol 21:2002(abstr.No.628)高知医療センター
3)Proc AP/IAP Joint Meetting.2006(Abatr.No.89)
4)日本癌治療学会誌41:278 2006(Abatr.No.S10-5) 札幌月寒病院 山光進他
5-FU併用のメニューをTS-1併用に変えたら
鎌田 すると、これからはTS-1プラス低用量シスプラチンのFP療法などが期待の星ということになりそうですね。
白坂 そうなれば良いと思っていますが。もう1つ期待されるのは、大腸がんの化学療法の分野です。アメリカではFOLFOXとか、FOLFIRIと呼ばれるメニューが標準治療とされ、日本もこれを受け継いで���ます。ところが、このメニューでは5-FUの投与法は持続投与ではないので、5-FUの本当の力が発揮できません。
これに対して、この5-FUをTS-1に代え、1日置きの内服にすればもっと効果が上がると私は考えています。TS-1は日本人の胃がん、大腸がんで有効性が証明されているのに、アメリカの真似事ばかりしているのは困ったことです。
鎌田 そもそも5-FUの効果を上げて、副作用を抑える改良型がTS-1なのですから、これを使うのが自然ですね。先生のご憤懣はわかります。大腸がん治療も、同じ注射系の5-FUが欧米で認められているから、どうしてもそれを取り入れることを考えざるを得ないわけですね。
しかし、がんセンターなどでもTS-1について症例検討して、そろそろ論文をまとめそうだということになれば、やはりFOLFOXの中の5-FUをTS-1に代えるといったことが検討されるべきでしょうね。
白坂 臨床試験では、EBM(evidence based medicine=根拠に基づいた医療)としての結果を出すために膨大な症例数の母集団が必要で、時間もかかります。だから、なかなか標準治療法に結びつくようなものは出せません。
フトラフールは最初注射剤でした。日本で経口剤に改良して道が開かれ、そこから、UFTもTS-1も誕生しました。もし「フトラフールはだめ」ということで終わっていたら、UFTもTS-1も誕生しなかったでしょう。その歴史を顧れば、抗がん剤の開発は、どうしたら患者さんを副作用に苦しめず延命効果につなげるかを考えていく必要があると思います。
「注射でなければ効かない」という飲み薬への偏見
鎌田 日本の医療界には、TS-1が3剤配合という理由から、「コロンブスの卵」のように独創的な発想ではないと見て、軽んじたりする傾向があります。しかし、コロンブスの卵だろうがなんだろうが、効けばいいわけですね。そのへんは日本の医療界も発想を変えたほうがいいのではないかと思います。
白坂 もう1つ、飲み薬に対する偏見もあると思います。アメリカのオンコロジスト(がん専門家)たちは、もちろん副作用の危険性の問題もあるけれど、完全に医師の監視のもとに抗がん剤を投与したいのです。自分の預かり知らないところで薬を飲むのは困るわけで、そこから「注射剤でなければ効かない」という考え方が生まれるのだと思います。フトラフールやUFTが出ても、アメリカでは「そんなもの、患者がきちんと飲んでいるかどうかわからない」というわけです。
鎌田 日本という国は外圧がかからないと変わらないといわれます。その点、外国でTS-1についていい成績が出れば変わる可能性があるわけですが、アメリカなどでは症例検討は行われ出しているのでしょうか。
白坂 ええ。いい結果が出ています。アメリカではTS-1と高用量シスプラチンとの併用療法で、ヨーロッパでもその検討が始まりました。ですから今後、外国でTS-1はすごい薬だといわれるようになり、逆輸入されてくるような形ができるのではないかと思います。
緩和ケアで望まれる治療にも対応できる
鎌田 今後構想されているお仕事はありますか。
白坂 私が先生にお会いしたら、緩和ケアの分野のことでぜひお聞きしたかったことがあります。それは末期がんの患者さんでも何も治療をしないのではなく、アクティブではないけれどケアに有効な治療をするのはどうかという点です。もう5年以上も前の話ですが、浜松市にある聖隷三方原病院の緩和ケアで、5-FUと低用量シスプラチン併用のFP療法を取り入れてもらったことがあります。すると患者さんの中には、症状が緩和されて元気になり、自宅に帰って農作業ができたというケースがあります。
こんなふうに末期の患者さんもけっしてあきらめるのでなく、TS-1によるやさしい治療なら行うことができるのではないでしょうか。
鎌田 僕らも緩和医療をやっていて、やはり政府や国のやり方に納得できない点があります。それは先生のおっしゃるようにQOL(生活の質)を上げるために抗がん剤を使うという方法があるけれども、緩和病棟の中では抗がん剤について保険請求ができないことです。
例えば私の『あきらめない』(集英社刊)という著書で紹介していますが、緩和ケア科にいるスキルス胃がんで余命3カ月という患者さんが、「何とか子どもが学校を卒業するまで生きたい」と希望されました。化学療法を行うとなれば、本来は一般の病棟に移ってもらうことを考えなければなりませんが、この患者さんは他の病院から緩和ケアに移って来られ、満足度が高くて「よそへ移りたくない」とおっしゃっています。死ぬことはわかっているけれど、苦しみたくもないし、生きる挑戦もしたいという状態です。
そこでスタッフみんなが議論して、「患者さんの希望だから赤字覚悟で緩和病棟で化学療法をやろう」ということになったのです。1年に何例かそういう選択をすべき症例があります。私は先生のご著書を読んでいて「この薬(TS-1)は緩和ケアに合うな」と考えた部分がありました。
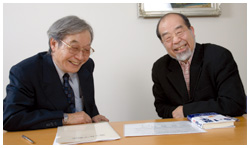
白坂 緩和ケアの中でも、FP療法やタキソールの毎週投与を加えた治療だったら十分できるでしょう。緩和ケア病棟にいるとがん治療ができないというのが日本の医療制度ですが、これを変えていく必要があります。先生の病院のようにあれだけ患者さんにやさしい空間で、ほんとうに患者さんにやさしいがん化学療法の治療ができたら理想的ですね。
(構成/林義人)
同じカテゴリーの最新記事
- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)
- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)
- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)
- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている
- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)
- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)


