鎌田實の「がんばらない&あきらめない」対談 在宅医/作家・山崎章郎 VS 「がんばらない」の医師 鎌田實
スピリチュアルな痛みとは「生きる意味」の喪失だと思う

鎌田 以前、スピリチュアルなケアは、ホスピスに限らず、すべてのケアの中にあるべき、とおっしゃっていましたね。
山崎 今もそう思います。人間は自分の力でどうしようもない壁に直面して生きなければならないときがあり、自分が今生きている意味を問いかけざるを得ません。「こんな状態で、生きている意味はあるのか」とね。でも、そういう状況は、実はいっぱいあります。そして、そのことを患者さんたちと話し合い、考え、深めて行くことは、ホスピスでも在宅でも、がんでもがんでなくても、必要だと思うんです。
当然、在宅ケアでも、そうした対話が日常会話の中で展開することは、けっこうあります。その結果、生き返ったようになる人たちがいます。それは薬のせいでも何でもなく、思いを、表面的でないところで受け止めようとする関係性を、実感できたからだと思います。これが、普段私たちが「スピリチュアル・ケア」と呼んでいるものなのではないか、と思いました。
鎌田 すべての医療には、スピリチュアルなものがあってしかるべきだと。
山崎 しかるべきだし、あるはずだと思います。逆にいうと、病気や障害をもつ人たちは、言葉に出さなくても、スピリチュアルな痛みを必ず感じていると思います。
鎌田 病んでいる臓器だけが問題ではない。
山崎 苦しい、夜眠れない、不安、痛い、イライラするといった訴えも、スピリチュアルなところから発する部分があると思います。それに対して、「安定剤でも使いましょう」というのは簡単ですが、話をよく聞くと、だんだん家族関係や社会的関係について、患者さんが吐き出してくることがありますね。聞いていると、体の症状も落ち着いて、「もう少し休みましょうか」で済んだりすることもあったりして。
ですから、患者さんの表現からスピリチュアルな痛みを感じる訓練を、医師も看護師もどこかで行う必要があると思います。
鎌田 日本の医学教育では、医師も看護師もあまり教わらずにきていますよね。いずれにしても、ホスピスケアはがん末期の患者さんのケアの手法というだけでなく、すべてのケアにつながるわけですね。
山崎 その人の生きてきた生活、今生きている環境、関係性。そこに支点を置くことで、私たちのもつ専門性がもっと生きる場面作りができるのではないかなあ、と思います。
鎌田 最近はバリデーションという、認知症の手法が評価されていますね。1人���人間を丸ごと評価することによって、「変なことをするおかしな人間」ではなくなるわけですが、ぼくはこれを勉強していて、「すべての場面で使えるなあ」と思いました。たとえば、子どもをちゃんと価値ある存在として見る。寝たきりになったおじいちゃんを、価値ある存在として見る。組織の中間管理職がバリデーションを学べば、スタッフは働きやすくなるだろうなあ、と思いましたが。優れたホスピスケアも、いろいろなものに応用できそうな気がしますね。
山崎 まさに、バリデーションもスピリチュアル・ケアだと思います。私がたどってきたのはスピリチュアルな痛みのほうですが、これももっと幅広くとらえていいと思います。
鎌田 スピリチュアル・ペインって、日本語では何といったらいいかしら。
山崎 やっぱり、「生きる意味の喪失」では?
鎌田 うん、なるほど。

山崎 そして、スピリチュアル・ケアとは、だれかが生きる意味を失って、もがいているとき、その思いを共有すること。それによって、その人が自分の問題を整理し、道を見い出せるようにすること、ではないかと思います。今、自殺する子どもたちが問題になっていますが、あの子たちも必要としていたのは、そうしたスピリチュアル・ケアだったのだと思います。
鎌田 本当にそうですね。
山崎 ホスピスの現場で必要なのも、「どうしていいかわからなくなり、道を見失ってしまった人たちに対するサポート」。つまり、とても普遍的なんです。それをホスピスだけでやるのがつらくなり、場を変えてみたわけです。
鎌田 で、成功したんだ(笑)。
山崎 ですから、コミュニティケアなんです。私たちは「子育て支援」も目的のひとつにしています。実際に月に1度、日曜日に遊びのプロに来てもらい、中庭やデイサービスの場所を使って子どもたちと遊んでもらっています。そうしたら、子どもたちがこの施設に違和感をもたなくなりました。いつのまにか子どもたちが来て、利用者たちと交流している。今度はそのおかあさんたちに参加してもらえる流れを作れないかなあ、と思っています。
結局、スピリチュアリティを中心に考えると、世代も立場も超えられる。それを私たちは「コミュニティケア」と呼び、この場所ではそれを実現していきたいと考えています。いろいろな人が混在して生きられる社会、ですね。
鎌田 何々ケアなんていわなくても、いいものの原点はみんな同じところなんだねえ。
人は病院ではなく、家で穏やかに死ぬこともできる
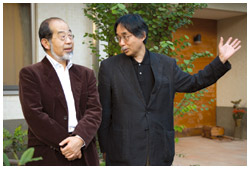
鎌田 最近、先生が尊敬されていたエリザベス・キューブラー・ロスが亡くなりましたが、彼女に関し、読者に伝えたいことは。
山崎 キューブラー・ロスが死を迎える人たちの心理過程をまとめた「死の5段階」もすごいと思いますが、私がいちばん影響を受けたのは、『死ぬ瞬間』という彼女の本の中に描かれた、ひとつの光景でした。彼女はスイスにいた子ども時代を回想しているのですが、木から転落して重傷を負った人の話が出てきます。その人は病院ではなく家に連れ帰ってほしいと頼み、家の中でいろいろな人に看取られて亡くなるのです。
当時、私は医者になって6~7年目で、人が死んでいく場面では当然のように蘇生術を施していました。けれども、病院でなくても人は死ねるし、家という場で死んでいくときに、そこから見える風景がこんなに平和で穏やかだというのが、とても衝撃でした。
鎌田 すると、先生の仕事とキューブラー・ロスから得たものとが、やっと重なってきつつあるわけですね。この「ケアタウン小平」で。
山崎 ありがたいことに、日々実感します。
もうひとつ、彼女から教えられたのは、「死をタブーにしてはいけない」ということです。患者さんたちは自分の身に迫ってくる死を感じ、それに関する言葉を口にし始めます。それをそらしたり逃げたりせず、率直に向き合うべきだと。それによって、死に近い人は死を受け入れられるし、死後を信じている人にとっては、未来に続く新しい出発点にもなりうるかもしれません。
同時に、私は、患者さんが自ら語り出した場合には、「私は経験できないので、教えてください。誰かに話してあげることができるかもしれないから」とお願いします。事実、そうした問いかけが可能な関係性ができると、とてもたくさんのことを伝えてくれますが、それは別な方から問われたときに、「ぼくはわからないけれども、こう聞きましたよ」と伝えることで生かすことができる。そういう流れも作れるのではないかと思っています。
そうした対話を、キューブラー・ロスは多数書いています。それは、死後の世界が約束されているキリスト教国だからできるのではなく、場面さえきちんと共有できれば、人はみな自分なりの死後世界観をもっているわけですから、日本でも可能だと思うんです。
鎌田 今後もたくさんのことを試みてほしいと思います。先日のお仕事を注目してみています。どうもありがとうございました。
(構成/半沢裕子)
同じカテゴリーの最新記事
- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)
- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)
- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)
- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている
- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)
- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)


