鎌田實の「がんばらない&あきらめない」対談 北里大学麻酔科教授・外 須美夫 VS 「がんばらない」の医師 鎌田實
ズキズキ、ちくちく。日本人の表現の豊かさ
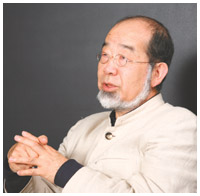
鎌田 ところで、痛みにはずいぶん多面的な表現があるんですね。刺すような痛み、打つような痛み、おそろしい痛み、冷酷な痛み……。この本にはたくさん書いてあります。一般に、人は他者である医療者に自分のつらさをうまく表現できない場合が多いんですが、これを読むと、痛みの表現は実は豊かなんだなあと思います。患者さんがこういう言葉のリストをもって医師に接してくれれば、医師も「痛くない」で終わらせず、「ああ、一晩中苦しんだのかなあ」など、想像できるのではないか、医師と患者さんが協力し合って痛みを取り除くことができるのではないか、と思いました。
外 本を書くに当たり、患者の痛みはどう表現されているのか調べました。そうしたら、アメリカに感覚的、情動的、評価的という3つのカテゴリーの分類がすでにありました。では、日本人はどう表現するかと考えたら、患者さんはまず、ズキズキ、ちくちくといった表現をする。これこそ、まさに日本人の表現の豊かさだと思いました。こういう言葉で表現されたものは、ぼくらにもすぐ伝わります。それは、体から発する言葉だからです。体の今の痛みを、ほかのところを介さずに、そのまま言葉として出している。
鎌田 子どもっぽい言葉かもしれないけれど、医師にとってもわかりやすいんですね。
外 そうです。これは非常に大事で、体の声のほかに、要素が何も加わっていない。次に、「何々のように痛い」という表現があります。これまた日本人に特有な表現ですが、焼きゴテを当てられたように、とか、剣山を当てられたように、という具合です。自分の経験と照らし合わせて、痛みを表現しようとするんです。
鎌田 なるほどねえ。たしかに、ぼく自身、一般内科医として、心臓の患者さんが胸を指して「ちくちく」とか言うと、「狭心症じゃないだろう」と思い、「重石を載せられたように」とか言われると、狭心症を疑って検査をしたり、自分なりに区別していますね。患者さんの痛みがどう表現されるかで、医師はずいぶん対応が変わるのではないかと思います。
擬態語、擬音語には、エビデンスがあった

外 はい。私はいちばん最初の擬態語、擬音語は、医師にとって本当に重要だと思ってい���す。たとえば、専門的にいうと、その言葉は、痛みがAデルタ線維なのか、C線維なのかを、意外と表現しているのではないかと思うんです。
鎌田 今の言葉、読者の皆さんにわかりやすく表現できますか。
外 痛みは、必ず体のどこかから来ています。痛いときにただ痛いという人はほとんどなく、頭が痛いとか足が痛いとか、体のどこかを指します。そして、ぼくらが習うのは、痛みが体のある場所に発生し、知覚神経で脊髄に運ばれ、知覚神経から脊髄、脊髄から視床という脳の中枢に行き、そこで痛みとして感じるということです。
その、経路の中の知覚の神経は、大きくAデルタ線維とC線維に分けることができる。でも、Aデルタ線維は速い鋭い痛み、C線維は遅い鈍い痛みというように、それぞれの神経線維のもたらす痛みはかなり違っています。患者さんの表現は意外にそれに即しているので、ああ、これはこういう神経が障害を受けているのだな、といったことがわかるんです。
そうしたメカニズムが科学により少しずつわかっています。また、神経伝達の仕方やシナプスの違いなども明らかになり、その痛みに対してどんな薬が効くか、ということもわかってきています。
鎌田 そうなんですか! というと、一見幼児語のようだけれど、ピリピリとかビリビリとかの痛みはAデルタ線維、ギュウーとした痛みはC線維と、わりあいエビデンス(根拠)がある可能性が高いわけですね。
外 そう思います。薬も、どんな薬がどういうところに効くか、細胞レベルや分子レベルでわかってきていますから。
内服、注射、パッチ。多様な薬を組み合わせて
鎌田 今は、痛み止めは注射から張り薬、座薬まで、すごく進歩しましたね。とくに医療用麻薬のオピオイドなどの進歩はすごい。
外 たしかに、私たちにとっても、手持ちの手段が増えました。
鎌田 外さんの場合は、ぼくたち一般医がやらない硬膜外ブロックなども、行うのでしょう。
外 まあ、麻酔医ですから、脊随や神経根などの、いわゆる神経軸にまで手を出すことはできます。
ただ、この方法は効果として切れ味はいいんですが、テクニックも必要だし、長期間のQOLとしては十分ではありません。やはり、経口薬や静脈注射やパッチなど、いろいろなものを組み合わせて、その人にあった鎮痛の方法を選ぶことが大事だと思います。
痛みをとる最終の方法としては、神経破壊薬と呼ばれる薬を使うこともあります。文字通り、神経を破壊することで痛みを感じないようにするのですが、この薬は運動神経や交感神経など、ほかの神経も一緒に破壊してしまうので、使える場所はごく限られています。手や足が動かなくなった、というわけにはいきませんから。
鎌田 硬膜外ブロックは長期的に欠点があるのですか? 私たちの病院では6年くらい前から、がんの手術などの場合に、硬膜外に手術前からチューブを挿入し、手術後4~5日の間、そこから麻酔薬を注入する方法を選択しています。患者さんが痛みを訴えたとき、ちょっと増量してあげるだけで、その数日をすごく快適に過ごせるし、術後にすごく早く離床し、歩き出せて、誤嚥性肺炎の比率も低くなりました。
当然、手術に対する患者さんの不安感も、すごく減っています。でも、それは短期の療法なんですね。
外 そうですね。チューブ(硬膜外カテーテル)を置くのは、感染なども心配ですから、どんなに長くても2週間ですね。もちろん、10日~2週間後に入れ直せば、1カ月などの長期間も可能ですが。
手術については、昔は手術中だけ痛みが取れればいいという考え方でした。ですから、手術後は病棟で鎮痛剤を打つという方法でした。でも、今は周術期という考え方で、全体を通して痛みをとるよう努めます。とくに最近は、入院期間を短くすることが求められているので、患者さんを早く離床させ、歩かせるためにも、痛みも早くから取ることが求められるようになりました。
同じカテゴリーの最新記事
- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)
- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)
- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)
- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている
- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)
- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)


