免疫ビッグ対談 世界的免疫学者(理化学研究所 免疫・アレルギー総合研究センター長)谷口 克 × 鎌田 實
自己免疫疾患とがんはシーソーの対局
鎌田 私は父親の精子と母親の卵子が結合した受精卵から生まれたわけです。母親にとってみれば受精卵の私は異物=非自己以外のなにものでもなく、排除されてしかるべき対象ですが、なぜ十月十日の間、母親の胎内にいることが可能だったのでしょうか。
谷口 それは、免疫系に抑制機構があり、胎児(非自己)に対する免疫反応を抑えているからです。
先ほど自己反応性T細胞は胸腺の中にいるうちに殺されてしまうといいましたが、すべてのそれが消滅してしまうわけではないのです。約6パーセントの自己反応性T細胞が胸腺から抜け出て、血液中を流れているのです。
では、なぜ体内の自己反応性T細胞が自分の身体を攻撃して膠原病や関節リウマチ等の自己免疫疾患を発症させないのかというと、リンパ球の中に免疫を抑えて制御するリンパ球が存在するからです。NKT細胞、抑制T細胞や免疫制御性T細胞、自己反応性T細胞はもとより、免疫システム全体を抑えるフェイルセーフ機構を形づくっているのです。
鎌田 抑制T細胞などの働きが弱いと自己免疫疾患を発病させてしまいますが、反対にその働きが強すぎるとがんを発病させてしまうのですね。
谷口 そうです。自己免疫疾患とがんは、ちょうどシーソーの反対側に位置しているのです。そういう意味では免疫は非常に危ういシステムだといえます。
免疫療法が効くがんと効かないがん
鎌田 感染症に対してワクチン等の免疫療法は大きな成果をあげましたが、がんに対する免疫療法はどのくらい期待できるものなのでしょうか。
谷口 がんはもともと自己の細胞から発生したものなので、本来、自己と反応しない免疫でがんの治癒をはかるというのはきわめて難しいことなのです。確かにがんにかからない人がいるのは、免疫が細胞のがん化を監視し、その発生を未然に防いでいるからです。しかし、いったん、免疫のバリアーが打ち破られ大きくなったがんを治癒させられるのかというと、それは難しいと言わざるを得ません。がんを攻撃するリンパ球の数に比べてがんのサイズが大きくなったら、これはもう退治するのが難しくなります。がんの増殖のほうが、それを殺すリンパ球の増殖を上回ってしまうし、またがん細胞は免疫抑制物質を出して免疫系を抑制するからです。
鎌田 ここが一番お聞きしたいところです。往復書簡の相手をしてくださっている病気と闘っている一人の女性に何かヒントはないかと思っています。そして、この連載を読んでくださっているたくさんの読者さんに、病気と闘う糸口を提供したい���です。がん治療における三大療法、つまり手術や放射線、抗がん剤による治療が尽きて、免疫療法に望みをつなぐ患者さんは多いのですが、がんに対して免疫療法はまったく歯が立たないのでしょうか。
谷口 いいえ、難しいことは事実なのですが、不可能なことではありません。子どもに見られる神経芽細胞腫というがんがあるのですが、この神経芽細胞腫のあるタイプ(IV S型)は患者さんの自前の免疫力だけで治ってしまいます。全身に転移していても、免疫の力だけでがんが死滅し完治してしまうのですから、免疫によるがん治療の可能性を照らし出し、非常に勇気づけられることだといえます。また、皮膚がんの一種であるメラノーマも免疫で治せる可能性が大きいといわれています。いずれも自己と異なるという証の抗原が強くがん細胞の表面に出てくるので、キラーT細胞などによって死滅させることができるのです。しかし、それ以外の多くのがん、すなわち乳がんや大腸がん、肺がん等では抗原が強く出てこないので、なにも工夫しなければ免疫で治癒させることはできません。
免疫療法をがん治療に活かす方法
鎌田 がん治療に免疫を役立てるためには工夫が求められるのですね。具体的にはどのような工夫が必要なのでしょうか。
谷口 がん細胞やがん抗原(ペプチド)で患者さんのリンパ球を試験管内で刺激し続けると、がん細胞に特異的に反応・攻撃するキラーT細胞が誘導されることがわかっています。リンパ球をいったん体外へ出して育て、再び患者に戻す養子免疫療法の一種です。副鼻腔にできる上顎がんに対し、がん細胞に特異的となったキラーT細胞を患者さんの血液に戻して優れた成果をあげています。すなわち試験管内でつくったキラーT細胞(10の9乗個)を上顎動脈へ9~10回繰り返し注射で投与すると、鶏卵大の腫瘍が縮小し、蓄膿症程度の軽い手術でがんが摘出できることが示されたのです。
それまで上顎がんの治療は眼球の摘出や顔面の欠損などが不可避だったことから、患者にとって大きな福音となりました。熊本大学医学部の石川哮前教授が始めた治療法で、成功した要因は上顎がんを支配している動脈が上顎動脈の1本だけで、そこにキラーT細胞を投与すると効率よく上顎がんに送り込めて破壊することができたからです。免疫をがん治療に活かすには、このようにさまざまな工夫が必要です。工夫することに成功すれば、免疫療法の可能性は大いに切り拓かれると思います。
鎌田 免疫療法をがん治療に活かす工夫にはどのようなものがあるのですか。
谷口 もっとも重要なのが、がん細胞を攻撃する特異的なリンパ球を増やしてあげることなのです。一つはがん抗原(ペプチド)をがん患者さんの身体に注射し、体内でそれに反応するキラーT細胞をどんどん増やすという方法があります。もう一つは今お話した患者さんから採取したリンパ球をペプチドなどで刺激し、試験管の中で特異的なキラーT細胞を増やしてそれを患者に戻してあげるという先の養子免疫療法です。今はキラーT細胞を1、2週間であっという間に1億個まで増やすことができるのです。そのうえで本当にがん細胞を特異的に攻撃するキラーT細胞のクローンが増えているのか、あるいは増えたクローンにがん細胞を攻撃する機能が保持されているのかなどを確かめながら治療に応用することが求められています。
鎌田 すでに臨床で試みているところはあるのですか。
谷口 久留米大学医学部の伊東恭悟教授の免疫学教室をはじめ、いくつかの施設などでもその試みが始められようとしています。ペプチド・ワクチン療法といいます。ペプチド・ワクチン療法はがん抗原の存在するペプチド(タンパク質を構成する小さな単位で、アミノ酸が9つくらいつながったもの)をがん患者さんに注射で投与し、がん細胞を特異的に死滅させるキラーT細胞を増やすという免疫療法です。現在、どのような間隔で投与すればいいのか、どのようにキラーT細胞が増やせるのかを研究中です。
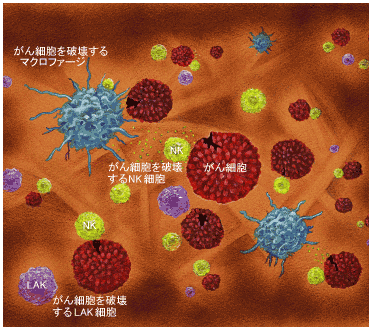
キラーT細胞やマクロファージ、LAK(リンフォカイン活性化キラー)細胞
などの免疫細胞ががん細胞を破壊する
同じカテゴリーの最新記事
- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)
- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)
- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)
- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている
- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)
- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)


