- ホーム >
- 連載 >
- 「がんばらない」の医師 鎌田 實 >
- 鎌田 實 コラム
鎌田實の「がんばらない&あきらめない」読者との座談会 一緒に考え、一緒に解決に向かう医療なら、厳しくても前を向ける 患者は泣きたいときに泣くところがないのがつらい
患者にとって良い病院とは

鎌田 沖原さんは、クリニックの内科医から大学病院を紹介されて行ったということですが、今、がんになっても有名な大学病院に行きますか。
沖原 行きません。肺がんになったときお世話になった先生は、今でも高く評価していて、肺に影があると言われた方から医者を紹介してほしいと頼まれれば、今は他の病院に移られたその先生を紹介しています。でも以前のように大病院がいいという考えは、今は持っていません。じつは私、来月、子宮筋腫の手術を受けるんですが、中規模の病院を選びました。
鎌田 そうした理由は?
沖原 先月父が急性骨髄性白血病で亡くなったんですが、はじめ家の近くの大学病院に行ったら呆れるほど無責任な対応をされたんです。父は近くの病院で糖尿病の検査を定期的に受けていたんですが、血液異常がわかって急性骨髄性白血病の疑いがあるということで、その大学病院に送られたんです。
その病院に行ったら、検査をやり直す必要があるということで、2日後にまた来るよう言われたんですね。言われたとおり2日後に父、母ともう1度行って結果を尋ねたら「2日前に見たデータよりさらに悪くなっている。この状況だと輸血だけなら1、2カ月の命です」と言われたんです。そう言っておきながら、「ウチには現在ベッドに空きがないのでいつ入れるかわかりません。治療しないのなら、ホスピスか長期療養を考えてください」と言い出したんです。でも、そんなことって有り得ない話なので、「あと1、2カ月の命の患者を受け付ける長期療養施設なんかないし、ホスピスも適用じゃないと思いますが」って反論したんです。
鎌田 たしかにホスピスは適用じゃないです���。
沖原 そうですよね。ところがそのお医者さんは「適用ですよ」と言い張るんです。これにカチンときたんで、「他の病院を探しますから、データをください」と言ったんですね。そしたら「そうなさるんでしたらウチではもう診ません、骨髄穿刺もしません」と言われちゃったんです。そうなると他を探しても受け入れてくれる病院が見つからない場合、救急車で駆け込むところがなくなると思ったんで、仕方なく「じゃあ、こちらで治療を受けることにします」と折れて、父にその日予定されていた骨髄穿刺を受けてもらったんです。
その間を利用して、私のほうは、知り合いに電話をかけ、受け入れてくれる病院を探したんです。そしたら、あまり規模の大きくない民間病院が受け入れてくれることになって、翌日その病院に早速入院し、骨髄穿刺もやり直したんです。
そのあと、最初に行った大学のほうにも予約をキャンセルする電話を入れたんです。そしたら「ホスピスは適用」と言い張った例の先生が電話口に出たので、「すでに他の病院に入院し、骨髄穿刺の結果もこちらのほうが早く出ますので、行く必要がなくなりました。申し訳ありませんがキャンセルさせていただきます」と伝えたんです。
そしたら、その先生が「ああ、良かった、ホッとしました。もし、次に来院されたとき、ウチのほうでまだベッドの空きがなかったら、その病院を紹介しようと思っていたんですよ」と言ったんで、もう、呆れ果ててしまったんです。それに比べて、父を受け入れてくれた民間の病院は、お医者さんがたいへん優しい方で、病院のケアも行き届いていたんですね。それで、子宮筋腫の手術は、絶対、中規模クラスのところで受けようと思ったんです。
鎌田 その事件があったんで、すっかり大病院不信になったと。
沖原 はい。日本のがん医療は私が肺がんになった9年前に比べ、いいほうに向かっていると思っていただけにショックは大きかったですね。
体はひとつしかないから実験できない
鎌田 小川さんは、お医者さんとのしっかりした信頼関係ができていたようですが、どんなところから信頼は生まれるとお考えですか。
小川 私がお世話になっている大学病院は、外科も内科もそれぞれグループを作ってお医者さんたちが患者のデータを持ち寄って討議するんですね。
しかも、どんな討議が行われたか、患者に教えてくれるんです。私のデータを内科の先生方で討議したときは、主治医の先生が「グループ討議ではこんな意見が多かったけど、ぼくはこう思っているんです。小川さんはどう思いますか?」と、すべてをオープンにして、私に意見も訊くんです。ときには、お医者さんの意見が真っ二つに割れた結果、私の希望が最優先に考慮されることさえあるんです。
鎌田 それは、どんなときですか。
小川 私、手術から2年2カ月後の昨年3月に再発したので、術後1年間やったときと同様に、ジェムザール単剤による抗がん剤治療を受けたんです。でも、それが、そろそろ1年になるので続けるか止めるか、お医者さんたちで討議したんです。
そしたら「1度転移しているんだから続けるべき」という意見と、「このまま続けると、いい細胞もボロボロになってしまうから、そろそろ休んだほうがいい」という意見が拮抗して真っ二つに分かれたようなんです。主治医の先生はそれを私に伝えたうえで、自分としては止めたほうがいいとおっしゃるんですね。私もそれに乗っかっちゃったんです。最初のときと違って味覚障害が出ていたし、空しさも感じていたので止めることにしたんです。
鎌田 で、現在は、休んでいるんですか。
小川 はい。今年7月で止めました。気になったのは、がんが再発したのは術後1年で抗がん剤を止めてしまったことが原因ではないかという点でした。それに関しては「続けていたら出なかったとも、続けなかったから出たとも言えないので、何とも言えない。体はひとつしかないんだから、実験はできませんから」とおっしゃったんで、それはそうだと思い納得しました。
鎌田 今のお話でいいのは、答えが1つではないとき、あるいは、わからないとき、お医者さんがプロセスをすべて患者さんに話し、患者さんも一緒になって意思決定に参加していることですね。それだと、結果はどうあれ自分も納得して決めたことだから、受け入れられるんですね。小川さんの状況は厳しいんだけど、そうやってニコニコしながら言えるのも、納得しているからなんだと思います。
小川 おっしゃるとおりです。
鎌田 きちっと自分の体のことを全部丁寧に説明してくれる医療があって、しかも一緒に考えてくれて、一緒に解決に向かう医療であれば、厳しくても前を向けるんですよね。
患者会に入ることの大切さを認識して欲しい
鎌田 北田さんは、医者との信頼感に関してはどうでしたか。
北田 私を診てくれている先生は無口でつっけんどんな感じの方なんで、夫は初めあまり印象がよくなかったんですが、同じ病室に乳がんの再発で入院している方がいて、「あなた、ここに来てよかったわよ。あの先生は無愛想で、言い方もぶっきらぼうだけど、すごく信頼できる先生だから」とおっしゃるんですよ。すごく信頼している方のお話でしたから、それでイメージが変わりました。そのあと、その方が主宰する乳がんの患者会に入ったんですが、その先生はよく医療相談とか講演に来てくださっていて、懇親会なんかでお話しをする機会もできたんです。
そんな席では先生もリラックスして本音が出るんです。それを聞いてると、先生が医療に対して前向きで、しっかりした考えを持ってらっしゃることがすごくよくわかるんですね。それがわかってからは診察室では優しい言葉をかけてもらえなくても、平気になりました。治療のほうは腕のいい、この先生。心のほうは精神科の先生に頼ると、分けて考えることができるようになりましたから(笑)。
沖原 心のケアをしてくれる人はたしかに必要ですよね。精神科医だけじゃなく、私のように臨床心理士のところに通うのでもいいと思います。それに加え人柄のいい内科医も不可欠だと思うんですよ。私の場合、最初に診てくれた近所の内科の先生がずっとフォローしてくれて「明日入院で、何日に手術です」と報告に行くと「寝られてる? 食べられてる?」という感じで声をかけてもらって、その後も「もし不安だったら、来ていいよ」「風邪ひきそうだったら、薬出してあげるね」って、やさしくフォローしてくださったんで、本当に助かりました。
小川 私の場合、近所のかかりつけの先生ではなかったですが、同じ大学病院の内科の先生が、手術で外科に移ってからもずっとケアしてくれて、外科と平行して通っていたんです。その先生が良く話を聞いてくださって、わからないことにも答えていただいて、それが私にとってのセカンドオピニオンになっていましたね。
沖原 外科医は人柄より腕、内科は人柄、そして必要なときカウンセリングしてくれる心の専門家、私はこれがセットになれば理想だと思っています。私の場合、主治医の先生は腕も良く、必要な情報は何でも提供してくれる優秀な方でしたが、それでも、心のケアは別に必要でしたね。
鎌田 今のお話は、この雑誌の読者にはいいヒントですよ。
北田 その三位一体に加え、もう1つ、患者会に入ることも、それに匹敵する重要な要素だと思います。ぜひ、そのことを認識していただきたいですね。
私は乳がんの患者会に入っているんですが、抗がん剤で落ち込んでいる患者には、そこに行けば笑える場所って必要なんですよ。とくに乳がんの場合、女ばかりですから、患者同士「髪の毛、抜けちゃった」「半年もすれば、こうなるから大丈夫よ」と笑いながら、言い合えるんですね。私は抗がん剤で苦しんで、うつ状態になったときは、もう一生笑わない人間になるんじゃないかと思ったくらいですが、患者会に入って、同じ状況に置かれた人たちと知り合い、自分のがんを笑いながら話せるようになりました。
「泣き部屋」があればいい
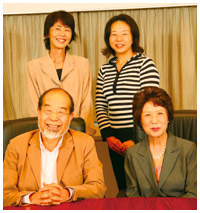
鎌田 家族、友人では解決できない問題も、患者会で新しい人間関係を作っていけば解決できることが多いでしょうしねぇ。最後に、これだけは言っておきたいということがあったらおっしゃってください。
沖原 がん患者の心のケアを十分にやろうというのなら、病院に「泣き部屋」みたいなものがあったほうがいいと思うんです。私の場合、リンパ節転移がわかったとき、順番待ちの椅子が廊下にあるだけだったので、トイレで泣くしかなかったんですね。
そのときは、泣ける場所があればどんなにいいかと思いました。できれば泣き部屋には、常時ボランティアがいて、自分の感情を言葉にしてぶつけたい人にはサンドバッグになってあげ、ただ泣きたい人には気が済むまで泣かせて見守ってあげるというスタイルができたら最高なんですけどね。
鎌田 泣く場所が必要だということは、私も病院の中側にいる人間として、勉強になりました。これについては「がんサポート」などで、提言していく価値のある問題だと思います。
話は尽きませんが本日は、普段気が付かない貴重なお話を伺うことができたいへん勉強になりました。本日は遠いところを、どうもありがとうございました。
(構成/吉田健城)


