「がんばらない」の医師 鎌田實とがん患者の心の往復書簡 松村尚美さん編 第1回
簡単ではないですね。患者さんは無理しなくていい。ぼくら医療者ががんばります。

かまた みのる
1948年東京生まれ。1974年東京医科歯科大学医学部卒業。長野県茅野市の諏訪中央病院院長を経て、現在管理者に。がん末期患者、お年寄りへの24時間体制の訪問看護など、地域に密着した医療に取り組んできた。チェルノブイリの救援活動にも参加。著書『がんばらない』『あきらめない』(ともに集英社刊)がベストセラー。医療者と患者の心のかよい、患者と家族のあたたかい絆、看護師さんたちの献身などが描かれ、評判に。
医療者・鎌田實さんから がん患者・松村尚美さんへの書簡
お手紙、何度も読み返しています。
このような往復書簡、最初すぐにお断りいたしました。ミハエル・エンデの「モモ」に出てくる時間泥棒に時間をとられてしまったぼくは、とても忙しくて余裕がなく、お断りしたのです。松村さんも、日本のお医者さんはなんでこんなに忙しいのですかと疑問をもたれていますね。あとでゆっくりお答えします。時間を奪われているぼくが、編集者の熱い思いに負けてしまいました。
初めて聞く言葉でした。「がん難民」。悲しい言葉です。がんが再発した人が漂流していると聞かされました。どうしたらよいのかわからない。どこへ行ったらよいのかわからない。たくさんの人が困っている。だから「がんサポート」という新しいスタイルの雑誌を作りたいんだ。
この国は、国を失った難民にも冷たい国ですが、進行したがん患者さんにも冷たい国だと思います。あたたかな医療ってどんな医療かずっと考えてきました。地域の人々と健康づくり運動をしながら、「攻める医療」の救急医療と高度医療を充実させて、脳卒中やがんの患者さんを最後まで見放さない「支える医療」との調和が大切と考えてきました。患者さんの希望の灯を消すことなく、真に安心できる医療や自宅でのあたたかいケアを受けられる医療システムをつくることに精出してきました。
病院のスタッフががんばる

書斎の机に向かって松村さんへの手紙を
したためる鎌田さん
「がんばらない」。本当にそんなことができるのでしょうかとおたずねですが、簡単ではないですね。とにかく日本人は「がんばる」のが好きですから。 ぼく自身、なんのために、なぜ、どのようにがんばればよいかも考えずに、「がんばろう」とか、「がんばれ」と声をかけている自分に気がついて、つい笑ってしまいます。
ぼくらの病院のラウンジには「がんばらない」「あきらめない」という障害者が書いた字の額がかかっています。お父さんも、養護の先生もその障害者に「がんばれ、がんばれ」と声をかけてきました。それは、その子が一人になってもしっかり生きてもらいたいとの愛情から発したものだと思います。しかし、その子にしてみれば、自分がどんなにがんばっても健康な子には勝てなかった。そんながんばれない自分にある日気がついて、書いたのがその言葉だったのです。
ぼくはこれを見て、この「がんばれ」は、健康な人と障害者の間だけではなく、医療を供給する側と受ける側との間にも横たわっている大きな問題だと思いました。病気を患っている患者さんは、それを払いのけようとがんばっています。しかし、がんばってもがんばっても払いのけられない時があるのです。そんな時に他者から発せられる 「がんばれ」という言葉は、時にその人をむち打ち、追い込むことになってしまうことがあります。そしてそのことに気がついているかどうか、それが大切だと思い、この「がんばらない」という言葉を大切にしようと思って本を書いたのです。
だから患者さんは無理してがんばらなくていい。ぼくら病院のスタッフががんばります。そんな気持ちでこの言葉を使ったのです。 患者さんが、その人らしく、ていねいに生きられるように、こちらの医療側も誠実に、ていねいに医療を提供していきたいと思いました。 医学や科学の力でどうにかしてあげられる時もありますが、全力で立ち向かっても、どうにもできない時もあります。そんな時にでも無理ではない方法で、その方の人生観や生き方にあったやわらかな治療法を見つけだすことはできると思っています。
自分が受けたい医療をつくってきた
がんの治療からターミナルケアまで一貫した医療が欲しい。 症状が進むにつれ、痛みのケアが中心になるが、要所の治療はしたい。こんな治療を受けることは可能ですかとのおたずねですが、可能だと信じています。
病気が進行して一番つらい時ですよね。この時にこそ支える医療が必要なのだと思います。支える医療は痛みだけをとる消極的な医療だけでは、けっしてないのです。
つい最近も、進行した直腸がんの方が東京から来られました。がんが骨盤腔内全体に浸潤して、ねても座っても痛みがとれず、苦しみの中で来られました。緩和ケアの痛みを止めるスペシャリストと、ペインクリニックをやっている麻酔科医と、がんが浸潤して皮膚にろう孔をつくってしまっているので、外科医と泌尿器科、皮膚科医がサポートに入っています。
できるだけあたりまえの生活が、気持ちよく送れるように心がけています。筋肉がおとろえないように理学療法士も、栄養状態をよくして、免疫系を元気にしようと栄養士もサポートに加わっています。自分が病気になった時受けたいような医療をつくってきたつもりですが、まだまだ完成には道は遠いです。
患者の声を聞き、言葉を受け止める
「今この透き通った悲しみを豊かだと感じることがあります」というあなたの言葉に引きつけられました。病気のことを話しあえる主治医と、悲しみを共感してくれるもう一人の主治医がいるとあなたはおっしゃいます。
ぼくは『病院なんか嫌いだ―良医にめぐりあうための10箇条』(集英社新書)という本を最近出しました。その中で「良医」とはなにかを考えてみました。
1.話をよく聞いてくれる
2.わかりやすく説明してくれる
3.薬に頼らず、生活上の注意をしてくれる
4.必要があれば専門医を紹介してくれる
5.家族の気持ちまで考えてくれる
6.地域の医療・福祉を熟知していて、必要な時に紹介してくれる
7.医療の限界を知っている
8.患者の悲しみ・つらさを理解してくれている
9.ほかの医者の診察(セカンドオピニオン)を受けることを快く受け入れてくれる
10.本当のことをショックなく教えてくれる医師。
あなたのお二人の主治医の特長を足すと、この10箇条の多くを偶然満たしているように思うのです。
いままで大学や大病院ではこういう医師を育ててくれませんでした。今年から研修医をとって、ていねいに教育してみたいと思っています。少しずつでも良くなることが大切だと思っています。
日本の医療は20世紀の後半に大変な進歩をしました。しかし、進歩とともに医療から、優しさや、あたたかさが減っていきました。冷たい医療がおこなわれ、脳卒中やがんでつらい時に、見放す医療や、放り出す医療が蔓延しています。医療は優しくなくちゃあ、医療じゃないって考えてきました。
日本の医療の中で特に欠けているのは患者の声を聞き、言葉を受け止めるということ、抗がん剤の投与、放射線治療、手術をするなど、攻める医療や高度医療の手段はなくなったとしても、支える医療は、その人が生きている限りあるはずだと思ってきました。
医学の道へ誘った重い病気
「豊かな時を過ごしています」という松村さんの言葉、すごいと思います。ぼく自身も精いっぱいていねいに生きていかなければと思いました。ありがとうございました。
最後になりますが、「がんばらない」のドラマの女優さんがステキだったとのこと、本当にステキな方でした。女優としても魅力的でしたが、それ以上に人間として美しい方でした。ご自分が直腸がんの手術をなさり、人工肛門になられ、女性が社会的活動を続けるため工夫をされ、どんなにハードな、長時間の仕事でも耐えられるような方法を考案し、それを公開しています。頭が下がります。

鎌田さんが松村さんにサイン入りで贈った
著書『あきらめない』
生きるということは、どんな人も、何かを背負って生きているのかもしれません。厳しい状況の中で、ぼくらがおこなっている医療や科学の常識を超えて生きられている方々のことを書いた『あきらめない』(集英社)をお贈りします。お時間がある時にお目通しいただければ幸いです。自分がこうして生きていることも、医師としての仕事をさせていただいていることも不思議です。自分一人で生きられない時に、食べるのも苦労している時にぼくをひろってくれ育ててくれた人が、重い病気を持っていたこと、それがぼくを医学への道へ進めました。この国の医療界の中で「医療は優しくなくちゃ医療じゃない」と変わったことを言い切れる自分をつくってくれたのは、貧しい中で育ててくれた義父だったと思います。
昨晩にかけて、里に雪がつもり、病院の周りは白い世界となりました。東京の人間ですが、雪は嫌いではありません。寒くて、厳しい、ちょっと暗い冬もいいものです。松村さんは昔、スキーをなさったとのこと。お時間をつくって信州へ雪を見にいらっしゃいませんか。長くなってしまいました。筆をおきます。ありがとうございました。どうぞご自愛を。
松村尚美さま
2003 冬 鎌田 實
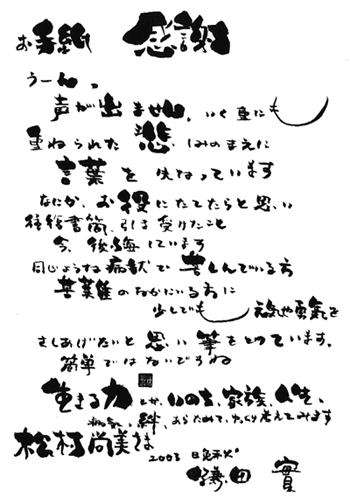
鎌田實さん直筆の個性的な、味わい深い手紙
同じカテゴリーの最新記事
- 「がんばらない」の医師 鎌田實とがん患者のこころの往復書簡 金子淑江さん編 第3回
- 「がんばらない」の医師 鎌田實とがん患者のこころの往復書簡 金子淑江さん編 第2回
- 「がんばらない」の医師 鎌田實とがん患者のこころの往復書簡 金子淑江さん編 第1回
- 「がんばらない」の医師 鎌田實とがん患者の心の往復書簡 松村尚美さん編 鎌田實から松村尚美さんへの最後の書簡
- 「がんばらない」の医師 鎌田實とがん患者の心の往復書簡 松村尚美さん編 第9回
- 「がんばらない」の医師 鎌田實とがん患者の心の往復書簡 松村尚美さん編 第8回
- 「がんばらない」の医師 鎌田實とがん患者の心の往復書簡 松村尚美さん編 第7回
- 「がんばらない」の医師 鎌田實とがん患者の心の往復書簡 松村尚美さん編 第6回
- 「がんばらない」の医師 鎌田實とがん患者の心の往復書簡 松村尚美さん編 第5回


